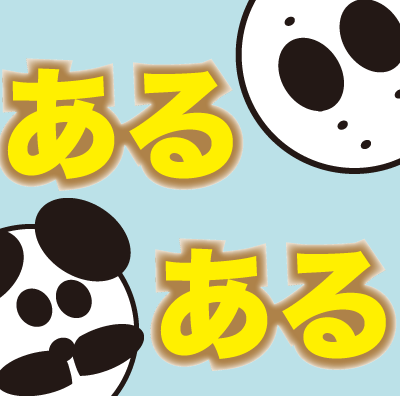『受験勉強で悩んで、ネガティブになってきたら見るブログ』中学生・高校生のあるある研究所<朝日新聞掲載>
勉強ができる人って努力してなさそうに見えて、劣等感感じますよね。 『頑張れ!』って言いません。だって頑張れないもん。 「悩んでも、大丈夫。」僕らがあなたを応援します。 『中高生の勉強あるある、解決します。』という書籍もよかったらお読みください
プロフィール
テーマ
最新の記事
カレンダー
月別
ブックマーク
ブログ内検索
はじめまして!
あるある研究所です!
================
『中高生の勉強あるある、解決します。』
がブログから書籍化しました!
================

著者は現役大学生!

なんとあのカリスマ予備校講師「安河内哲也先生」
おすすめの、勉強をサポートする画期的な本なんです!
例えるならば、『ドラえもん』のような存在!
「やる気がでないよ~」
「問題集の使い方がわかんないよ~」
「ケアレスミスしちゃうよ~」
そんな時、みんなは、どうしてる?・・・『頑張る!><』って人が多いんじゃないかな?
僕らは『具体的な工夫』=”ヒミツ道具”をみんなに伝えています!
だから、「辛くない!」「楽しくなる!」「悩んでもいいんだ」って
安心して、毎日を過ごす事ができるはず!
先生や親御さんに「頑張れ!」って言われて、
『そんなこといってもどうすればいいんだー』
って思ってる人の力になりたいんです。
僕らが昔は悩んだので!(「帰宅部、ネガティブ、Youtube」の無気力高校生でしたwww)
本は、こんな感じで、、、(恋のあるあるもあったりw)

ブログっぽくて、、、

読みやすくて、、、(ネガティブになることもあるよねw)

面白い!

☆動画解説も!(著者が解説しちゃいます!)
twitterもやってます。
@aruaru_nonaka

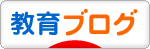
にほんブログ村
あるある研究所です!
================
『中高生の勉強あるある、解決します。』
がブログから書籍化しました!
================

著者は現役大学生!

なんとあのカリスマ予備校講師「安河内哲也先生」
おすすめの、勉強をサポートする画期的な本なんです!
例えるならば、『ドラえもん』のような存在!
「やる気がでないよ~」
「問題集の使い方がわかんないよ~」
「ケアレスミスしちゃうよ~」
そんな時、みんなは、どうしてる?・・・『頑張る!><』って人が多いんじゃないかな?
僕らは『具体的な工夫』=”ヒミツ道具”をみんなに伝えています!
だから、「辛くない!」「楽しくなる!」「悩んでもいいんだ」って
安心して、毎日を過ごす事ができるはず!
先生や親御さんに「頑張れ!」って言われて、
『そんなこといってもどうすればいいんだー』
って思ってる人の力になりたいんです。
僕らが昔は悩んだので!(「帰宅部、ネガティブ、Youtube」の無気力高校生でしたwww)
本は、こんな感じで、、、(恋のあるあるもあったりw)

ブログっぽくて、、、

読みやすくて、、、(ネガティブになることもあるよねw)

面白い!

☆動画解説も!(著者が解説しちゃいます!)
twitterもやってます。
@aruaru_nonaka

にほんブログ村
2016-09-21 20:29:32
マイナス思考だからいい
テーマ:ブログ
プラス思考とマイナス思考。
ポジティブとネガティブ。
明るい性格と暗い性格。
よく対立されるものだけど、人間ってこう簡単に二極分化できるものでもない気がする。人間は常に2面性を持っていてプラス思考になれる時もあれば、その逆でマイナス思考が前面に出てくる日だってある。
しかし、マイナス思考やネガティブであることが「ダメだ」と感じている人が多いと思う。
でも、そもそもマイナス思考やネガティブでなければ不満や不安を抱いたり、悩むことなんてない。
悩まなければ、解決もしない。
つまり、世の中で何かを解決しよう、成し遂げようとする人は全員が一時的にネガティブだったはず。
受験でいえば、「落ちたらどうしよう・・・」「受かるかな・・・」「全然点数が伸びない・・・」などとほぼ受験生全員がネガティブな感情に支配される。
けれど、ここで「じゃあ、どうしたら受かるかな!」と次のステージへと足を踏み出せる人が結局、合格していく人。
つまり、「マイナス思考」や「ネガティブ」で終わらない人。
マイナス思考やネガティブは、達成するという道の中で最初の段階では絶対に必要な感情。
でも、そこで止めてはもったいない。せっかく悩めているんだから「解決」へ向かうようにしてほしいな。
マイナス思考はいい。マイナス思考だからいい。
でもそこで終わらない。
2016-09-18 16:51:47
なにを勉強しないかの勇気ある決断
テーマ:勉強法(悩みや失敗)
生徒からのよくある質問が『どんな参考書を使ったらいいですか?』っていうもの。
正直、「やれるもんなら全部やったほうがいいに決まってる」と思う。
だけど、入試までという時間制約の中で「こなせる絶対量」は限られてる。
だからむしろ『なにはやらないか』の方が重要。
予備校での授業案を考える時も、『このクラスでは、何は教えないか』のほうから考えるとうまくいくことが多い。
最近は、大学生の講師からどう授業づくりをしたらいいのかを聞かれることもあるけどそういうときは『宿題を何だすかから決めるといい』と伝えてる。
宿題から先に考えると授業中に『これは教えなきゃいけない、これは言わなくていい』ってことがハッキリするから。
生徒自身も受験というイベントが時間制限があるものってことを今以上にリアルな問題として心に刻み、勇気をもって『どこまで勉強するか。なにはやらないか。』を決断してほしいな。
▼・ω・▼
2016-09-17 17:11:29
再現性のある技術にできるか
テーマ:ブログ
日々、授業していく中で思うことは『授業で理解させること』は当たり前として、それを生徒たちがいつでもどこでも『再現できるもの』へと昇華させるようサポートすること。
今日、この授業1コマでの問題の出来不出来なんてどうでもよくて、結局その内容が最終的に『なんの違和感も迷いもなく、自分の知恵、技術として再現できる』ようになるのが大事だと感じる。
再現できるようになるってことは、授業ができるようになるってこと。
つまり「人に教えることができる」ということ。
だから生徒におススメするのは、「セルフ講義」。
自分で自分に授業をしてみる。
人に教えるとなると、本当の意味での『理解』をしていないところは絶対につまってしまう。
もしくは、問題演習の時に細かく文章を記述してみること。つまり論証をがっつり行うこと。
それが、スラスラできるようになればもう大丈夫。
2016-09-17 02:52:45
ゾンビな受験生が合格する
テーマ:ブログ
毎年、受かる受験生は『ゾンビ』みたいな精神を持ってると思う。
何度も、何度も立ち上がる不死身な精神の持ち主。
単語が覚えられない、模試でE判定、確認テストで20点しかとれない。受験勉強なんて『失敗の連続』なんだよね。
でも、そのつど「何が悪かったのか修正して」いく諦めない精神が合格へと近づけていく。
とくに夏終わりは少し受験生のテンションが低いね。
本格的に『やばい!』って気持ちが先行してきてるんだよね。
やばいって思うことは問題ないけど、一番まずいのはそれで「立ち止まる」こと。
ポジティブだろうが、ネガティブだろうが、メンヘラだろうが、とにかく『動いて』いればいい。
たとえくじけても、そのままにするんじゃなくてそれを乗り越えるゾンビのような受験生が最後は受かると思う。
2016-09-16 14:43:45
あれから5年。
テーマ:ブログ2011年の9月16日。
『中高生の勉強あるある、解決します。』が発売された日。
 | 中高生の勉強あるある、解決します。 1,404円 Amazon |
当時、大学生である自分(池末翔太)と、相方(野中祥平)が必死で命がけで書いた1冊。
もう5年もたったのか。と思う反面、まだ5年なのかと思うこともある。
でもよく考えれば、当時の読者はもう大学生になったり、下手したら社会人になってたりするんだよね。そう思うとずいぶん時間たったて思うね。
本を出してから人生は変わった気がする。
本を出そうとガンバったから変わったのかな?
大学生という肩書はなくなり、昔からの目標だった「予備校講師」となり、大学受験の指導をしている今現在。
この5年間で本は合計6冊ほど書いてきたけど、ブログの記事を書くのは久しぶりで緊張するね。
いつも思うことだけど、『初心を思い出す』ことはできても、『初心に戻ること』はできないと思う。だから、5年前、書いてた記事とはまた全然異なるノリ、雰囲気、文章、コトバ選びになるけどしばらく気ままにまたちょこっとの間だけ、最近の受験生について思うこととか、自分自身の気づきとか好き勝手に書いてみようと思う。
2014-08-08 12:53:41
夏期講習波動ゼミしゅーりょー
テーマ:ブログどーも!
パグ夫です。▼^ω^▼
今日で5日間の高2物理ゼミ「波動」が終わったー。
テキストの問題全部きっちり終われてよかったw
波動分野は、難関大学でこそ差がつきやすいから、高2のうちにある程度固めておくのはすごく有理になるよね。
夏休みはまだまだ半分以上残ってるので、中高生のみんなはしっかりと学んだことの復習してくれるといいな~。
やっぱり、どの年代の子も「目的意識を持ってるか」、「なんとなくで夏休み勉強するか」で大きく変わるよね。
勉強をやらされている感を出してる学生って、たいして伸びることないんだよね。
どれだけ、自分事にできるかって大事。
自分から、進んでペンを持つことができるかが、成長できるかの右左大きく別れる道になってると思う。
読者のみなさんも、残りの夏休み、積極的に勉強楽しんじゃってください!!ww
受験該当学年以外の人は、遊びも適度に入れてね!w
今年受験する人は、遊びは基本しないほうがいいかもw
パグ夫です。▼^ω^▼
今日で5日間の高2物理ゼミ「波動」が終わったー。
テキストの問題全部きっちり終われてよかったw
波動分野は、難関大学でこそ差がつきやすいから、高2のうちにある程度固めておくのはすごく有理になるよね。
夏休みはまだまだ半分以上残ってるので、中高生のみんなはしっかりと学んだことの復習してくれるといいな~。
やっぱり、どの年代の子も「目的意識を持ってるか」、「なんとなくで夏休み勉強するか」で大きく変わるよね。
勉強をやらされている感を出してる学生って、たいして伸びることないんだよね。
どれだけ、自分事にできるかって大事。
自分から、進んでペンを持つことができるかが、成長できるかの右左大きく別れる道になってると思う。
読者のみなさんも、残りの夏休み、積極的に勉強楽しんじゃってください!!ww
受験該当学年以外の人は、遊びも適度に入れてね!w
今年受験する人は、遊びは基本しないほうがいいかもw
2014-08-04 03:49:11
夏期講習スタート!!
テーマ:ブログどーも。
こんにちは。パグ夫です▼^ω^▼
予備校で物理を教えている僕ですが、今日から夏期講習がスタートします!
5日間の高2物理ゼミを担当してます。
内容は「波動分野」です。
波の基本、反射波、定常波、弦や気柱の振動、ドップラー効果が主になりますね~。
まあ、光以外の波動分野だね。
波動は、物理の中でも結構独立してる単元だから、夏期講習とかでグッと集中的にやっちゃうのがいいよね。
波動むずかしいよねw
高校生の頃の自分はとにかく公式丸暗記しちゃってたなwでもそれで定期テストはそこそこ点が取れたりしてww
波動を基礎から分かりやすく伝えるようがんばるぞーさん!!
高校生で物理取ってる人しかわからない話ですねw
ノナのお兄ちゃんの講演あるんだ!!聞きに行きたいなw↓
ノナbrother講演会
こんにちは。パグ夫です▼^ω^▼
予備校で物理を教えている僕ですが、今日から夏期講習がスタートします!
5日間の高2物理ゼミを担当してます。
内容は「波動分野」です。
波の基本、反射波、定常波、弦や気柱の振動、ドップラー効果が主になりますね~。
まあ、光以外の波動分野だね。
波動は、物理の中でも結構独立してる単元だから、夏期講習とかでグッと集中的にやっちゃうのがいいよね。
波動むずかしいよねw
高校生の頃の自分はとにかく公式丸暗記しちゃってたなwでもそれで定期テストはそこそこ点が取れたりしてww
波動を基礎から分かりやすく伝えるようがんばるぞーさん!!
高校生で物理取ってる人しかわからない話ですねw
ノナのお兄ちゃんの講演あるんだ!!聞きに行きたいなw↓
ノナbrother講演会
2014-08-03 06:43:24
お兄さんの公開講座!『なんでそんなふうに言ったんだろう?~「なぜ」に迫る言語学~』
テーマ:ブログこんにちは。
のなです(00)/
8月ですね!
本格的に暑いですね~。
暑いとだらけますが、夏と言えばみなさん
メリハリついてますかね?
僕の高校時代を思い返すと、
これといった特別なイベントが少なく
けっこうダラダラしちゃっていたように感じますw
じゃあどーすればいいのか?って考えると、
自分から何かを発見したりどっかにでかけてみたり、
自由研究的に何か自分でプロジェクトしてみるのが
おすすめです!
(ちなみに最近パグ夫に触発されて運動始めました、プールに週に1回行こうかなと)
さて、遊んでばかりもいられない夏休みですが、
息抜きにもなるおすすめのイベントを紹介です!
そのテーマは、「コトバ」です!
コトバ・・・よく考えると僕らはコトバを使って考えて、
コトバを使ってコミュニケーションしているわけですが、
「コトバって僕らは普段どのように使ってるんだろうか?」
「なんであの時そんな風に言ったんだろうか?」
ってことに好奇心をもってみましょというのがこの公開セミナーのテーマです。
たとえば、
■「彼は顔が赤い」と「彼の顔が赤い」は同じ意味だろうか?
■「財布が見つかった」と「財布を見つけた」は何が違うのか?
などなど、普段自分が使っているコトバでも、
ひとつひとつ?をもって観るとなんだか変な気分に。。。
(一度疑問を持つとなんだか解説が聞きたくなっちゃうから不思議ですwww)
っと。国語や英語・・・っていう教科から離れてみて、
純粋にコトバそのものを考えてみる機会ってなかなかないですが、
「テストで点を取る!」とは別次元でこういった話を
聞けるのって僕はとっても中高生の時に体験したかったなーと思います。
コトバに興味がある人もそうでない人も、
大学でどんなことしたいのかなって迷ったり考えている人も、
夏にスパイス的なイベントを取り入れたいという人も、
ぜひ無料なので参加してみてね~!
8月9日の土曜日14時から、場所は河合塾本郷校です。
4つ上の僕のお兄さんがお話しますのできっと面白いと思いますー。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
なんでそんなふうに言ったんだろう?~「なぜ」に迫る言語学~
http://www.kawai-juku.ac.jp/event/e-detail.php?eventNum=0000030111&grade=98&area=3
■開催日時 2014年8月9日(土)14:00~16:00
■対象学年 高校生・中学生・保護者
英語や言語学に興味のある中高生ならどなたでも参加できます。ぜひ、ご参加ください。
■講演者 野中 大輔 (K会英語科講師) 東京大学大学院 言語学専攻 ←4つ上の兄貴です。
■参加費 無料
■申込方法 窓口/電話申込
実施校舎の窓口または、下記問い合わせ先にお電話にてお申し込みください。
※ 定員になり次第締め切りとなります。
■お問い合わせ K会事務局(本郷教室) 0120-540-315
■主催 (学)河合塾
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
さて。
僕もコトバを使って考え事、
楽しもうと思います♪
のなです(00)/
8月ですね!
本格的に暑いですね~。
暑いとだらけますが、夏と言えばみなさん
メリハリついてますかね?
僕の高校時代を思い返すと、
これといった特別なイベントが少なく
けっこうダラダラしちゃっていたように感じますw
じゃあどーすればいいのか?って考えると、
自分から何かを発見したりどっかにでかけてみたり、
自由研究的に何か自分でプロジェクトしてみるのが
おすすめです!
(ちなみに最近パグ夫に触発されて運動始めました、プールに週に1回行こうかなと)
さて、遊んでばかりもいられない夏休みですが、
息抜きにもなるおすすめのイベントを紹介です!
そのテーマは、「コトバ」です!
コトバ・・・よく考えると僕らはコトバを使って考えて、
コトバを使ってコミュニケーションしているわけですが、
「コトバって僕らは普段どのように使ってるんだろうか?」
「なんであの時そんな風に言ったんだろうか?」
ってことに好奇心をもってみましょというのがこの公開セミナーのテーマです。
たとえば、
■「彼は顔が赤い」と「彼の顔が赤い」は同じ意味だろうか?
■「財布が見つかった」と「財布を見つけた」は何が違うのか?
などなど、普段自分が使っているコトバでも、
ひとつひとつ?をもって観るとなんだか変な気分に。。。
(一度疑問を持つとなんだか解説が聞きたくなっちゃうから不思議ですwww)
っと。国語や英語・・・っていう教科から離れてみて、
純粋にコトバそのものを考えてみる機会ってなかなかないですが、
「テストで点を取る!」とは別次元でこういった話を
聞けるのって僕はとっても中高生の時に体験したかったなーと思います。
コトバに興味がある人もそうでない人も、
大学でどんなことしたいのかなって迷ったり考えている人も、
夏にスパイス的なイベントを取り入れたいという人も、
ぜひ無料なので参加してみてね~!
8月9日の土曜日14時から、場所は河合塾本郷校です。
4つ上の僕のお兄さんがお話しますのできっと面白いと思いますー。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
なんでそんなふうに言ったんだろう?~「なぜ」に迫る言語学~
http://www.kawai-juku.ac.jp/event/e-detail.php?eventNum=0000030111&grade=98&area=3
■開催日時 2014年8月9日(土)14:00~16:00
■対象学年 高校生・中学生・保護者
英語や言語学に興味のある中高生ならどなたでも参加できます。ぜひ、ご参加ください。
■講演者 野中 大輔 (K会英語科講師) 東京大学大学院 言語学専攻 ←4つ上の兄貴です。
■参加費 無料
■申込方法 窓口/電話申込
実施校舎の窓口または、下記問い合わせ先にお電話にてお申し込みください。
※ 定員になり次第締め切りとなります。
■お問い合わせ K会事務局(本郷教室) 0120-540-315
■主催 (学)河合塾
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
さて。
僕もコトバを使って考え事、
楽しもうと思います♪