今回は過去最多人数となる12名様がご参加くださいました!遠い方はなんと愛知県から♪嬉しいです♡
JR川越駅に集合し、バスで最初の目的地へ🚌
開運の旅の始まりはお城から🏯
『川越城跡(本丸御殿)』
川越城は、室町時代にこの地を治めていた一族である扇谷上杉氏が、ライバル勢力の足利家に対抗するために、長禄元年(1457)家臣の太田道真・道灌父子に命じて築城。江戸時代には江戸の北の守りとして重要視されました。日本で2つしか現存しない本丸御殿があるお城で、2006年に「日本100名城」の一つに選ばれています。
豊臣秀吉の小田原征伐の際に、前田利家の攻撃を受けて落城。徳川家康が関東に配置換えになった時に、川越も家康の領地になりました。以後は徳川家の重臣が城主を務め、天草の乱を鎮圧した松平信綱や、5代将軍綱吉の側近だった柳沢吉保などもこの地を治めています。
家光以降の将軍は川越城を利用しなくなり、本丸御殿は取り壊され、更地のままの状態が続きましたが、嘉永元年(1846)に藩主の住居だった二の丸が火災により焼失。その2年後に藩主の松平斉典が、空き地だった本丸御殿の場所に新しく御殿を建設。それが現在残されている本丸御殿です。
なんと当時の広さは1025坪(約3400㎡)で、16棟の建物を有していたといいますから驚きです。
☆物頭詰所
☆使者の間
明治維新以降、川越城は少しずつ縮小されましたが、大広間・移築復元された家老詰所・玄関などが現存しており、埼玉県の重要文化財に指定されています。
☆大広間
日本で本丸御殿の大広間が現存しているのは、ここ川越城と高知城だけであり、非常に貴重な文化遺産として保存されています。
鎧や熊の毛で作られた手杵が展示されていました🐻
☆家老詰所
☆便所
へぇ〜昔はこんなだったのね🚽
ここが一番印象深かったかも笑
川越城跡の見どころの一つが枯山水の庭園🌳
この後に行く喜多院の曲水の庭に次ぐ古庭園とされています。
川越城跡には七不思議が存在するのでチラッとご紹介。
①初雁の杉
川越城跡のすぐ隣の「三芳野神社」は、元々は川越城内に鎮座していて“お城の天神様”といわれていました。この神社の裏手に見事な杉の木があり、北の空から飛んできた初雁が、毎年一度も忘れることなく必ずこの杉の上で「がぁ〜」と三声鳴きながら三度ぐるっとまわり、南の方へ飛び立ったといいます。このことから川越城は「初雁城」と呼ばれるようになりました。
②霧吹きの井戸
敵が攻めてきた時に井戸の蓋を開けると霧が吹き出て城を隠してくれたという言い伝えがあり、川越城は別名を「霧隠城」とも呼ばれました。
③人身御供
川越城のまわりは土地が柔らかくて沼が多く「七ッ釜」と呼ばれており、大田父子は築城に難儀していました。ある夜のこと、沼の主である龍神様が道真の夢枕に現れて「明朝、一番早く汝のもとに現れた者を人身御供として我に差し出せば築城は成就するだろう」と告げました。そして朝になり一番に現れたのはなんと自分の娘だったのです。道真は驚き、娘に夢のお告げのことを話すと娘は「実は私も父上と同じ夢を見ました。これは龍神様のお告げです。大勢の人のためならば私は生贄になります」といって、皆が止めるのも聞き入れず沼に身を投げ、龍神にその身を捧げました。その後、川越城は見事に完成しました。
④片葉の葦
昔、川越城にお姫様が住んでいましたが、戦に敗れたため夜に乳母に連れられ城を落ち延び、浮島神社の近くの七ッ釜という葦のたくさん生えている沼地のあたりに逃げてきました。するとお姫様は七ッ釜の一つに落ちてしまい、乳母は助けを求めますが誰も来ずどうすることもできません。お姫様は近くの葦の葉にしがみつき這い上がろうとしましたが、葦の葉はもろくちぎれ、片葉を掴んだまま哀れな最期を遂げました。その後、七ッ釜あたりに生い茂る葦はすべて片葉の葦になったということです。
⑤よな川の小石供養
昔、芳野村の名主に「およね」という優しく美しい娘がいました。ある日のこと、殿様の鷹狩りのお供で村へやってきた小姓がおよねに一目惚れし二人は愛し合うように。そしておよねは武士の小姓の家へ嫁ぐのですが姑につらくあたられ毎日が大変でした。ある日のこと、およねは殿様より拝受した大切な皿を誤って一枚割ってしまいます。今まで以上に姑からつらくあたられたおよねはたまりかねて小川に身を投げてしまいました。夫は気も狂わんばかりに毎日小川へ行って「およねやー、およねやー」と呼び続けました。すると川底から「はーい」とおよねが返事をするように聞こえたので、夫も小川に身を投げてしまいました。その後、この小川のそばを通る人が、2人を哀れに思い小石を拾って投げ込むと底から無数の泡が浮いてきました。この小川は「およね川」と呼ばれ、いつの頃からか“夜奈川”や“遊女川”と書いて「よな川」と呼ばれるようになったそうです。
⑥神洗足の井水
太田父子が築城のために堀の水を貯める水源を探していました。道灌は初雁の杉のあたりに清水が湧き出ているのを見つけ、老人に築城のことを話したところ満々と水をたたえた水源地に案内してくれました。そして川越城が完成。その老人は日頃から信仰していた三芳野天神様の化身ということが分かり、老人の浸かっていた井水を「天神洗足の井水」と名付け、後の世に伝えることにしました。この水源地は御門のあたりとも八幡曲輪、三芳野神社付近ともいわれています。
⑦城中蹄の音
江戸時代初期、豪勇で知られた酒井河内守重忠が城主だった頃、夜更けに皆が寝静まると城中にどこからともなく矢叫びや蹄の音がけたたましく聞こえるようになったので、怖くなり易者に占ってもらいました。すると城内に何か戦の図があり、それが災いしているとのこと。宝物庫を調べてみると占い通り、堀川夜討の大戦の屏風画が一双見つかりました。その屏風画の半双を養寿院に寄進したところ、その夜から矢叫びや蹄の音は聞こえず安心して眠れるようになりました。この屏風画は現在も養寿院の秘蔵として残っているそうです。
明日へ続く☆
⭐️鑑定依頼はゆだぽん公式ラインから
※リピーター様は15分2500円〜受付いたします
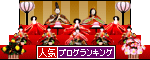
人気ブログランキング













