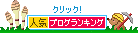昨日、当社禰宜(息子)が、2月初めの珠洲市と輪島市に続いて、能登・穴水町の被災神社支援活動のため、県神道青年会(神主の青年会)の友人たちと早朝5時半に出発しました。
さて、昨日の朝は放射冷却現象でとても寒かったのですが、快晴だったので、昨年11月末に庭師さんによって施された、当社遙拝所前の松や庭の雪吊りを、午前8時より取り外す作業を開始しました。
本来、木々の雪吊りや灯籠への菰巻きは雪害から守るためのものですが、鑑賞を目的とした要素の方が強く、まさに冬の金沢の風物詩です。
なので、当社神役のFさんに手伝ってもらって、まず、遙拝所前の“りんご吊り”から外しました。
剪定バサミで枝との結び目を切っていきます。
ですが、太い孟宗竹の支柱と、その先端から伸びる縄を取り外すのは大変で、途中で縄が枝にからまったりして、やっとのことで2人掛かりで外すことが出来ました。
一番手間のかかる松の雪吊りを外してスッキリしました。
なお、雪吊りに使った縄は、農作業で再利用していただくため、近所の農家の方々にお分けしております。
続いて、当家の庭の雪吊りを外しました。
これは、柊(ひいらぎ)の古木に施された“りんご吊り”ですが、柊の葉には棘(とげ)があって刺さって痛いので、縄の結び目を外すのが大変なのです。
これも、Fさんと2人掛かりで取り外しました。
2人だと作業もはかどります。
最後に、春日灯籠の“菰(こも)巻きを”外しました。
樹木や灯籠への菰巻きは、大変風情があっていいのですが、本当は、越冬の習性を持つマツカレハの幼虫(マツクイムシ)を除去する方法の一つでもあるのです。
前日降った雪で湿っているので、長縄やクズ縄、菰(こも)を半日干しました。
で、先述のとおり、菰巻きの藁には虫がうじゃうじゃいるので、午後からドラム缶の簡易焼却炉で、焼却しました。
再利用できない、短いクズ縄もいっしょに燃やしました。
遙拝前の松も、我が家の庭もようやく春の装いになりました。
そして、昨日は東日本大震災から13年経ったので、近所の真宗大谷派のお寺での、午後2時46分からの鐘撞き堂の鐘の音にあわせて黙祷を捧げました。
これは、勿忘の鐘(わすれなのかね)といって、震災を心に刻むため地震発生時刻に合わせて鐘を打ち鳴らすもので、被災地はもとより、宗派を超えて全国各地の寺院で毎年鳴り響かせています。
今回の能登半島地震同様、「あの日を忘れずに」次の世代へバトンを繋ぐことが重要です。
m(。-_-。)m ↓おねがいします!