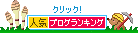4月第3火曜日の昨日は、私が代表をつとめる高齢者を対象とした“地域サロン”開催日で、午後1時半より町内会館で実施いたしました。
今年度第1回目の昨日は、輪島市鳳至町鎮座・住吉神社の禰宜で、石川県神社庁職員(録事)のA君に、「輪島の若手神主が語る地震の惨状」と題して講演いただきました。
A君と当社禰宜(息子)は國學院大學の同級生で、とても仲が良いので、講師をお願いいたしたのですけど、本当は、思い出したくもない記憶ながら、涙目で惨状を語っていただきました。
そして、悲惨な画像の数々を目の当たりにしました。
元日の発災当時ことから、津波から逃れるため神主姿のまま草履も履かずに足袋だけで、近所の氏子さんを誘導しながら高台に避難したこと。
川の水が引いて、消火活動に支障が生じ、朝市通りが完全に鎮火したのは翌朝で、余震の恐怖に加え、多くの方々が避難したため毛布も足りず、寒さに耐えながら眠れぬ夜を過ごしたこと。
翌日撮影した、鳥居や灯籠、玉垣が倒壊し、拝殿の屋根が落ち、本殿や手水舎や渡り殿が全壊して、社務所玄関や室内が崩壊する様、輪島塗職人が多く住む街並みの惨状…。
なお、石川県神社庁HPの被災神社写真をご参照ください、
電気や水も無い中で、携帯もつながらずテレビも見られないため、避難生活での誤った情報の伝達や、正月の食材がなくなって以降、おむすびやカップ麺の日々が続いたこと。
トイレ事情と不衛生によるノロウイルス発症や、避難所でのコロナやインフルの感染が相次いだこと。
自衛隊や他県の消防など救援の方々が来てくださり、自衛隊員による仮設風呂設置により10日ぶりに入浴出来て、本当に有難かったこと。
彼も、1ヶ月間地元に残って避難生活を送りながら支援活動に従事し、2月になってやっと神社庁の職務に復帰しました。
写っている画像は、豪華絢爛な輪島塗の曳山とそれを納める倉庫ですが、神輿庫も含めて全壊するなど甚大な被害となりました。
輪島の春を彩る曳山祭は300年以上の伝統があり、住吉神社では毎年4月4日~5日におこなわれ、華麗な高さ5㍍の山車が輪島の街を練り歩くのですが…。
こんな時だからこそと、通常2日間の日程を4月4日の1日に縮小して祭りを実行し、氏子の方たちが御神体を乗せた台車を引き、避難所になっている鳳至小学校や公民館に立ち寄って、地元の人に御神酒(白酒)をふるまいました。
なお、この神座台車は、被災神社支援活動を行なっている羽咋市・深江八幡神社のM宮司よりお借りしたもので、コロナ禍で神輿渡御が中止になった時期、神輿に代わってM宮司が手づくりしたものを今回も使用しました、
m(。-_-。)m ↓おねがいします!