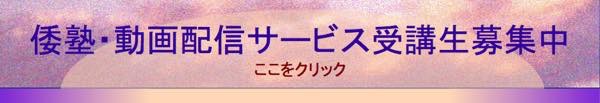嵐吹く 三室の山の もみぢ葉は
竜田の川の 錦なりけり
山の風に吹き散らされた三室山の紅葉は、ふもとを流れる竜田川を、まるで錦のように染め上げていますね。
*
この歌のキーワードは「三室の山」です。
別名を神南備山といい、神々が降臨する山とされました。
そして「室」というのは、氷室などのように外気を防ぐための室のことをいいます。
つまり「三室の山」は風雨を防いで神々が降臨する山という意味になります。
そこに「嵐吹く」ということは、神々の御在所が嵐になるわけで、これは国家の政乱を指すことになります。
この歌単独でも、そこまで読み解くことも可能ですが、「百人一首」は、読む人が歌の真意を理解しやすいように、配列にも気を遣っているのです。
*
つまり、神々が降臨する三室山は、そのまま朝廷であり、その朝廷に吹いている嵐は、まさに政乱を指しています。
けれども、「そうした政乱でさえも絢爛豪華な錦と同じように我が国の歴史を飾っている」と、この歌は詠んでいるのです。
*
「政争が錦のようだ」というのは、不思議に感じられるかもしれません。
けれど、三条院と藤原道長の争いは、当事者にとっては血みどろの戦いそのものかもしれませんが、目を海外に向けてみれば、中世における王室内の争いというのは、ヨーロッパにせよ中国にせよ、まさに本物の流血を伴う凄まじいものであったわけです。
政争に敗れれば、一族郎党は女子供まで容赦なく皆殺しにされるし、後宮内の女性同士の争いにしても、例えば清朝末期の西太后は皇帝の寵愛を得るために、ライバルの女性の両手両足を切断して肥桶に首だけ出して生かしておくなど、およそ人間のすることとは思えないほどの残酷な仕打ちをしています。
*
そうした諸外国の争いと比べると、我が国の政争が、いかに穏やかなものかが分かります。
ここまでくると、もはや政争でさえも優美といえるものです。
実際、六十八番の三条院は、政争に破れ「心にもあらで憂き世に長らへば恋しかるべき夜半の月かな」
と詠みました。
「憂き」と詠んでいながら、同時に「恋しかるべき夜半の月」と詠んでいます。
ある意味、とても優雅なものです。
大陸なら殺されています。

人気ブログランキングへ