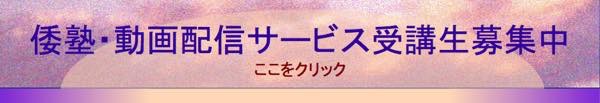寂しさに 宿を立ち出でて ながむれば
いづくも同じ 秋の夕暮れ
あまりにさみしいので、家から出てあたりを眺めてみたら、どこも同じ秋の夕暮れだったよ。
*
大勢の人がいる騒がしくて忙しい環境から離れ、自然の中でのんびりと一人で暮らす夢のような日々がようやくやって来ました。
ところが実際に独り暮らしをしてみると、どうにも寂しくてたまりません。
そして住まいとなっている草庵を出て、付近一帯を眺めてみると、あたりはもうすっかり秋の景色です。
そこで、「ああ、どこもかしこも、秋景色なんだなあ」と詠んだのがこの歌と、一般には解されています。
*
藤原定家は、この歌を三条院の「恋しかるべき夜半の月」、能因法師の「竜田の川の錦」の次に配しました。
三条院の歌は朝廷の政争を、能因法師の歌はその政争さえも我が国では錦だと詠んでいます。
ということは、次に配された 良暹法師の歌も、ただ寂しいとか孤独だとか言っているのではありません。
人に揉まれた比叡山も、人里離れた大原も、そして京の都も、「いずくも同じ」生命の息吹にあふれている、と言っています。
そして「夕暮れ」は「落日」です。
つまり日本全体が、落日の時を迎えているのです。
日本は「シラス」国です。
平安末期、そのシラスによる統治体制が音を立てて崩れていきました。
良暹法師はそのことを寂しいと詠んでいるのです。

人気ブログランキングへ