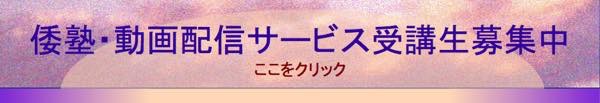雲居にまがふ 沖つ白波
舟に乗って大海原に漕ぎ出してみると、久しぶりのきれいな空のかなたに、雲と見間違えるばかりの、沖の白波が立っています。
***
「百人一首」の撰者、藤原定家は、恐ろしいほど壮大な歴史的背景を持つ七十五番歌のあとに、「保元の乱」の当事者である藤原忠通(法性寺入道前関白太政大臣)と崇徳上皇の歌を、続けて配列しています。
この七十六番歌は、崇徳天皇が上皇となった時のお祝いの席で、藤原忠通が心から悦びの気持ちを詠んだ歌です。
*
崇徳上皇の祝いの席ですから、新たな門出にふさわしい、晴れやかで広がりのある風景を詠っています。
ただ、気になるのは「白波」です。
海の波には、「うねり」と「白波」があります。
「うねり」は海水が自然に盛り上がったり、へこんだりする様子ですが、「白波」は、強風にあおられた波のてっぺんが、吹き飛ばされて白く泡立っている状態です。
舟で海に漕ぎ出したというくらいですから、その日は、風も海もおだやかで、天気の良い日だったのだろうと思います。
しかし、沖合は風が強く白波が立ち、航海するには危険な状況だということです。
つまり舟の進む未来に大きな不安があることを、この歌は暗示しています。
**
皮肉なことにこの歌は、詠んだ時の清々しい思いとは裏腹に、未来に起こる動乱(沖つ白波)を予言していたともいえるのです。
このように見ていくと、「日本の施政者には、神様が降りるのかも」などと思ってしまいます。
*
おそらく藤原定家は、藤原忠通に対して複雑な気持ちを抱えていたと思います。
*
批判したい気持ちと、かばいたい気持ちの両方があったのではないでしょうか。
だからこそ藤原忠通を軽んじた藤原基俊の歌の直後に、当の本人である藤原忠通の歌をーしかも生涯の数ある歌の中から、崇徳上皇と良好な関係にあった頃の清々しい歌を配しているのです。
まるで、崇徳上皇を祝う歌を載せることが、貴族社会に終焉をもたらした一族の長、藤原忠通の贖罪になるかのように。
『ねずさんの日本の心で読み解く百人一首』
~31文字に込められたもうひとつの思い~
http://goo.gl/WicWUi
~31文字に込められたもうひとつの思い~
http://goo.gl/WicWUi

人気ブログランキングへ