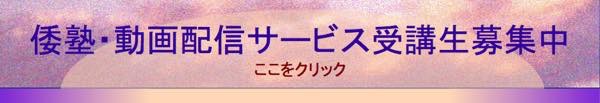世の中は 常にもがもな 渚漕ぐ
海人の小舟の 綱手かなしも
世の中は永遠に変わらないでほしいものです。
渚を漕ぐ漁師の小舟が、綱手で引かれる様子は、何とも切ないものだけれども。
***
鎌倉右大臣とは、鎌倉幕府の三代将軍 源実朝のことです。
鎌倉幕府の創始者である源頼朝の次男で、十二歳で征夷大将軍となり、武士として初めて右大臣に栄達しました。
***
武士として初めて右大臣の位に上がったことに敬意を表すとともに、朝廷と幕府との良好な関係を築いていける立派な人物であったことを、藤原定家は「鎌倉右大臣」という歌人名で示したのだと思います。
***
平安末期から鎌倉時代初期の歴史の流れについて、認識しておかなければならない大切なことがひとつあります。
それは、いわゆる悪意を持った悪者がいない、ということです。
誰もがそれぞれのポジションで誠実に働き、世の中を良くしよう、平和を維持しようとどりを続け、できる精一杯の努力を積み重ねていただけなのに、世の中が荒れてしまっています。
*
鎌倉幕府にしても、源頼朝はどこまでも天皇に忠実であれと、部下たちに何度も訓戒しています。
このあたり、他国における政権獲得者が野心によって天下人の位を射止めたのと、全く状況を異にしています。
***
実際は混乱の時代にあっても、誰もが真っ直ぐで誠実であったというのが、日本の歴史の大きな特徴です。
源実朝を暗殺した源公暁も、自分が将軍になりたいといえ野心で暗殺行為を働いたわけではありません。
それは彼が暗殺のときに、「親の敵はかく討つぞ」と叫んだ事実が証明しています。
要するに、誰もがそれぞれのポジションで「まこと」を尽くした結果、まるで「渚漕ぐ海人の小舟の網手」で舟が引っ張られるように、時代が移り変わっていったのです。
何度も書きましたが、こうして貴族社会から武家社会へと時代が移ったおかげで、「元寇」という国難から国を守ることができました。
ですから結果をみれば、時代の流れは私たち日本人にとって、最悪の時期に最良の方向へ流れていったといえると思います。
***
式子内親王を失った悲しみ、弟子の源実朝を失った悲しみ、国のカタチが崩れていく悲しみ、そんな絶望的な悲しみの中で、藤原定家は「百人一首」を編纂したのです。

人気ブログランキングへ