子どもの健康管理については、どんな親でも悩みどころですね。
予防接種、ワクチンについて、医学博士で元・国立公衆衛生院(現・国立保健医療科学院)免疫部感染症室長の母里啓子(もりひろこ)先生が詳しく解説した本を紹介します。
子どもと親のためのワクチン読本 知っておきたい予防接種/双葉社
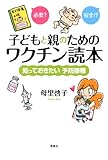
2013年10月発行
≪目次≫
予防接種のスケジュール表を見ると驚きますよね。あまりにたくさんのワクチン。これをきちんと打っていかなくちゃいけないの?と。
母里先生によると、必要なワクチンもあるし、ワクチン接種が必要な地域もある。けれど、できたワクチンを全部打たなければならないような風潮に乗る必要はない。
小児科ではどんどんすすめられている有料の任意接種も「このワクチンがすべて必要なのですか」と訊かれたら、「必要なものはわずかです」と答えるそうです。
予防接種は決して強制されてするものではなく、打つ、打たない、の決定権は親にある。
でも、だからこそ、悩むわけで。
ワクチンは体にとって不自然で、リスクを持つもの。
この前提がある上で、どれを選んだらいいのか。
頭で考えただけではわかりません。正しい情報が必要です。
予防接種について、どのように考えたらいいのか、
たくさんあるワクチンはどのようなものなのか。
ひとつひとつの疑問に答えてくれます。
目次では質問の他に回答のタイトルも掲載していますが、これだけで「あ、そうなのね」と納得せずに、気になるところはぜひ、本文にあたっていただきたいと思います。
--------------
ところで、風邪などで小児科に行ったところ、受診前に看護師さんなどから母子健康手帳の提出を求められ、予防接種についてあれこれ言われたりしたことはありませんか?
まるで成績不良のようにお説教されること、あるんです…(146p)
わたしは長男が1歳のころに母里先生の講演を拝聴し、予防接種は慎重にいこうと考え、決められた時期に受けることはしていませんでした。
で、小児科で看護師さんにぐいぐいと迫られたことがあります。
それ以来、受診の際には母子健康手帳は持参しませんでした。チェックされるのがいやだったからです。
そのことについては、特に何も言われたりしなかったのですが、その理由がこの本を読んでわかりました。
厚労省の予防接種実施要項にも「母子健康手帳の持参は必ずしも求めるものではないが、接種を受けた記録を本人が確認できるような措置を講じること」とあるのだそうです。
予防接種を受けるときにも必ずしも持参を求めるものではない、としたら、普通の受診であればなおさらのこと。
母子健康手帳を持参しなかったのは、悩んでいるところに追い打ちをかけるようなプレッシャーから逃れる自衛策だったのです。
目次で色をブルーにしたところは、高橋ユウさんのまんがの部分です。
母親たちの本音、葛藤がよ~くわかる。これは必見です。

特に賛同するのはこのひとこと。
最近はネットなどでもいろんなママの意見を知ることができますが─心が弱っている時の閲覧はホドホドに…
(で あなたは受ける派?受けない派?編39p)
子どもの健康を願うのはみんな同じ。その方法論は、いろいろとあるのでしょう。
予防接種について考えるとき、この本はぜひ読みたい一冊です。
必要なのは情報を得たうえで、どうするか判断すること。
人がやっているから、人から言われたから、という基準だけでは心もとないと思うのです。
最後に、母里先生のことばをふたつ。
いつもこころに留めておきたいものです。
病気への不安におびやかされて、今持っている心と体の健康をふいにしてしまわないでください。(あとがき159p)
人間の体は長い長い進化の過程を経て、ここまでできあがりました。自分自身の体を強くして、病と戦う力をつけておくことが一番大事なことなのです。(はじめに5p)
 【本のこと あれこれ】since 2004
【本のこと あれこれ】since 2004
 【きょうのパン 明日のパン】愛犬パンの毎日&犬の本や映画の紹介
【きょうのパン 明日のパン】愛犬パンの毎日&犬の本や映画の紹介
予防接種、ワクチンについて、医学博士で元・国立公衆衛生院(現・国立保健医療科学院)免疫部感染症室長の母里啓子(もりひろこ)先生が詳しく解説した本を紹介します。
子どもと親のためのワクチン読本 知っておきたい予防接種/双葉社
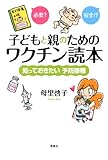
2013年10月発行
≪目次≫
|
予防接種のスケジュール表を見ると驚きますよね。あまりにたくさんのワクチン。これをきちんと打っていかなくちゃいけないの?と。
母里先生によると、必要なワクチンもあるし、ワクチン接種が必要な地域もある。けれど、できたワクチンを全部打たなければならないような風潮に乗る必要はない。
小児科ではどんどんすすめられている有料の任意接種も「このワクチンがすべて必要なのですか」と訊かれたら、「必要なものはわずかです」と答えるそうです。
予防接種は決して強制されてするものではなく、打つ、打たない、の決定権は親にある。
でも、だからこそ、悩むわけで。
ワクチンは体にとって不自然で、リスクを持つもの。
この前提がある上で、どれを選んだらいいのか。
頭で考えただけではわかりません。正しい情報が必要です。
予防接種について、どのように考えたらいいのか、
たくさんあるワクチンはどのようなものなのか。
ひとつひとつの疑問に答えてくれます。
目次では質問の他に回答のタイトルも掲載していますが、これだけで「あ、そうなのね」と納得せずに、気になるところはぜひ、本文にあたっていただきたいと思います。
--------------
ところで、風邪などで小児科に行ったところ、受診前に看護師さんなどから母子健康手帳の提出を求められ、予防接種についてあれこれ言われたりしたことはありませんか?
まるで成績不良のようにお説教されること、あるんです…(146p)
わたしは長男が1歳のころに母里先生の講演を拝聴し、予防接種は慎重にいこうと考え、決められた時期に受けることはしていませんでした。
で、小児科で看護師さんにぐいぐいと迫られたことがあります。
それ以来、受診の際には母子健康手帳は持参しませんでした。チェックされるのがいやだったからです。
そのことについては、特に何も言われたりしなかったのですが、その理由がこの本を読んでわかりました。
厚労省の予防接種実施要項にも「母子健康手帳の持参は必ずしも求めるものではないが、接種を受けた記録を本人が確認できるような措置を講じること」とあるのだそうです。
予防接種を受けるときにも必ずしも持参を求めるものではない、としたら、普通の受診であればなおさらのこと。
母子健康手帳を持参しなかったのは、悩んでいるところに追い打ちをかけるようなプレッシャーから逃れる自衛策だったのです。
目次で色をブルーにしたところは、高橋ユウさんのまんがの部分です。
母親たちの本音、葛藤がよ~くわかる。これは必見です。

特に賛同するのはこのひとこと。
最近はネットなどでもいろんなママの意見を知ることができますが─心が弱っている時の閲覧はホドホドに…
(で あなたは受ける派?受けない派?編39p)
子どもの健康を願うのはみんな同じ。その方法論は、いろいろとあるのでしょう。
予防接種について考えるとき、この本はぜひ読みたい一冊です。
必要なのは情報を得たうえで、どうするか判断すること。
人がやっているから、人から言われたから、という基準だけでは心もとないと思うのです。
最後に、母里先生のことばをふたつ。
いつもこころに留めておきたいものです。
病気への不安におびやかされて、今持っている心と体の健康をふいにしてしまわないでください。(あとがき159p)
人間の体は長い長い進化の過程を経て、ここまでできあがりました。自分自身の体を強くして、病と戦う力をつけておくことが一番大事なことなのです。(はじめに5p)
 【本のこと あれこれ】since 2004
【本のこと あれこれ】since 2004  【きょうのパン 明日のパン】愛犬パンの毎日&犬の本や映画の紹介
【きょうのパン 明日のパン】愛犬パンの毎日&犬の本や映画の紹介