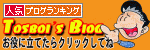いくつかの地域・商業地区を、一定のセグメントに基づいて徹底的に視察し続けると、
その地域の特性や、消費傾向、あるいは成熟度などを肌で感じられ始めます。
価値観が多様化し、且つ、人口が減っていて、且つ、デフレ傾向にある時代のビジネスというのは、
ある分野において、専門性を高め、顧客との関係性を徹底的に高め、一定数と長くお付き合い
していく方向性と、
低価格で、売れ筋商品を無節操に揃え続けて、地域の人数シェアを高める方向性の
二極化が進むことが考えられます。
物販(全ての商品・サービスと言ってしまってもいいか?)においては、
前者は一般に、得意分野を持つ少人数性が前提となり、営業コストはかかり、高価格帯中心の
品揃えになります。
後者は一般に、誰でもできるシステム化による多人数が前提となり、低価格帯の品揃えとなるでしょう。
前者は、嗜好する客数そのものが少ないことや、利益の源泉が人にあるがゆえの継続性が
悩みと考えられますが、
では、後者が客数が伸び続けるかと言えば、そうとも言えません。
誰でもできるようになるということは、文字通り誰でもできてしまうので、似たような店舗がいくつもできて、
競争が激しくなり、顧客からは見分けがつかなくなって、結局、支持人口は分散され、さらに低価格へと
向かわざる負えないアリジゴクへと進むリスクをはらんでいます。
(ちなみに商圏人口と支持人口は違います。ここでは書きませんが・・・・・。)
人口数が減っているのだから、結局、どのみち客数の増加には悩むのです。
どちらに転んでも、ビジネスを継続していく以上、「顧客の創造」に対する悩みは途絶えることは
ないのだと思います。
どちらの方向性にも、「強み」と「弱み」は隣り合わせである以上、最後は、どちらが好きなのかに
委ねられるのだと思います。
結局は、自分はどちらが好きで、どちらが人生経験上得意にしているかで、ビジネスの枠組みは
変わってくるのでしょう。
どちらが「正しい」「間違っている」という問題ではなく、どちらが「好き」」嫌い」、どちらが「得意」「苦手」、
どちらを「やりたい」「やりたくない」という問題なのだと思います。
最後は、「自分を知る」ということになるのでしょうね。
何をもってして「人生の豊かさ」と自分が定義するか・・・・・・・・、
そんなことを改めて考え、自分を改めて知る経験と時間でした。
最後は本人の「好き」「嫌い」。
応援クリックお願いします~。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓