昨日のバーゲンセールについての記事について、
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
http://ameblo.jp/tosboistudio/entry-11888105473.html
Facebookのコメントから、下記のような質問がありました。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
ところで、マジレスなんですが、セールは「買いたい・買いたくない」
の動機創りにはならないんですか?そこら辺の違いがしっくり理解できない(´・ω・`)
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
実は、そこら辺を書くかどうか、長くなるし、ややこしいので迷ったんです
けどね(苦笑)。
下記、私見です。
まず一つ目に、確かに、「セール」時期や「セール」情報を受けて、
「なんかねぇかなぁ」と街に出たり、いつもは行かない店や百貨店に行って
みるということはあると思うんですね。
私も、セール時期だから行く場所というのはあります。
そして、そこで新たに気付く店や商品と出会って、思いがけず見つけて買っ
てしまう、ということはあって、そういう意味では「セール」というのは、
発信手にとって、新たに自社のことや商品の魅力を知ってもらえる機会に
なる可能性はありますね。
でも、例えば、セールをやっている商店街に出たとして、ブラブラ歩きながら、
漠然と(なんかねぇかなぁ。)と思ってたとしても、私は、婦人服の専門店
には入らないし、ゴルフ専門店には入らないワケですね。
百貨店に行っても、レディースフロアには足は向かないし、寝具の店にも入
りません。
やっぱり、自分に有益だと感じる何かを五感情報で嗅ぎつけて、そこに入る。
前提として「欲しい」あるいは「ここには欲しいものがあるかもしれない。」
と期待させるだけの事前情報が、自分の脳にインプットされていないと、
足を向けるという実際の行動には行きつかないワケです。
私がセール時期に「街・人・店」という大枠で、流行りの感覚値を掴んで
おきたいといっても、それは消費者という前提がある以上、メンズ衣料で
あったり、そもそも興味のある対象が前提になっていますから。
二つ目に、前記したように、「セール」がきっかけとなって消費者に新たな
気づきや発見を促す、あるいは、新たな出会いの機会を創ったり、店舗や
サービスを体験してもらおう、と意図したとしますよね。
それはそれでアリだとは思うのですが、でも、だとしたら、百貨店のあの
いかにも「セールでごさいます」的な、セール用の什器配列や売場創りや
情報発信の仕方では苦しいでしょうね。
ブランド名と、通常価格と、○○%OFFと書かれた情報だけでは、無知
な私には、そもそも何がどういい商品で、買った後の生活のメリットがどう
あるのかサッパリ分からないから、気付くとか発見のしようがないんですね。
「セール」で「何か」がきっと安くなっていることだけは分かっても、
そもそもその「何か」が何なのかが分からない(苦笑)。
以前のように、「良いモノは百貨店」という時代なら、百貨店にあるモノは
何から何まで「良いモノだ」という前提がインプットされていたのでしょうが、
今はそうではありません。
先日、ユニクロの店頭のマネキンディスプレイが目に入ったんですね。
白のブラウスとギンガムチェックのタイトパンツのシンプルなコーデだった
んだけど、そっくりそのまま有名ブランドのウィンドウディスプレイになった
としたら、オレ違いが分かるかなぁ、と思えるほど見た目にはカッコ良かった。
違いが分からないのです。
どうして「セール」もやっていないユニクロの方が安くて、「セール」をやって
いるに関わらず、百貨店ブランドの方がユニクロよりも高いのかが分からない(苦笑)。
きっと、何らかの違いはあると思うし、あるはずなんだと信じています。
でも、違いが分かるのは、「セール」じゃない時に違いを認識している顧客
やファンだけでしょう。
そうなると、「セール」でその売場や店舗、商品を知った人に対して、何が
他との違いで、何か魅力なのか教えてくれないと、価格の情報だけでは買う
に至らないでしょ、というのが私の見解です。
そうなると、そもそものターゲットに向けてのみ「セール」情報を発信すれ
ばいい、となって百貨店としての発信はどんな意味があるのか?が今ひとつ
分からなくなる、という感じになるんでしょうかね。
昔は百貨店というのは、「いいモノが「百貨」もある」、というのがウリ
だったのが、今では「「百貨」しか揃っていないのか」という時代背景なの
だと思うのです。
百貨店に限らず、少々の大型店だからといって、売れなくなってきている
対策を、商品と価格の話しかできていない会社は抜本的に苦しいでしょうね。
そうやって考えると、自分が百貨店の責任者だったら、どうするかなぁ?と
考えては、考えつかなかったりして、まぁ他人事だからいいや、手遅れだし(笑)、
みたいな結論にいつもなるんですね(苦笑)。
ご質問頂いた方の答えになってるかどうか分かりませんが、今のところ、私な
結論として、人の消費の順序というのは、まず「欲しい・欲しくない」という
「情動」が先にあって、次に「買える・買えない」という「理性」に対する
問題解決という、この順序は基本として変わらないという考えです。
まぁ、今後、どう変わるかは責任持てませんがね(苦笑)。
私見ですから、私見(笑)。
ご参考頂ければ幸いです。
消費を人の心理から考えてみよう。
応援クリックお願いします~。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
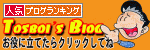
iPhoneからの投稿
