昨日鑑定理論アクセスβ一回目の優秀答案と僕の答案を見比べてみました(°_°
問題が小問3まであるのですが、、、小問2まではほぼ点数が同じ!!小問3で8点差つけられてました(°_°)
見直してみると凄~くわかりやすい差があった…
小問3で中心となる論点の描いてる量が圧倒的に少ない。。
いや!書こうと思ったらかけたんやで!!
ただ派生論点書いてたら書くスペース無くなってしまっただけなんや!!
(……それ答案構成で失敗してるだけやん!)…くそぅ
ここで、僕なりの論文試験(鑑定理論)の点数の取り方をまとめてみました。
まず前提として大きな派閥に分かれるであろうケインズ派か古典派・・・では無く。T先生派かW先生派か・・・でも無く
関連論点ひたすら書いて点を取る派か
要点をしっかり書いて点を取る派です
ちなみに僕はどちらかというと
ブログを見て頂ければわかるのですが、文章力が皆無なので関連論点ひたすら書いて点数取る派です。
それに比べて今回の優秀答案は文字数すっごい少ない!!論点しっかり書く派ですね
文字数で言う僕は一行55~60文字程度、優秀答案は一行45~50文字程度!!
これ論文試験受けてる人ならわかると思いますが。この10文字の差ってめちゃくちゃ大きい!!
僕は優秀答案の真似は出来ない!!
というわけで今回のブログは
「タイゾーよりは文章力あるけど答案構成あんま得意じゃないから関連論点たくさん書くなー」って人向けに鑑定理論の点数の取り方について僕の意見を書いてみます
①関連論点は書いても1点とかなので、出来る限り分量少なくする。
例えば「価格を求める鑑定評価の手法」の前文を長ーく書くと
「価格を求める鑑定評価の手法は価格の3面性、鑑定評価方式の三方式を前提とした原価法、取引事例比較法、収益還元法の三手法の他、これらの考え方を活用した開発法等がある。」と書けます。
でもでもここはこんなに書いても基本は1点しかもらえない!!それならば
「価格を求める鑑定評価の手法は原価法、取引事例比較法、収益還元法等がある。」
まで短縮しても同じ1点だと思います。
②中心の論点は書けるだけ書く
当たり前ですけどここは配点が5点とか6点つくとこなので知ってる事全部吐き出しましょう。(前回失敗したやつが何を言ってんだか笑)
③答案構成は一問5分~7分
関連論点をたくさん書いて点数とりたい人にとって書く分量って凄い重要なんですよね
僕は毎回一行55~60文字、改行少なめ、たまにわざと吹き出し使って分量増やしてる
みたいな感じですが、ここまでの分量書くと答案構成に7分位掛けてしまうと最後まで書ききれないんですよね。だから僕は基本5分にしてます(あくまで参考に
こんな感じですかねー
って僕もまだまだ出来ない事が多いですが、あと理論のテスト7回くらいかな?一回は優秀答案のれるようにがんばります^^ではでは
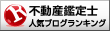
不動産鑑定士(試験・資格) ブログランキングへ
問題が小問3まであるのですが、、、小問2まではほぼ点数が同じ!!小問3で8点差つけられてました(°_°)
見直してみると凄~くわかりやすい差があった…
小問3で中心となる論点の描いてる量が圧倒的に少ない。。
いや!書こうと思ったらかけたんやで!!
ただ派生論点書いてたら書くスペース無くなってしまっただけなんや!!
(……それ答案構成で失敗してるだけやん!)…くそぅ
ここで、僕なりの論文試験(鑑定理論)の点数の取り方をまとめてみました。
まず前提として大きな派閥に分かれるであろうケインズ派か古典派・・・では無く。T先生派かW先生派か・・・でも無く
関連論点ひたすら書いて点を取る派か
要点をしっかり書いて点を取る派です
ちなみに僕はどちらかというと
ブログを見て頂ければわかるのですが、文章力が皆無なので関連論点ひたすら書いて点数取る派です。
それに比べて今回の優秀答案は文字数すっごい少ない!!論点しっかり書く派ですね
文字数で言う僕は一行55~60文字程度、優秀答案は一行45~50文字程度!!
これ論文試験受けてる人ならわかると思いますが。この10文字の差ってめちゃくちゃ大きい!!
僕は優秀答案の真似は出来ない!!
というわけで今回のブログは
「タイゾーよりは文章力あるけど答案構成あんま得意じゃないから関連論点たくさん書くなー」って人向けに鑑定理論の点数の取り方について僕の意見を書いてみます
①関連論点は書いても1点とかなので、出来る限り分量少なくする。
例えば「価格を求める鑑定評価の手法」の前文を長ーく書くと
「価格を求める鑑定評価の手法は価格の3面性、鑑定評価方式の三方式を前提とした原価法、取引事例比較法、収益還元法の三手法の他、これらの考え方を活用した開発法等がある。」と書けます。
でもでもここはこんなに書いても基本は1点しかもらえない!!それならば
「価格を求める鑑定評価の手法は原価法、取引事例比較法、収益還元法等がある。」
まで短縮しても同じ1点だと思います。
②中心の論点は書けるだけ書く
当たり前ですけどここは配点が5点とか6点つくとこなので知ってる事全部吐き出しましょう。(前回失敗したやつが何を言ってんだか笑)
③答案構成は一問5分~7分
関連論点をたくさん書いて点数とりたい人にとって書く分量って凄い重要なんですよね
僕は毎回一行55~60文字、改行少なめ、たまにわざと吹き出し使って分量増やしてる
みたいな感じですが、ここまでの分量書くと答案構成に7分位掛けてしまうと最後まで書ききれないんですよね。だから僕は基本5分にしてます(あくまで参考に
こんな感じですかねー
って僕もまだまだ出来ない事が多いですが、あと理論のテスト7回くらいかな?一回は優秀答案のれるようにがんばります^^ではでは
不動産鑑定士(試験・資格) ブログランキングへ