- 家守綺譚 (新潮文庫)/梨木 香歩
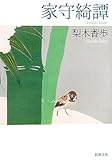
- ¥380
- Amazon.co.jp
梨木香歩の『家守綺譚』
「家守綺譚」のストーリーって
かんたんに図式化できそうな気がするんだけど、
それでも読んでいくうちにその図式がねじれていく
そんな小説になっている。
いい小説とはおそらくは、そういうものだと思う。
ぼくにとっての「家守綺譚」は、
親友の家を守ること、
書くということ、
そして雅/俗の対立
がポイントになっている。
で、ここで乱暴に家を自我と仮定してみる。
自我なんてもはや死語で、捨て去られた言葉だけれど、
自分にとってわかりやすくするためにそう仮定してみる。
自我というのを「意味と非意味をわける線」とだけ考えて
もらってもいい。
家と自我の関わり合いは大きい。
「浮雲」の文三は二階の部屋でいびつな自我を発酵するし、
コルタサルの「占拠される屋敷」では、得体の知れないものに
自我が侵食される恐怖が<屋敷>に仮託されて語られている。
家守とは、自我を守るメタファーであるともいえる。
でも、「家守綺譚」においては、<家>は主人公の家ではない。
主人公の親友高堂の家。つまり、<他者>の自我だ。
ここがこの小説の<仕掛け>だと思う。
(よその自我にはいりこむスリリングな小説に、
カーヴァーの「隣人」がある)
親友の家=他者の自我を守るということ。
それは、主人公の綿貫にとって、
彼自らの意味回路を切り拓く契機になるともいえる。
<他者>の自我を守るということは、
自らの自我を宙吊りにすることを意味している。
自らの自我を保留にすることによって、
今まで訪れることのなかったような新たな他者が
綿貫のもとを訪れることとなる。
それが俗の領域に住まう隣のおかみさんや
聖でいながら同時に俗でもある坊さんなどだ。
新たな他者が訪れることで、
綿貫はみずからのかたくなな自我をみつめなおし、
他者を思いやるという経験を何度となく遂行させられる。
綿貫は雅にこいこがれ、雅=高堂をひきよせながらも、
俗の領域が自らの精神を育み、養っていくことを学んでいく。
高堂の家に舞い込む新たな他者が
新たな意味へと綿貫をひきずりこんでいくことを
彼自身最終的に自覚したのだとぼくは思っている。
それは簡単にいえば、
<他者>に住まう、ということの寛容でもある。
<書く>という行為は<他者>を背負い込むことと関わり合いが深い。
それは<他者>に住まうのだ、といういいかたも出来るのかもしれない。
<書かれるもの>というのはつねに他者によって、
すでに書かれたものでもあり、
またこれから書かれるであろうものだからだ。
なにより<書かれたもの>は再度他者によって<書かれる>必要がある。
そうでなければ<書かれ>たことにはならない。
書くということは他者に住まうことに通じており、
日記を書いているわたしは、
いつも他者の家守をしているのかも知れない。