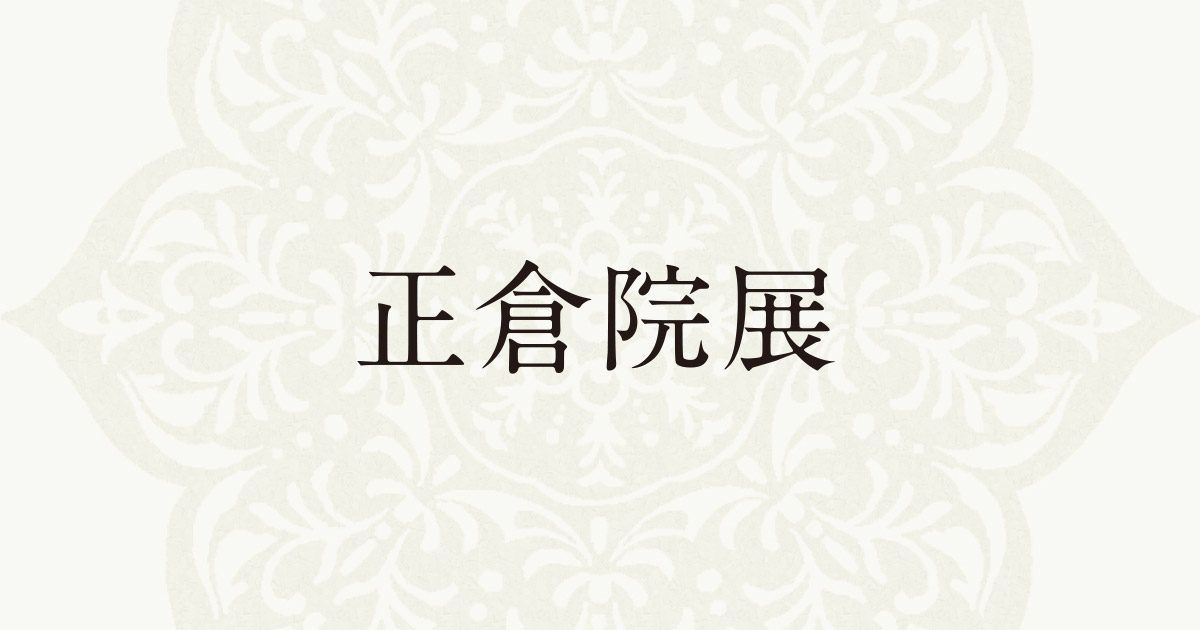奈良博前の池には、「もののけ姫」あたりに出てきそうなシルエットの鹿
カメラの明るさを調整したら、姿を現しました
暗闇に浮かび上がる鹿よ、
おうちに帰りましょう!
こちらも暗闇に浮かび上がる
「正倉院展」の文字↓
厳かです
今年の展示はやや地味めでしたが、
展示スペースに余裕があり、
パネル展示も充実していて
私の周りでは概ね好評でした
ではここからは、「図録」を参考に
面白いと私が思った展示をご紹介します
↓「図録」
鉄三鈷(てつのさんこ)
いきなりシブいところから失礼します
↓鉄三鈷は密教法具で、先が三又に分かれているので「三鈷杵(さんこしょ)」です

真言密教の三鈷杵とは違い、平面的で、まるでバイキンマンの持つモリのような形状の正倉院の鉄三鈷ですが、次の2点が面白いと思いました
まず一点目
↓この鉄三鈷は「素木三鈷箱(しらきさんこのはこ)」に納まるという点
つまり、鉄三鈷はケース付きだったということ
正倉院宝物は、聖武天皇遺愛の物だけあって、収納箱や袋が遺されていることは珍しくありません
鉄三鈷も同様に、独特な形にピッタリの見事な箱が遺されていて感動しました(なんなら三鈷杵そのものより、箱の方に感動した)
箱に収めると…ホントにピッタリ!
奈良時代、8世紀の技術レベルには毎度感服します
木はサクラの一枚板で、サクラ材は固くて虫にも強いため完璧な形で遺っているということでしょう
感動した二つめの点は
↓箱が金銀絵長花形几にピッタリ置ける点(←今回は展示されていません)
図録には、鉄三鈷を納める素木三鈷箱が花形几の上にピッタリ置くことができることが明らかになったと書いてありました
つまり、
鉄三鈷は、素木三鈷箱に入れられて、この金銀絵長花形几の上に置かれていた可能性が考えられるということです
いわば「鉄三鈷、3点セット」(セット内容、鉄三鈷・箱・机)という感じ
そして、これが東寺の密教法具のような「組法具」の祖形となった可能性も考えられるそうです
白石鎮子(はくせきのちんす)
大理石のレリーフである白石鎮子は、「虎・卯」と「辰・巳」の2点が展示されていました(全部で8点のうち)
虎・卯
大きさは、縦21.5㎝、横33.3㎝、厚さ4.7㎝、重さ8854g
一見ごちゃごちゃしてよくわからないのですが、
よーく見ると、虎とうさぎがいます
↓緑の線が虎、黄色い線がうさぎ
(私が指でなぞったのでわけわかめです…奈良博で確認してください)
辰・巳
縦21.4㎝、横32.8㎝、厚4.8㎝、重さ9441g
こちら、もっとごちゃごちゃしていて、とても分かりづらい
↓下の図で、とりあえずヘビ(赤)と辰(青)を指でなぞりましたが…なんじゃこれ?![]()
ヘビは向かって左側で右を向いてグニョグニョ体を伸ばしている
辰は、なぞっているうちにナゾが深まった…
が、真ん中あたりで体を捻じ曲げてヘビと対峙しているようです…よくわからん)
現物の石は重厚感があり、これを木彫で再現してみたいと思いました
漆背金銀平脱八角鏡(黒漆地に金銀飾りの鏡)
8世紀、唐製の華やかな八花形の鏡
ですが、表面には鳳凰や花喰鳥、飛鳥、蝶などが軽やかに飛んでいます
正倉院宝物の鳥って、可愛いよね
鸚鵡﨟纈屏風・象木﨟纈屏風(ろうけつ染めの屏風)
ろうけつ染めの屏風は全部で十畳あるそうで、今回はこの2点が出展されていました↓
鸚鵡の屏風と象の屏風
この2つの展示のなかでも、
鸚鵡の屏風で、鸚鵡の下にいる小さい鹿が可愛かった(さすが奈良)
↑下の方に、振り返る小さな鹿
銀壺(大型の銀製の壺)
高さが46.6㎝もあります
私は以前、この壺で「魚々子(ななこ)」ということばを知った気がします
全体に暗い色合いですが、よくみるとたくさん模様が描かれています
↓こちらは馬に乗り弓を持った人と、鹿?
絵を取り囲む地の部分に「魚々子」と呼ばれる細かい点々が打たれています
この魚々子があるために、絵が浮かび上がってはっきり見えます
(余談ですが、私は「魚々子」模様とは、この壺のような細かい点々の模様だと思っていました
しかし、京都にある法金剛院阿弥陀如来坐像の台座に施された「魚々子」模様を観た時、あまりにも違う様子に驚いたことがあります
法金剛院像の台座の模様も魚々子模様ですが、粗い点々模様なのです
ちなみに、法金剛院像の意匠の「繊細さ」は平安後期の典型とされています
しかし、この魚々子模様を繊細と言っていいのか、戸惑う感覚が拭えないのです
参考 法金剛院阿弥陀如来坐像
(文化庁公式ツイートからお借りしました)
この阿弥陀如来坐像の台座の、
↓黄色で囲んだ部分にぐるりと魚々子模様がある
写真ではよく見えないですが、
法金剛院阿弥陀如来坐像は素晴らしい仏像なので、機会があったら是非現地でご確認ください
鳥獣花背円鏡(霊獣と葡萄模様の鏡)
(写真が少し歪んでしまいましたが)
7世紀、唐製の海獣葡萄鏡です
現地では暗くてよく見えなかったのですが(近視で老眼が入ると、どう工夫しても見えないことがある…)
図録でみると、
↓鳥と葡萄が細やかに鋳出されているのがわかりました
とても繊細な模様
そしてここでも、鳥が可愛い
金銀平脱皮箱(金銀飾りの皮箱)
↓箱の模様のうち、鈍色に見える部分は当初は銀色だったそうで、
元々は金と銀の鮮やかな箱だったようです
金の花枝を二羽の銀の鴛鴦(おしどり)が加える模様が配され、中央には鳳凰
これも、鳥のモチーフでした
今年は鳥関連の展示が多いのかしら?それとも、私が鳥ばかり選んでしまうのかしら?
紫檀木画箱(象嵌細工の箱)
奈良時代日本製、または8世紀唐製といわれるこの箱は、蓋の部分のみが当初のものだそうです(当初の蓋と後補の本体の区別がつかないほど後補の技術もすごい)
正倉院の宝物は、時々持ち帰りたくなるほど(ドロボーですよ)素敵なものがありますが、
今回、私はこの箱を持ち帰りたくなりました
蓋の部分を拡大してみると、かわいい
やっぱり、鳥の模様でした![]()
この画面の範囲だけでも、異なる種類の小鳥が3羽飛んでいます
可愛いです
それから、枝もハート型が連なり、おしゃれで可愛い
こんな箱を自分が持っていたら、
何を入れようかしら?(盗む気満々)
彩絵水鳥形(鳥形の飾り具)
実際の展示では何だかわからないくらい小さいものです
目をこすってよーく見ると、バッジのような鳥
(また、鳥!)
同じくらいの大きさのバッジが、実際に奈良博の売店にありました
帽子やカバンに着けたくなります
イヤリングやピアスにしてもいいかもしれません
この鳥、実はヒノキでできているというから驚きです
犀角魚形(腰飾り)
こちらもとても小さな飾りです
今すぐ使えそうな金具までついているのがすごい
これ、腰につるして身につけたそうです
オシャレです
唐では高い身分を示すために使われたそうですよ(なぜ魚?)
大歌緑綾袍(綾の上着)
大仏開眼会で使われたと考えられるそうなんですが、私がおどろいたのはその「幅の大きさ」です
幅が218.0㎝と図録に書いてあります
とてもとても大きいのです
昔の人は小柄だったでしょうに、こんなに幅の広い着物は大きすぎる!
ひょっとして、二人羽織?(いや違うだろう)
それに、首回りは小さすぎない?
身ごろはぶかぶか
首は締まる
機能的ではなさそうです
造寺司牒三綱務所諸国封戸事(造東大寺司から東大寺三綱所へ宛てた文書)天平勝宝4年(752)
展示の最後の文書類は、ササっと見ることが多いと思います
今回は夜ごはんの予約時間も気になって、なおさらササっと見ることになりました
↓下の展示文書の内容は、造東大寺司が管理していた封戸五千戸のうち千戸について東大寺三綱所が管理することになったことを示すそうです
改変を防ぐために押された「造東大寺司」のハンコが丸い印で可愛いです
↓串に刺さったダンゴ![]() のような造東大寺印
のような造東大寺印
…と思ったらこのハンコには「造東寺印」と書いてない?
これ、「造東大寺司」じゃなくて、「造東寺司」の管轄の間違いなんじゃない?
…と思って図録を確認したら、
「造東寺印」と書いて、造東大寺司の管轄で良いようです(マニアックですいません)↓
…ということで、今年の正倉院展について、
私的に面白かった点についてザックリ書いてみました
詳しい内容については、下にHPのリンクを貼りましたので、参考にしてください




ところで、
今回泊まった宿が、とても素晴らしかったのでご紹介します
毎年、一棟貸しの宿を友人が選んでくれるのですが、今年は↓ここ
肖舎
二階建ての長屋を改装した宿です
キッチンもバスまわりもなんでも揃っていて、住めます!
このお宿、近鉄奈良駅すぐそばの、絶対に誰も気づかないような袋小路の中にあります
長屋を宿屋・食べ物屋等に改装したもののようです
素泊まりでした
食事は、2晩とも東向商店街でとりました
一晩目
私が好きな
ベトナム料理コムゴン
とりあえず、奈良での再会を祝して
かんぱーい🍻
みんな腹ペコで、もりもり食べた
美味しかった
いや、これ、食べすぎでしょ

ご馳走様でした😊
↓お店の外と中にあった人形
え??
ちょっと待って!
コムゴンの人形って、
高月観音まつりで会った仏像(ひとつ前の記事参照)に似てないか?
あらやだ、冗談ですよ💦
とても似てる気がするけど、きっと気のせいだ
2日目の夜は
ここは、大和牛や飛鳥鍋が売りもののようです
私たちは、2つのビールの名前
あをによし、そらみつ
にすっかり魅せられ
味見のためにちょっとずつ分けて
今宵もまた、かんぱーい🍻
軽くて美味しいビールでした
この日の昼は栄山寺、夜は奈良博で正倉院展を観た後だったので、また、バクバク食べる…
いやだから、食べすぎでしょ(それに私は人間ドック前よ😱)
何はともあれ、
今年も古い仲間と元気に奈良を満喫できたことに
感謝\(^o^)/