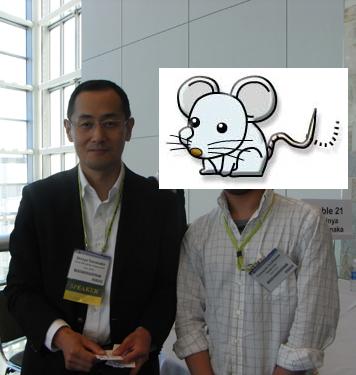再生医療が描く未来 -iPS細胞とES細胞-
京都の大学院生改め一研究員改め一大学教員が贈る、夢の未来への軌跡。 人工多能性幹細胞(iPS細胞)や胚性幹細胞(ES細胞)などの万能細胞、クローン、生殖補助医療技術 についてのトピック紹介・論文解説。
カレンダー
テーマ
ブログ内検索
ブックマーク
最新の記事
最近のコメント
月別
プロフィール
このブログのフォロワー
うぇるかむ!
今話題になっている、人工多能性幹細胞(iPS細胞)や胚性幹細胞(ES細胞)などの万能細胞、クローン、生殖補助医療技術などの話をしていきたいと思います。
このブログの趣旨は、今この分野でとてつもないスピードで進展している研究について説明し、専門分野以外の方々にも興味を持っていただくことです。よって質問は大歓迎です!
ここさえ見ていれば再生医療のトピックスが分かるようなデータベースになることを目指しています。
一つ一つ説明するととてつもない時間がかかりますので専門用語が多いのには多少目をつぶって下さいm(__)m
代わりに質問で対応できればと思っております。
今話題になっている、人工多能性幹細胞(iPS細胞)や胚性幹細胞(ES細胞)などの万能細胞、クローン、生殖補助医療技術などの話をしていきたいと思います。
このブログの趣旨は、今この分野でとてつもないスピードで進展している研究について説明し、専門分野以外の方々にも興味を持っていただくことです。よって質問は大歓迎です!
ここさえ見ていれば再生医療のトピックスが分かるようなデータベースになることを目指しています。
一つ一つ説明するととてつもない時間がかかりますので専門用語が多いのには多少目をつぶって下さいm(__)m
代わりに質問で対応できればと思っております。
2016-10-18 00:00:10
詳細記事目次
テーマ:ブログはじめに
専門用語解説 専門用語の質問の受付 専門用語集および用語質問受付
ウィキベディア 胚性幹細胞(ES細胞)、人工多能性幹細胞(iPS細胞)のウィキペディア記事へのリンク
幹細胞って何? 幹細胞・TA細胞(前駆細胞)・分化細胞の定義
多能性 分化能の一つである多能性の説明
再生医療に関する3つの誤解 臓器置換から細胞移植への移行、幹細胞とガン化、幹細胞とクローン
将来の再生医療-遺伝子治療との融合- 遺伝病の根治に向けた将来の治療法についての戦略
テロメアについて iPS細胞とクローンにおけるテロメア長
mixiとの連動 このブログとの連動コミュニティー
胚性幹細胞とクローン技術
ES細胞って何? ES細胞の定義・能力
ES細胞ができるまで ES細胞樹立に至るまでの歴史、テラトカルシノーマ、EC細胞、EG細胞
ES細胞樹立時における倫理的問題の回避法 受精卵を破壊しないES細胞の樹立法について
拒絶反応回避とクローン技術 セラピューティッククローニングと呼ばれる技術の歴史、捏造事件
ヒトクローンにおける倫理的問題の回避法 ヒトクローン作出の回避とレシピエント卵の確保について
エピブラストステムセルとヒトES細胞 マウスES細胞とヒトES細胞の違い、EpiSCs、FAB-SCs、rESCs
エピブラストステムセルとヒトES細胞(その2)
ES細胞中のサブポピュレーション ICM様(原始外胚葉様)ES細胞とエピブラスト様ES細胞
ES細胞における自己複製の基底状態 Mek/Erk, GSK3, FGF経路阻害による未分化性維持とラットES細胞
ES細胞からの生殖細胞分化誘導 体外でES細胞から卵および精子を作出する試み
ES細胞とiPS細胞の違い iPS細胞が生まれた経緯、ES細胞研究のメリット・必要性
人工多能性幹細胞
iPS細胞って何? 京都大学 山中伸弥先生によるiPS細胞の第1報 すべてはこの1報から始まった
第二世代マウスiPS細胞 ほぼES細胞と同等の能力を持つiPS細胞の作製について
コロニーの形態によるiPS細胞の選抜法 薬剤選抜なしでの樹立、全身がiPS細胞に由来するマウスの作製
ヒトiPS細胞の樹立 ヒトiPS細胞樹立に関する第1報から第4報、および第6報についての詳細
ガン遺伝子c-MycなしでのiPS細胞の樹立 iPS細胞のc-Myc再発現によるガン化の回避、L-Mycでの代用
肝臓および胃の細胞からのiPS細胞の樹立 レトロウイルス挿入を減らしてガン化リスクを低減
iPS細胞樹立に必要な導入遺伝子発現時間の解析 薬剤誘導系による導入遺伝子発現の必要時間の解析
独バイエル社ヒトiPS細胞論文詳細 特許問題で話題になったヒトiPS細胞樹立に関する論文
Bリンパ球・すい臓β細胞からのiPS細胞樹立 終末分化細胞からもiPS細胞が樹立可能なことの証明
統合ゲノム解析を通したiPS細胞樹立メカニズムの解析 樹立メカニズム解析とDnmt・転写因子阻害効果
ヒトiPS細胞樹立効率の改善とNILベクター使用の試み ヒトiPS細胞第7報の詳細
化学的・遺伝学的手法を組み合わせたiPS細胞の樹立 化合物による代用、G9a・MEK・PRMTの阻害、PS48
小分子化合物によるiPS細胞樹立効率の改善 Dnmt阻害、HDAC阻害(VPA、酪酸)、8-Br-cAMP
神経幹細胞からのiPS細胞樹立 神経幹細胞・神経前駆細胞からの少数の遺伝子によるiPS細胞樹立
複数の細胞種からの遺伝的に均一なiPS細胞の樹立 薬剤誘導系による複数の細胞種からのiPS細胞樹立
Wntシグナリングの刺激によるiPS細胞樹立効率の改善 Wnt経路の刺激による樹立効率改善
難病患者からのiPS細胞樹立 将来の再生医療およびiPS細胞の病因解明・創薬への応用への第一歩
薬剤誘導系によるヒトiPS細胞の樹立 ヒトiPS細胞の樹立に必要な導入遺伝子の発現時間を解析
アデノウイルスを用いたiPS細胞の作製 一時的な遺伝子発現誘導によるiPS細胞作製の第1報
ウイルスを使わないでiPS細胞を樹立 プラスミド、エピソーマル(EB)、minicircleベクターによる一時的な遺伝子発現誘導でiPS細胞作製
髪の毛一本からのヒトiPS細胞樹立 ケラチノサイトからの急速で効率的なヒトiPS細胞樹立
シグナル阻害によるiPS細胞樹立法の改善 Mek/Erk経路およびGSK3の阻害剤を用いたiPS細胞の樹立法
山中ファクター以外の遺伝子を用いたiPS細胞樹立 p53 siRNAとUTF1、Esrrb、ESCC miRNA、Sall4、Nr5a2、Tbx3、Rem2、TCL-1A、YAP
山中ファクター以外の遺伝子を用いたiPS細胞樹立(その2) E-Cadherin、Prmt5、miR-93、miR-106b
マウス・ヒト以外の種でのiPS細胞樹立 山中ファクターを用いた他種でのダイレクトリプログラミング
マウス以外の種におけるマウスES細胞様ES/iPS細胞の樹立 マウス以外の種でのノックアウト動物作製への応用、MEK/ERK, GSK3, AKL5阻害、p38阻害、Forskolin
マウス以外の種におけるマウスES細胞様ES/iPS細胞の樹立(その2) 低酸素培養、NANOG強制発現
単一ベクターによるiPS細胞樹立 ポリシストロニック発現ベクター、Cre/loxPシステムの応用、phage integrase
特定の組み合わせの薬剤誘導リプログラミング因子を持つマウス 代替因子探索ツールの作製
多能性誘導におけるリプログラミング因子の役割 iPS細胞誘導におけるOct4, Sox2, Klf4, c-Mycの機能
多能性誘導におけるリプログラミング因子の役割(その2)
iPS細胞からの生殖細胞分化誘導 iPS細胞を介して体細胞から卵・精子を体外で作製するための研究
piggyBacトランスポゾンを利用したiPS細胞の樹立法 トランスポゾンによる外来因子挿入のないiPS細胞樹立
末梢血・臍帯血等の様々な組織からのiPS細胞樹立 採取が容易な組織からのヒトiPS細胞樹立
末梢血・臍帯血等の様々な組織からのiPS細胞樹立(その2)
リプログラミング関連DNAメチル化変化の解析 iPS細胞樹立に伴うエピジェネティックな変化の解析
リプログラミング関連DNAメチル化変化の解析(その2)
タンパク質によるiPS細胞の樹立 細胞膜透過性組換えタンパク質によるiPS細胞の樹立
真の多能性を示すマーカーの探索 TGを経ないで導入したレポーターによる選抜、厳密なマーカーの探索
iPS細胞とES細胞の遺伝子発現の違い iPS細胞に特徴的な遺伝子発現
iPS細胞とES細胞の遺伝子発現の違い(その2)
iPS細胞株の安全性のバリエーション 由来する細胞種・樹立法が違うiPS細胞におけるガン化リスクの違い
p53,RB経路によるiPS細胞樹立の抑制 p53,RB経路の抑制によるiPS細胞樹立効率の改善
p53,RB経路によるiPS細胞樹立の抑制(その2) Vitamin C、Rem2
p53,RB経路によるiPS細胞樹立の抑制(その3) capase 3, 8、増殖率との関連
低酸素培養によるiPS細胞樹立効率の改善 培養時の酸素濃度がiPS細胞樹立に与える影響
TGFβシグナリング阻害によるiPS細胞樹立効率の改善 ALK5阻害剤(EMD 616452、SB431542)
iPS細胞樹立に有効な線維芽細胞中のサブポピュレーション リプログラミングに有効なマーカーの探索
センダイウイルスを用いたiPS細胞の樹立 センダイウイルスによるゲノム挿入のないiPS細胞樹立
異種成分を含まないコンディションでのヒトiPS細胞樹立 GMP準拠細胞提供への第一歩
ジーンターゲティングによるiPS細胞の樹立 ゲノム上の安全な位置への遺伝子導入によるiPS細胞樹立
線維芽細胞リプログラミングにおけるMET Epithelial-to-mesenchymal transition(EMT)、TGFβ、BMP
iPS細胞における起源細胞由来エピジェネティックメモリーの残存 起源細胞種と分化能との関連
合成mRNAの導入によるiPS細胞の樹立 抗ウイルス応答を受けないように改変した合成RNAの利用
miRNAを用いたiPS細胞の樹立 miR-302,367,372,200c,369を用いたiPS細胞樹立
その他の多能性幹細胞
ES細胞と体細胞の融合技術 ES細胞と融合させることによる体細胞の幹細胞化について
多能性生殖幹細胞(mGS細胞・gPS細胞) 精巣由来の多能性幹細胞の発見について
単為発生ES細胞(pES細胞) 再生医療への応用のための単為発生ES細胞の作出
多能性成体前駆細胞(MAPCs) 骨髄由来の体性幹細胞の多能性・可塑性
卵の幹細胞 卵の新生、骨髄・末梢血・皮膚由来の生殖細胞
※この記事は常にトップに配置しています。※
専門用語解説 専門用語の質問の受付 専門用語集および用語質問受付
ウィキベディア 胚性幹細胞(ES細胞)、人工多能性幹細胞(iPS細胞)のウィキペディア記事へのリンク
幹細胞って何? 幹細胞・TA細胞(前駆細胞)・分化細胞の定義
多能性 分化能の一つである多能性の説明
再生医療に関する3つの誤解 臓器置換から細胞移植への移行、幹細胞とガン化、幹細胞とクローン
将来の再生医療-遺伝子治療との融合- 遺伝病の根治に向けた将来の治療法についての戦略
テロメアについて iPS細胞とクローンにおけるテロメア長
mixiとの連動 このブログとの連動コミュニティー
胚性幹細胞とクローン技術
ES細胞って何? ES細胞の定義・能力
ES細胞ができるまで ES細胞樹立に至るまでの歴史、テラトカルシノーマ、EC細胞、EG細胞
ES細胞樹立時における倫理的問題の回避法 受精卵を破壊しないES細胞の樹立法について
拒絶反応回避とクローン技術 セラピューティッククローニングと呼ばれる技術の歴史、捏造事件
ヒトクローンにおける倫理的問題の回避法 ヒトクローン作出の回避とレシピエント卵の確保について
エピブラストステムセルとヒトES細胞 マウスES細胞とヒトES細胞の違い、EpiSCs、FAB-SCs、rESCs
エピブラストステムセルとヒトES細胞(その2)
ES細胞中のサブポピュレーション ICM様(原始外胚葉様)ES細胞とエピブラスト様ES細胞
ES細胞における自己複製の基底状態 Mek/Erk, GSK3, FGF経路阻害による未分化性維持とラットES細胞
ES細胞からの生殖細胞分化誘導 体外でES細胞から卵および精子を作出する試み
ES細胞とiPS細胞の違い iPS細胞が生まれた経緯、ES細胞研究のメリット・必要性
人工多能性幹細胞
iPS細胞って何? 京都大学 山中伸弥先生によるiPS細胞の第1報 すべてはこの1報から始まった
第二世代マウスiPS細胞 ほぼES細胞と同等の能力を持つiPS細胞の作製について
コロニーの形態によるiPS細胞の選抜法 薬剤選抜なしでの樹立、全身がiPS細胞に由来するマウスの作製
ヒトiPS細胞の樹立 ヒトiPS細胞樹立に関する第1報から第4報、および第6報についての詳細
ガン遺伝子c-MycなしでのiPS細胞の樹立 iPS細胞のc-Myc再発現によるガン化の回避、L-Mycでの代用
肝臓および胃の細胞からのiPS細胞の樹立 レトロウイルス挿入を減らしてガン化リスクを低減
iPS細胞樹立に必要な導入遺伝子発現時間の解析 薬剤誘導系による導入遺伝子発現の必要時間の解析
独バイエル社ヒトiPS細胞論文詳細 特許問題で話題になったヒトiPS細胞樹立に関する論文
Bリンパ球・すい臓β細胞からのiPS細胞樹立 終末分化細胞からもiPS細胞が樹立可能なことの証明
統合ゲノム解析を通したiPS細胞樹立メカニズムの解析 樹立メカニズム解析とDnmt・転写因子阻害効果
ヒトiPS細胞樹立効率の改善とNILベクター使用の試み ヒトiPS細胞第7報の詳細
化学的・遺伝学的手法を組み合わせたiPS細胞の樹立 化合物による代用、G9a・MEK・PRMTの阻害、PS48
小分子化合物によるiPS細胞樹立効率の改善 Dnmt阻害、HDAC阻害(VPA、酪酸)、8-Br-cAMP
神経幹細胞からのiPS細胞樹立 神経幹細胞・神経前駆細胞からの少数の遺伝子によるiPS細胞樹立
複数の細胞種からの遺伝的に均一なiPS細胞の樹立 薬剤誘導系による複数の細胞種からのiPS細胞樹立
Wntシグナリングの刺激によるiPS細胞樹立効率の改善 Wnt経路の刺激による樹立効率改善
難病患者からのiPS細胞樹立 将来の再生医療およびiPS細胞の病因解明・創薬への応用への第一歩
薬剤誘導系によるヒトiPS細胞の樹立 ヒトiPS細胞の樹立に必要な導入遺伝子の発現時間を解析
アデノウイルスを用いたiPS細胞の作製 一時的な遺伝子発現誘導によるiPS細胞作製の第1報
ウイルスを使わないでiPS細胞を樹立 プラスミド、エピソーマル(EB)、minicircleベクターによる一時的な遺伝子発現誘導でiPS細胞作製
髪の毛一本からのヒトiPS細胞樹立 ケラチノサイトからの急速で効率的なヒトiPS細胞樹立
シグナル阻害によるiPS細胞樹立法の改善 Mek/Erk経路およびGSK3の阻害剤を用いたiPS細胞の樹立法
山中ファクター以外の遺伝子を用いたiPS細胞樹立 p53 siRNAとUTF1、Esrrb、ESCC miRNA、Sall4、Nr5a2、Tbx3、Rem2、TCL-1A、YAP
山中ファクター以外の遺伝子を用いたiPS細胞樹立(その2) E-Cadherin、Prmt5、miR-93、miR-106b
マウス・ヒト以外の種でのiPS細胞樹立 山中ファクターを用いた他種でのダイレクトリプログラミング
マウス以外の種におけるマウスES細胞様ES/iPS細胞の樹立 マウス以外の種でのノックアウト動物作製への応用、MEK/ERK, GSK3, AKL5阻害、p38阻害、Forskolin
マウス以外の種におけるマウスES細胞様ES/iPS細胞の樹立(その2) 低酸素培養、NANOG強制発現
単一ベクターによるiPS細胞樹立 ポリシストロニック発現ベクター、Cre/loxPシステムの応用、phage integrase
特定の組み合わせの薬剤誘導リプログラミング因子を持つマウス 代替因子探索ツールの作製
多能性誘導におけるリプログラミング因子の役割 iPS細胞誘導におけるOct4, Sox2, Klf4, c-Mycの機能
多能性誘導におけるリプログラミング因子の役割(その2)
iPS細胞からの生殖細胞分化誘導 iPS細胞を介して体細胞から卵・精子を体外で作製するための研究
piggyBacトランスポゾンを利用したiPS細胞の樹立法 トランスポゾンによる外来因子挿入のないiPS細胞樹立
末梢血・臍帯血等の様々な組織からのiPS細胞樹立 採取が容易な組織からのヒトiPS細胞樹立
末梢血・臍帯血等の様々な組織からのiPS細胞樹立(その2)
リプログラミング関連DNAメチル化変化の解析 iPS細胞樹立に伴うエピジェネティックな変化の解析
リプログラミング関連DNAメチル化変化の解析(その2)
タンパク質によるiPS細胞の樹立 細胞膜透過性組換えタンパク質によるiPS細胞の樹立
真の多能性を示すマーカーの探索 TGを経ないで導入したレポーターによる選抜、厳密なマーカーの探索
iPS細胞とES細胞の遺伝子発現の違い iPS細胞に特徴的な遺伝子発現
iPS細胞とES細胞の遺伝子発現の違い(その2)
iPS細胞株の安全性のバリエーション 由来する細胞種・樹立法が違うiPS細胞におけるガン化リスクの違い
p53,RB経路によるiPS細胞樹立の抑制 p53,RB経路の抑制によるiPS細胞樹立効率の改善
p53,RB経路によるiPS細胞樹立の抑制(その2) Vitamin C、Rem2
p53,RB経路によるiPS細胞樹立の抑制(その3) capase 3, 8、増殖率との関連
低酸素培養によるiPS細胞樹立効率の改善 培養時の酸素濃度がiPS細胞樹立に与える影響
TGFβシグナリング阻害によるiPS細胞樹立効率の改善 ALK5阻害剤(EMD 616452、SB431542)
iPS細胞樹立に有効な線維芽細胞中のサブポピュレーション リプログラミングに有効なマーカーの探索
センダイウイルスを用いたiPS細胞の樹立 センダイウイルスによるゲノム挿入のないiPS細胞樹立
異種成分を含まないコンディションでのヒトiPS細胞樹立 GMP準拠細胞提供への第一歩
ジーンターゲティングによるiPS細胞の樹立 ゲノム上の安全な位置への遺伝子導入によるiPS細胞樹立
線維芽細胞リプログラミングにおけるMET Epithelial-to-mesenchymal transition(EMT)、TGFβ、BMP
iPS細胞における起源細胞由来エピジェネティックメモリーの残存 起源細胞種と分化能との関連
合成mRNAの導入によるiPS細胞の樹立 抗ウイルス応答を受けないように改変した合成RNAの利用
miRNAを用いたiPS細胞の樹立 miR-302,367,372,200c,369を用いたiPS細胞樹立
その他の多能性幹細胞
ES細胞と体細胞の融合技術 ES細胞と融合させることによる体細胞の幹細胞化について
多能性生殖幹細胞(mGS細胞・gPS細胞) 精巣由来の多能性幹細胞の発見について
単為発生ES細胞(pES細胞) 再生医療への応用のための単為発生ES細胞の作出
多能性成体前駆細胞(MAPCs) 骨髄由来の体性幹細胞の多能性・可塑性
卵の幹細胞 卵の新生、骨髄・末梢血・皮膚由来の生殖細胞
※この記事は常にトップに配置しています。※
2016-10-18 00:00:00
iPSから体外で卵子生成 不妊研究に期待 九大など
テーマ:生殖細胞マウスのiPS細胞(人工多能性幹細胞)から体外培養で卵子をつくることに九州大と京都大などの研究チームが成功した。その卵子を体外受精させ、子や孫を得ることもできた。これまでよくわからなかった卵巣内で卵子が育つ過程を培養皿上で詳しく観察できるようになり、不妊の原因解明などにつながると期待される。17日付の英科学誌ネイチャー(電子版)で発表した。
研究チームの林克彦・九州大教授(生殖生物学)らは2012年にiPS細胞から卵子をつくったことを発表している。この時はiPS細胞から卵子や精子の元になる「始原生殖細胞」をつくり、胎児から取り出した将来卵巣に育つ細胞と一緒に培養して、マウスの卵巣に移植していた。
今回はiPS細胞からつくった始原生殖細胞を卵巣に育つ細胞と一緒にした後、体外で培養し続けた。卵子になるまでの約5週間を三つの時期に分けて培養液を使い分けたほか、卵巣内に近い環境を再現して細胞に栄養が行き渡るように、細胞を浸す方法を工夫したり、塊になった細胞を手作業でばらしたりした。
1回の培養で約600個から1千個の卵子ができた。できた卵子を通常の精子と体外受精させて子宮に戻した計1348個の受精卵から、最終的に8匹の子どもが生まれた。通常の体外受精では、約6割の割合で子どもが生まれるといい、それに比べるとかなり低かったが、8匹はいずれも健康で、別のマウスとの間に孫も生まれた。
また、12年の時は、胎児の細胞からつくったiPS細胞を使ったが、今回は大人のメスの尻尾の細胞からiPS細胞をつくっており、大人の卵子の特徴を再現できているという。
さらにES細胞(胚(はい)性幹細胞)でも体外培養で卵子をつくることに成功し、受精卵316個から11匹の子どもが生まれた。
卵巣内で卵子がつくられる過程に異常があれば不妊や遺伝病の原因になる。林教授は「複雑な生殖細胞の分化メカニズムを観察できるようになり、不妊原因や治療法の開発につながる」と話している。
ヒトのiPS細胞からつくった卵子を受精させることは現在、国の指針で禁じられている。研究チームは今後、培養方法をさらに改良し、マウス以外の動物への応用をめざすという。
(朝日新聞)
http://digital.asahi.com/articles/ASJBG7K1SJBGTIPE03H.html?rm=598
iPS細胞 培養で卵子を大量作製
九大や京大などのチームが世界初の成功
マウスの人工多能性幹細胞(iPS細胞)から培養だけで卵子を大量に作ることに世界で初めて成功したと、九州大や京都大などのチームが17日付の英科学誌ネイチャーに発表した。これまでの手法では、作製過程でマウスの卵巣への移植が必要で、人への応用につなげるのは難しかった。今回の作製方法に磨きがかかれば、数年以内に人の卵子作りが実現する可能性もある。
チームの林克彦・九州大教授は「不妊女性のiPS細胞を使って卵子の形成を再現すれば、不妊の原因究明につながる。体外で大量の卵子を作ることができれば、絶滅危惧種の保護にも利用できるかもしれない」としている。
ただ人の卵子の作製は、将来の子の誕生につながり得る技術のため、倫理的な課題も浮上しそうだ。
チームは、生後10週目のマウスの尻尾から作ったiPS細胞で、卵子や精子のもととなる「始原生殖細胞」を作製。その後、体内で卵子ができる約5週間の過程を3段階に分け、さまざまな試薬を用いて培養した。その結果、特定の条件下で計約4000個の卵子ができた。この卵子と通常の精子を体外受精してできた受精卵約1300個からは、8匹のマウスが誕生した。
今回の体外受精でマウスが誕生した割合は、1%未満だった。九州大によると、通常の卵子を使う体外受精の成功率は60〜70%。培養条件を改良するなどして卵子の質を高めることが、今後の課題という。
これまでもマウスのiPS細胞から始原生殖細胞は作られていたが、受精が可能な卵子にするには、別のマウスの卵巣へ移植する必要があり、一度に卵子を作製できる数には限りがあった。
培養だけで作製したのは驚き
国立成育医療研究センター研究所の阿久津英憲・生殖医療研究部長の話 体内で時間をかけて成熟する卵子を、培養だけで作製したのは驚き。卵子ができる過程は謎が多く、その解明につながる。ただ人とマウスでは形成の過程が大きく異なり、人の卵子を作れるようになるには時間がかかる。仮に可能になっても不妊治療などに使うことは、生まれる子への影響も予測できず許されない。作製した卵子の受精を禁じた国の指針を直ちに見直す必要はないが、専門家だけでなく社会を巻き込んだ議論が必要だ。海外での安易な利用を防ぐための国際的な枠組みも求められるだろう。
(毎日新聞)
http://mainichi.jp/articles/20161018/k00/00m/040/106000c
マウスのiPS培養で卵子を大量作製、九州大が世界初 人で実現すれば「不妊の原因究明に」
マウスの人工多能性幹細胞(iPS細胞)から培養だけで卵子を大量に作ることに世界で初めて成功したと、九州大や京都大などのチームが17日付の英科学誌ネイチャーに発表した。この卵子と通常の精子を体外受精させることで、8匹のマウスが誕生。今回の作製方法に磨きがかかれば、数年以内に人の卵子作りが実現する可能性もある。
これまでの手法では、作製過程でマウスの卵巣への移植が必要で、人への応用につなげるのは難しかった。ただ人の卵子の作製は将来、子の誕生につながり得る技術のため、倫理的な課題も浮上しそうだ。 チームの林克彦・九州大教授は「不妊女性のiPS細胞を使って卵子の形成を再現すれば不妊の原因究明につながる。体外で大量の卵子を作ることができれば、絶滅危惧種の保護にも利用できるかもしれない」としている。
チームはマウスの尻尾から作ったiPS細胞で、卵子や精子のもととなる「始原生殖細胞」を作製。その後、さまざまな試薬を用いて培養した結果、特定の条件下で計約4千個の卵子ができた。これに通常の精子を使って約1300個の受精卵を作り、経過を観察した。
(産経ニュース)
http://www.sankei.com/life/news/161018/lif1610180008-n1.html
体外培養で卵子作製=マウスiPS、初成功-九大
マウスの尻尾の組織から人工多能性幹細胞(iPS細胞)を作り、卵子に変化させるまでの全過程を体外培養で実現したと、九州大大学院の林克彦教授らのグループが発表した。体外で卵子の形成過程が観察でき、不妊の原因究明などにつながると期待される。論文は17日付の英科学誌ネイチャー電子版に掲載された。
マウスの卵子は、受精卵から卵子のもとになる始原生殖細胞ができるまでに約6日、その後卵子になるまでに約5週間かかる。この間は袋のような卵胞で育てられ、複雑な過程で形成されるため、体外培養は難しいと考えられていた。
研究グループは、始原生殖細胞から卵子ができるまでの期間を三つに区切り、約3年にわたり培養条件を検討。血清濃度や成長因子、有機化合物などの組み合わせを変え、培養皿で卵子を作製する仕組みを作った。
尻尾の組織のほか、マウスの胎内の子の細胞から作製したiPS細胞や胚性幹細胞(ES細胞)でも卵子を作り出すことに成功した。1回の培養実験でできる卵子が600~1000個と多いのも特徴で、精子と受精させると健常なマウスに成長し、生殖能力も持っていた。
林教授はマウス以外の動物や、絶滅危惧種の保存などに応用を期待する。国内では人のiPS細胞などから作った精子や卵子の受精が禁じられており、人への活用について林教授は「議論の余地はあるが、技術的に達成するベースはできた」と話した。
(時事ドットコム)
http://www.jiji.com/jc/article?k=2016101800007&g=soc
iPSから卵子作製 九大など マウスで成功、出産も
マウスの人工多能性幹細胞(iPS細胞)から体外培養だけで卵子を作ることに世界で初めて成功したと、九州大大学院医学研究院の林克彦教授らのチームが17日付の英科学誌ネイチャー電子版に発表した。全ての過程を培養皿の上で行っており、卵子の形成中に起こる不妊症の原因究明や治療法の開発に寄与するとして注目される。
従来の手法としては、京都大などのチームが胎児のiPS細胞から卵子のもとになる「始原生殖細胞」を作ることに成功し、雌の体内に移植して卵子を作製していた。
九大のチームは、生後10週(ヒトの25~30歳に相当)の雌の尻尾のiPS細胞から始原生殖細胞を作り、液や器具を変えながら培養。胎児の卵巣細胞を混ぜて分化を導き、一つ一つの細胞を手作業で離して成長しやすい配置にし、約4千個の卵子を形成できた。この過程で大切な遺伝子刷り込みも培養皿上で確認した。
これらの卵子と雄の精子を体外受精させてできた約1300個の受精卵を雌に移植したところ、8匹のマウスが誕生。順調に成長して子どもをつくり、iPS細胞から作製した卵子が正常であることを確認した。
不妊症や胎児の発育異常は、卵子の形成過程に起因するケースが指摘されている。林教授は「ブラックボックスだった分裂過程などが観察でき、異常を発見しやすい。ヒトの遺伝子異常の原因解明や創薬などにつなげたい」として、現在は霊長類のマーモセットで同様の研究を続けている。
小川毅彦横浜市立大大学院教授(生命医科学)は「従来の手法ではがん化の可能性もあり、ヒトへの応用に大きな障壁となっていた。不妊症だけでなく絶滅危惧動物の保護や生命誕生のメカニズム解明にも大きな一歩となる」と評価している。
■ヒトへ応用 慎重議論を
iPS細胞による卵子作製は、不妊や先天性疾患の原因究明につながると期待される一方、ヒトへの応用には倫理的問題をはらみ、慎重な議論が求められる。
研究に関する国の指針では、ヒトのiPS細胞から卵子や精子を作ることは認めているが、受精は人為的に命の源を生み出す行為として禁じている。昨年9月には政府の総合科学技術・イノベーション会議生命倫理専門調査会も、受精が必要といえる研究段階には達していないと結論付けた。
ただ、一部には「受精させなければ正常かどうか分からない」と解禁を求める声がある。iPS細胞による生殖細胞研究は国外でも進んでおり、皮膚などから卵子を作る方法が確立されれば、不妊に悩む人が相次いで海を渡る可能性がある。
一方で調査会は、研究が細胞の分裂段階に至った場合などに検討を再開するともしている。九大チームはこの段階まで達しており、今後、ヒトへの応用論議にまで一気に深まる可能性もある。
▼人工多能性幹細胞(iPS細胞) 神経や筋肉、血液などさまざまな組織や臓器になる能力をもつ新型万能細胞。皮膚などの体細胞に数種類の遺伝子を導入して作る。京都大の山中伸弥教授が2006年にマウスで、07年にヒトでの作製に成功。病気や事故で失った細胞や組織の機能を回復する再生医療などへの応用が期待されている。がん化の恐れなど安全面で課題もある。
(西日本新聞)
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/science/article/282563
凄いですねぇ〜
今後、サルなどの大動物での研究がますます重要になりそうです。
プレスリリースは「こちら」
2016-08-25 00:00:00
京大、iPS細胞の分化 一端解明 初期化の解釈へ道
テーマ:生殖細胞京都大学の斎藤通紀教授らは24日、ヒトのiPS細胞が様々な細胞へ育つ謎の一端を解明したと発表した。iPS細胞は事故やケガで傷んだ体の機能を取り戻す再生医療への応用が期待されている。移植に適した神経や臓器などを作るのに参考になりそうだ。英科学誌ネイチャー(電子版)に25日、掲載される。
マウスの胚性幹細胞(ES細胞)はあらゆる細胞に育つが、ヒトのiPS細胞やES細胞は精子や卵子など一部の細胞にはならないとされる。
iPS細胞は、いったん育った細胞を生まれたころに時間を巻き戻す「初期化」という現象が働いている。今回の研究は初期化のしくみを解明する手がかりとなる。
研究チームはヒトとカニクイザルで共通する約700の遺伝子に注目した。ヒトのiPS細胞やES細胞は、受精から16~17日たったサルの胚と遺伝子の状態が似ていた。サルの胚はマウスのES細胞よりも少し成長した段階にあたる。マウスとヒトでは細胞が初期化する程度が違うとみられ、詳しいメカニズムがわかれば様々な細胞ができる謎を解く鍵になる。
(日本経済新聞)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG24H9V_U6A820C1CR8000/
中村さん、おめでとうございます!!
プレスリリースは「こちら」
2015-07-17 00:00:00
iPS細胞から卵子・精子の元 始原生殖細胞、京大教授ら作製
テーマ:生殖細胞ヒトのiPS細胞から卵子と精子の元になる「始原生殖細胞」を効率良く作り出す手法を、京都大の斎藤通紀教授らが確立した。今後、この細胞から卵子や精子が作れるようになれば、不妊や遺伝病の原因解明につながると期待される。
米科学誌セル・ステムセル電子版に17日発表する。始原生殖細胞は受精卵が子宮に着床した後に現れるため、母体から取り出して研究に使うことは倫理的に難しかった。
斎藤さんらはiPS細胞を使ってマウスの始原生殖細胞を作り、卵子と精子に変えて子どもを得ることに世界で初めて成功。だが、ヒト始原生殖細胞を安定して作ることができなかった。
そこで、始原生殖細胞に特徴的な遺伝子が働くと光るiPS細胞を作り、様々な条件で培養。その結果、特定の2種類の化合物で刺激した細胞を使えば、マウスと同じ手法でヒトの始原生殖細胞を効率良く作り出せることがわかった。
(朝日新聞)
http://apital.asahi.com/article/story/2015071700006.html
iPSで精子・卵子のもとの細胞を効率よく作製
人のiPS細胞(人工多能性幹細胞)から、精子や卵子のもとになる「始原生殖細胞」を、従来の手法より数十倍も効率よく作製する方法を開発したと、京都大の斎藤通紀教授らのチームが発表した。人間の生殖細胞ができる詳細な仕組みや、不妊症の原因解明などにつながる可能性がある。17日の米科学誌セル・ステムセル(電子版)に論文が掲載される。
チームは、人のiPS細胞に2種類の試薬を加えて2日間培養し、血液や筋肉などのもとになる細胞を作った。その後、この細胞に別の4種類の試薬をかけ、8日間培養した結果、最大で約60%が始原生殖細胞に変化した。人のiPS細胞から始原生殖細胞を作製した報告例は国内外であるが、多くの場合、作製効率は1%未満と低かった。
チームでは、これまでにマウスのiPS細胞から始原生殖細胞を作製。それをマウスに移植し、精子や卵子に変化させ、子マウスを誕生させる実験に成功している。
今後は、人の精子や卵子が作製できるかどうかが研究の焦点になる。
国の指針では、人のiPS細胞から始原生殖細胞や精子、卵子を作るのは、生命倫理に触れるため規制されているが、研究機関の倫理委員会の承認などを条件に認められている。ただ、作製された精子や卵子を受精させることは禁止されている。
始原生殖細胞
精子や卵子など、生殖細胞の大もとになる細胞。受精卵から胎児になる過程で現れ、性別に応じて精子や卵子に変化していく。
(読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/osaka/news/20150717-OYO1T50009.html
iPSで人の精子や卵子のもと作製 京大が成功
京都大の斎藤通紀教授らは人のiPS細胞から精子や卵子のもととなる「始原生殖細胞」を作る実験に成功した。将来、試験管内で精子や卵子を作れるようになれば、親から子が生まれるしくみの解明に役立つ。成果は17日、米科学誌セル・ステム・セル(電子版)に発表する。
京大iPS細胞研究所から提供を受けた人のiPS細胞を、まず神経に成長しやすい条件で培養し、次に生殖細胞に変わりやすくなる複数の試薬をふりかけた。
iPS細胞が変化した細胞は、マウスやカニクイザルの始原生殖細胞に性質が似ており、研究チームは人の始原生殖細胞ができたと結論づけた。今後は人の精子や卵子を作る技術を開発する計画だ。
研究チームは既に、マウスのiPS細胞から始原生殖細胞を作り、卵子に変えて子供を生ませる実験に成功している。ただ、文部科学省は人のiPS細胞から作った精子や卵子を受精させる実験を禁じている。斎藤教授は「受精の実験を進めて良いかどうかは社会的な議論が必要になる」と話している。
(日本経済新聞)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG16HAU_W5A710C1CR8000/
京大、ヒトiPSから始原生殖細胞を誘導する手法開発-不妊治療法確立に道
京都大学大学院医学研究科の斎藤通紀教授、佐々木恒太郎特定研究員、横林しほり特定助教らの研究グループは、ヒト由来のiPS細胞から精子や卵子のもとになる始原生殖細胞を誘導する手法を開発した。ヒトiPS細胞に、特定の細胞間情報伝達分子(サイトカイン)や薬剤を導入することで、効率よく分化できた。生殖細胞の発生メカニズムや不妊症の原因の解明、また将来の不妊治療法確立につながると期待される。
ヒトとマウスのiPS細胞はそれぞれ異なる性質を持つ。マウスiPS細胞はナイーブ型と呼ばれ、生殖細胞を含むさまざまな細胞に効率良く分化するのに対し、ヒトiPS細胞はプライム型と呼ばれ生殖細胞への分化能力が低い。そのためプライム型での始原生殖細胞への誘導は難しいとされていた。
海外の研究機関などがヒトiPS細胞のナイーブ型への変換を目指す中、研究グループは、一般的なプライム型のヒトiPS細胞から始原生殖細胞への分化を試みた。ゲノム編集技術を使い、始原生殖細胞で発現する遺伝子「BLIMP1」と「TFAP2C」が分化誘導の過程で発現すると、赤色および緑色の蛍光を発するiPS細胞を作った。
アクチビンというサイトカインとカイロンという薬剤を使い、iPS細胞をヒト初期中胚葉様細胞に誘導した。そこにマウスiPS細胞を生殖細胞に誘導する際に使うのと同じ4種のサイトカインを投与すると、細胞が赤と緑の蛍光を発し、BLIMP1とTFAP2Cを発現していることが分かった。
(日刊工業新聞)
http://www.nikkan.co.jp/news/nkx1020150717eaam.html
精子卵子のもと高効率作製、京大 人のiPS細胞から
精子と卵子のもとになる「始原生殖細胞」とみられる細胞を、人の人工多能性幹細胞(iPS細胞)から高い効率で作製する手法の開発に成功したと、京都大の斎藤通紀教授のチームが16日付の米科学誌セルステムセル電子版に発表した。
人の卵子と精子を作る技術の開発につながる成果で、将来的には生物発生のメカニズムの解明や不妊治療法の研究に役立つと期待される。
チームはまず、さまざまな細胞や組織になる人のiPS細胞に薬剤などを加えて「初期中胚葉様細胞」を作った。この細胞にサイトカインと呼ばれるタンパク質を作用させ、始原生殖細胞とよく似た遺伝子パターンを示す細胞を作り出した。
(47News)
http://www.47news.jp/CN/201507/CN2015071601001637.html
ヒトiPSで精子や卵子の元 京大、作成に成功
ヒトiPS細胞(人工多能性幹細胞)から精子や卵子の元となる始原生殖細胞を作ることに、京都大医学研究科の斎藤通紀教授や佐々木恒太郎研究員、京大iPS細胞研究所の横林しほり助教らのグループが成功した。ヒトの生殖細胞の発生メカニズムや不妊症の原因の解明につながる成果で、米科学誌セル・ステムセルで17日に発表する。
斎藤教授らはこれまでに、マウスiPS細胞から始原生殖細胞を経て、精子と卵子を作製している。ヒト始原生殖細胞については、国内外の複数のグループが作製の報告をしているが、手順のあいまいさや再現性の低さで問題があった。
斎藤教授のグループは、ヒトiPS細胞に生理活性物質のアクチビンなど2種類の薬剤を投与して、血液や筋肉になる細胞集団である中胚葉の初期の状態を作り、さらに4種の薬剤を加えて始原生殖細胞を作製した。ヒトやカニクイザルの始原生殖細胞の遺伝子の活動パターンとよく似ており、男女いずれのiPS細胞からもできた。
斎藤教授は「今回の成果は、ヒトiPS細胞から精子や卵子を作る研究の基盤となる」と話している。
<始原生殖細胞>ヒトでは受精卵が細胞分裂を始めて2~3週間後の胚に存在する。性別に応じて精子または卵子へと成長するが、発生のメカニズムはほとんど分かっていない。
(京都新聞)
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20150717000017
佐々木さん、おめでとうございます!!!
凄いクオリティーの論文ですね~
プレスリリースはこちらとこちら。
米科学誌セル・ステムセル電子版に17日発表する。始原生殖細胞は受精卵が子宮に着床した後に現れるため、母体から取り出して研究に使うことは倫理的に難しかった。
斎藤さんらはiPS細胞を使ってマウスの始原生殖細胞を作り、卵子と精子に変えて子どもを得ることに世界で初めて成功。だが、ヒト始原生殖細胞を安定して作ることができなかった。
そこで、始原生殖細胞に特徴的な遺伝子が働くと光るiPS細胞を作り、様々な条件で培養。その結果、特定の2種類の化合物で刺激した細胞を使えば、マウスと同じ手法でヒトの始原生殖細胞を効率良く作り出せることがわかった。
(朝日新聞)
http://apital.asahi.com/article/story/2015071700006.html
iPSで精子・卵子のもとの細胞を効率よく作製
人のiPS細胞(人工多能性幹細胞)から、精子や卵子のもとになる「始原生殖細胞」を、従来の手法より数十倍も効率よく作製する方法を開発したと、京都大の斎藤通紀教授らのチームが発表した。人間の生殖細胞ができる詳細な仕組みや、不妊症の原因解明などにつながる可能性がある。17日の米科学誌セル・ステムセル(電子版)に論文が掲載される。
チームは、人のiPS細胞に2種類の試薬を加えて2日間培養し、血液や筋肉などのもとになる細胞を作った。その後、この細胞に別の4種類の試薬をかけ、8日間培養した結果、最大で約60%が始原生殖細胞に変化した。人のiPS細胞から始原生殖細胞を作製した報告例は国内外であるが、多くの場合、作製効率は1%未満と低かった。
チームでは、これまでにマウスのiPS細胞から始原生殖細胞を作製。それをマウスに移植し、精子や卵子に変化させ、子マウスを誕生させる実験に成功している。
今後は、人の精子や卵子が作製できるかどうかが研究の焦点になる。
国の指針では、人のiPS細胞から始原生殖細胞や精子、卵子を作るのは、生命倫理に触れるため規制されているが、研究機関の倫理委員会の承認などを条件に認められている。ただ、作製された精子や卵子を受精させることは禁止されている。
始原生殖細胞
精子や卵子など、生殖細胞の大もとになる細胞。受精卵から胎児になる過程で現れ、性別に応じて精子や卵子に変化していく。
(読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/osaka/news/20150717-OYO1T50009.html
iPSで人の精子や卵子のもと作製 京大が成功
京都大の斎藤通紀教授らは人のiPS細胞から精子や卵子のもととなる「始原生殖細胞」を作る実験に成功した。将来、試験管内で精子や卵子を作れるようになれば、親から子が生まれるしくみの解明に役立つ。成果は17日、米科学誌セル・ステム・セル(電子版)に発表する。
京大iPS細胞研究所から提供を受けた人のiPS細胞を、まず神経に成長しやすい条件で培養し、次に生殖細胞に変わりやすくなる複数の試薬をふりかけた。
iPS細胞が変化した細胞は、マウスやカニクイザルの始原生殖細胞に性質が似ており、研究チームは人の始原生殖細胞ができたと結論づけた。今後は人の精子や卵子を作る技術を開発する計画だ。
研究チームは既に、マウスのiPS細胞から始原生殖細胞を作り、卵子に変えて子供を生ませる実験に成功している。ただ、文部科学省は人のiPS細胞から作った精子や卵子を受精させる実験を禁じている。斎藤教授は「受精の実験を進めて良いかどうかは社会的な議論が必要になる」と話している。
(日本経済新聞)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG16HAU_W5A710C1CR8000/
京大、ヒトiPSから始原生殖細胞を誘導する手法開発-不妊治療法確立に道
京都大学大学院医学研究科の斎藤通紀教授、佐々木恒太郎特定研究員、横林しほり特定助教らの研究グループは、ヒト由来のiPS細胞から精子や卵子のもとになる始原生殖細胞を誘導する手法を開発した。ヒトiPS細胞に、特定の細胞間情報伝達分子(サイトカイン)や薬剤を導入することで、効率よく分化できた。生殖細胞の発生メカニズムや不妊症の原因の解明、また将来の不妊治療法確立につながると期待される。
ヒトとマウスのiPS細胞はそれぞれ異なる性質を持つ。マウスiPS細胞はナイーブ型と呼ばれ、生殖細胞を含むさまざまな細胞に効率良く分化するのに対し、ヒトiPS細胞はプライム型と呼ばれ生殖細胞への分化能力が低い。そのためプライム型での始原生殖細胞への誘導は難しいとされていた。
海外の研究機関などがヒトiPS細胞のナイーブ型への変換を目指す中、研究グループは、一般的なプライム型のヒトiPS細胞から始原生殖細胞への分化を試みた。ゲノム編集技術を使い、始原生殖細胞で発現する遺伝子「BLIMP1」と「TFAP2C」が分化誘導の過程で発現すると、赤色および緑色の蛍光を発するiPS細胞を作った。
アクチビンというサイトカインとカイロンという薬剤を使い、iPS細胞をヒト初期中胚葉様細胞に誘導した。そこにマウスiPS細胞を生殖細胞に誘導する際に使うのと同じ4種のサイトカインを投与すると、細胞が赤と緑の蛍光を発し、BLIMP1とTFAP2Cを発現していることが分かった。
(日刊工業新聞)
http://www.nikkan.co.jp/news/nkx1020150717eaam.html
精子卵子のもと高効率作製、京大 人のiPS細胞から
精子と卵子のもとになる「始原生殖細胞」とみられる細胞を、人の人工多能性幹細胞(iPS細胞)から高い効率で作製する手法の開発に成功したと、京都大の斎藤通紀教授のチームが16日付の米科学誌セルステムセル電子版に発表した。
人の卵子と精子を作る技術の開発につながる成果で、将来的には生物発生のメカニズムの解明や不妊治療法の研究に役立つと期待される。
チームはまず、さまざまな細胞や組織になる人のiPS細胞に薬剤などを加えて「初期中胚葉様細胞」を作った。この細胞にサイトカインと呼ばれるタンパク質を作用させ、始原生殖細胞とよく似た遺伝子パターンを示す細胞を作り出した。
(47News)
http://www.47news.jp/CN/201507/CN2015071601001637.html
ヒトiPSで精子や卵子の元 京大、作成に成功
ヒトiPS細胞(人工多能性幹細胞)から精子や卵子の元となる始原生殖細胞を作ることに、京都大医学研究科の斎藤通紀教授や佐々木恒太郎研究員、京大iPS細胞研究所の横林しほり助教らのグループが成功した。ヒトの生殖細胞の発生メカニズムや不妊症の原因の解明につながる成果で、米科学誌セル・ステムセルで17日に発表する。
斎藤教授らはこれまでに、マウスiPS細胞から始原生殖細胞を経て、精子と卵子を作製している。ヒト始原生殖細胞については、国内外の複数のグループが作製の報告をしているが、手順のあいまいさや再現性の低さで問題があった。
斎藤教授のグループは、ヒトiPS細胞に生理活性物質のアクチビンなど2種類の薬剤を投与して、血液や筋肉になる細胞集団である中胚葉の初期の状態を作り、さらに4種の薬剤を加えて始原生殖細胞を作製した。ヒトやカニクイザルの始原生殖細胞の遺伝子の活動パターンとよく似ており、男女いずれのiPS細胞からもできた。
斎藤教授は「今回の成果は、ヒトiPS細胞から精子や卵子を作る研究の基盤となる」と話している。
<始原生殖細胞>ヒトでは受精卵が細胞分裂を始めて2~3週間後の胚に存在する。性別に応じて精子または卵子へと成長するが、発生のメカニズムはほとんど分かっていない。
(京都新聞)
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20150717000017
佐々木さん、おめでとうございます!!!
凄いクオリティーの論文ですね~
プレスリリースはこちらとこちら。
2015-05-22 22:00:00
出生前ヒト生殖細胞系列におけるDNAメチル化動態
テーマ:生殖細胞Cell Published online: May 21, 2015
DNA Demethylation Dynamics in the Human Prenatal Germline
Sofia Gkountela, Kelvin X. Zhang, Tiasha A. Shafiq, Wen-Wei Liao, Joseph Hargan-Calvopiña, Pao-Yang Chen, Amander T. Clark
http://www.cell.com/cell/abstract/S0092-8674(15)00560-7
Global DNA demethylation in humans is a fundamental process that occurs in pre-implantation embryos and reversion to naive ground state pluripotent stem cells (PSCs). However, the extent of DNA methylation reprogramming in human germline cells is unknown. Here, we performed whole-genome bisulfite sequencing (WGBS) and RNA-sequencing (RNA-seq) of human prenatal germline cells from 53 to 137 days of development. We discovered that the transcriptome and methylome of human germline is distinct from both human PSCs and the inner cell mass (ICM) of human blastocysts. Using this resource to monitor the outcome of global DNA demethylation with reversion of primed PSCs to the naive ground state, we uncovered hotspots of ultralow methylation at transposons that are protected from demethylation in the germline and ICM. Taken together, the human germline serves as a valuable in vivo tool for monitoring the epigenome of cells that have emerged from a global DNA demethylation event.
あまり話題になっていませんが、えらい論文が出ましたね。
倫理的によく許されたなというのが正直な印象ですが。。
DNA Demethylation Dynamics in the Human Prenatal Germline
Sofia Gkountela, Kelvin X. Zhang, Tiasha A. Shafiq, Wen-Wei Liao, Joseph Hargan-Calvopiña, Pao-Yang Chen, Amander T. Clark
http://www.cell.com/cell/abstract/S0092-8674(15)00560-7
Global DNA demethylation in humans is a fundamental process that occurs in pre-implantation embryos and reversion to naive ground state pluripotent stem cells (PSCs). However, the extent of DNA methylation reprogramming in human germline cells is unknown. Here, we performed whole-genome bisulfite sequencing (WGBS) and RNA-sequencing (RNA-seq) of human prenatal germline cells from 53 to 137 days of development. We discovered that the transcriptome and methylome of human germline is distinct from both human PSCs and the inner cell mass (ICM) of human blastocysts. Using this resource to monitor the outcome of global DNA demethylation with reversion of primed PSCs to the naive ground state, we uncovered hotspots of ultralow methylation at transposons that are protected from demethylation in the germline and ICM. Taken together, the human germline serves as a valuable in vivo tool for monitoring the epigenome of cells that have emerged from a global DNA demethylation event.
あまり話題になっていませんが、えらい論文が出ましたね。
倫理的によく許されたなというのが正直な印象ですが。。
2015-05-07 03:00:00
ヒトES細胞、マウス胚で分化成功 再生医療で応用期待
テーマ:iPS細胞(基礎)万能細胞のヒトES細胞をマウスの胚(はい)に移植し、神経や筋肉などになる細胞に分化させることができたと、近畿大の岡村大治講師(発生生物学)らの研究グループが発表した。人間の体が作られる仕組みの解明などにつながるという。論文が英科学誌ネイチャー電子版に7日、掲載された。
体のさまざまな部位になれる人間の万能細胞をブタなどの動物の胚に入れ、人間の臓器を作ることができれば、再生医療につながると期待されている。だが、人間とは異なる種の細胞を混ぜた状態で成長させるのが難しかった。
岡村さんらのグループは米国のソーク研究所で、ヒトES細胞を独自の方法で培養したうえで、マウスの子宮に着床した胚を取り出して移植。胚を試験管で1日半培養したところ、ES細胞はマウスの細胞と混じり、神経や筋肉などに成長する細胞に分化したことが確認できたという。従来の方法で培養したES細胞は胚の中で育たず、研究グループは「培養方法を変えることで、新しい性質を持ったES細胞を作ることができた」としている。
しかし、着床後に子宮から取り出した胚を戻して成長させる技術は確立されておらず、今回の研究成果を動物の体内で人間の臓器を作ることに、すぐに応用できるわけではないという。
岡村さんは「人間の細胞が着床後にどのように分化していくかを詳しく調べられるので、人間の発生学の研究には大きな前進になる」と話している。
(朝日新聞)
http://www.asahi.com/articles/ASH525K4ZH52PLBJ001.html
ES細胞培養:受精卵と混在でさまざまなヒト組織細胞に
ヒトのES細胞(胚性幹細胞)を特殊な方法で培養し、マウスの受精卵と混ざった状態でさまざまな細胞に変化する能力を持たせることに世界で初めて成功したと、近畿大の岡村大治講師(発生生物学)らが6日付の英科学誌ネイチャー電子版で発表した。移植用のヒトの臓器を動物の体内で作る技術につながる成果で、ヒトの受精卵が成長する過程の研究にも役立つという。
岡村講師が米ソーク研究所に在籍中の研究。マウスのES細胞やiPS細胞(人工多能性幹細胞)は、他の動物の受精卵に混ぜると一緒に成長して体のさまざまな細胞や組織になる。ヒトではこの性質はなく、研究が競争となっていた。
岡村講師らは、特定のたんぱく質の働きを妨げる物質「Wnt抑制剤」などでヒトのES細胞を培養すると、マウスの受精卵に混ぜても増殖を続け、筋肉や神経などのもとになる細胞に分化することを突き止めた。ただ、子宮に着床した後のマウス受精卵で、腹から下になる部分でなければ増殖・分化せず、「領域選択型幹細胞」と名付けた。
さらに、ヒトのES細胞は細胞を1個ずつばらばらにすると死んでしまうが、新たな培養法ではばらばらでも増殖を続けることが分かり、ES細胞の簡単な培養法としても注目される。
移植用の臓器を作らせる動物は、臓器の大きさがヒトに近いブタが想定される。岡村講師は「さらに技術開発が必要だ」と話している。
(毎日新聞)
http://mainichi.jp/select/news/20150507k0000e040092000c.html
人の多能性幹細胞に新能力 マウス受精卵と混じり変化 近畿大講師ら
さまざまな細胞や組織に変化する能力を持つ人の胚性幹細胞(ES細胞)や人工多能性幹細胞(iPS細胞)に、マウスの受精卵と混じり合って変化、増殖する能力を持たせることに成功したと近畿大農学部の岡村大治講師(発生生物学)らが6日付の英科学誌ネイチャー電子版に発表した。
傷ついた体の組織を人の多能性幹細胞で修復する治療法の研究が進む一方、臓器を人の体外で作るのは難しいとされる。新しい能力を持たせたことで、将来、ブタなどの動物の体内で人間の臓器を作り、臓器移植に使う研究に応用できる可能性があるという。
岡村講師らによると、「Wnt抑制剤」という化合物を加えるなどの新たな方法で人のES細胞を培養。着床後のマウスの受精卵に注入すると、下半身に成長する部位に定着し、神経や筋肉などの元となる細胞に分化した。iPS細胞も同様に増殖がみられた。これまで人のES細胞やiPS細胞は、マウスの受精卵に移植しても増殖や分化はしないとされていた。
国内では現在、倫理上の問題から、人の細胞を導入して動物の子を作ることは禁じられている。岡村講師は米ソーク研究所に在籍中に成果としてまとめており、「すぐに実用化に結びつくものではないが、人の発生の仕組み解明にも期待できる」と話している。
(産経新聞)
http://www.sankei.com/west/news/150507/wst1505070020-n1.html
ヒトのES細胞に新能力 近大、マウス胚に移植
近畿大学の岡村大治講師らはヒトの胚性幹細胞(ES細胞)やiPS細胞を特殊な条件で培養すると、マウスの胚の中で神経や筋肉の細胞に育つ性質を示すことを突き止めた。再生医療向けに移植用の臓器を動物の体内でつくる技術につながる可能性があるという。
岡村講師が米ソーク研究所に在籍していた時の研究成果で、英科学誌ネイチャー(電子版)に7日掲載された。
ヒトのES細胞やiPS細胞はあらゆる細胞に育つ能力を持つ。ただ通常の培養法では動物の胚に入れても混ざらず、こうした変化は起こらない。
研究チームは特殊な化合物やたんぱく質などを加えてES細胞を培養した。マウスから着床後の胚を取り出し、将来下半身になる部分にこの細胞を移植すると、神経や筋肉のもととなる細胞に育った。
培養条件の工夫によってES細胞の性質が変わり、マウスの胚の中で死滅せずに増え、成長したと岡村講師は考えている。iPS細胞も同様に増えた。
今回の技術はヒトの発生の仕組み解明に役立つほか、将来、ブタの体内で人間の臓器をつくり患者に移植する再生医療につながる可能性がある。ただ実現にはES細胞などを移植した後の胚を動物の子宮へ戻す技術や、臓器につながる神経や血管をヒトの細胞から作る技術なども必要という。
(日本経済新聞)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG07H31_X00C15A5CR0000/
人の多能性幹細胞に新能力 マウス受精卵と混じり変化
さまざまな細胞や組織に変化する能力を持つ人の胚性幹細胞(ES細胞)や人工多能性幹細胞(iPS細胞)に、マウスの受精卵と混じり合って変化、増殖する能力を持たせることに成功したと近畿大農学部の岡村大治講師(発生生物学)らが6日付の英科学誌ネイチャー電子版に発表した。
傷ついた体の組織を人の多能性幹細胞で修復する治療法の研究が進む一方、臓器を人の体外で作るのは難しいとされる。新しい能力を持たせたことで、岡村講師は「移植用に人の臓器をブタで作らせる技術や、人の発生の仕組み解明に役立つ可能性がある」と話す。
(47NEWS)
http://www.47news.jp/CN/201505/CN2015050601001461.html
動物胚でヒト細胞分化=ESで初確認、将来医療応用も-米ソーク研
一定の条件下でヒトの胚性幹細胞(ES細胞)を培養し、着床後のマウス胚に移植すると、細胞が定着、増殖し神経や筋肉の基となる細胞に分化することを、米ソーク研究所の岡村大治博士研究員(近畿大講師)らのグループが発見した。動物の胚で人間の細胞の分化が確認できたのは世界初という。論文は7日、英科学誌「ネイチャー」電子版に掲載された。
岡村博士研究員は「何年先になるか分からないが、さらに技術革新が進み倫理的な課題が解決されれば、ブタなどの動物で移植用のヒトの臓器を作製できる可能性がある」と話している。
研究グループは、特定のたんぱく質と小分子化合物を用い、培養液として牛の血清を使わない条件で、サルやヒトのES細胞を培養。マウスの子宮から取り出した着床後の胚の後極(将来下半身になる部分)に移植したところ、ES細胞が定着、拡散し分化したという。同様の条件で作ったヒト人工多能性幹細胞(iPS細胞)もマウス胚で定着、拡散したが、ES、iPSいずれも胚の前極側では定着、拡散しなかった。
将来的には、動物体内での人間の臓器作製のほか、着床後のヒト初期発生のメカニズムを明らかにし、流産を防止する治療法などの開発に発展する可能性があるという。
動物体内で人間の臓器を生み出す研究は、人間か動物かはっきりしない生物の誕生につながる恐れがあり、日本では現在承認されていない。
(時事ドットコム)
http://www.jiji.com/jc/c?g=int_30&k=2015050700138
どこのグループかと思いましたが、ソークと聞いてもしやと思ったところ、やはりベルモンテでしたか。
ほんと、何でもやりますね。この人は。
ヒトでのキメラは日本では禁止されていて、かなりグレーな研究ですが、最近のEpiSC関連の複数の論文から考えると、十分に考えられる結果で、誰かやるんじゃないかと思っていましたが、さすが速いですね。。
目的にもよるとは思いますが、厳密なnaive化を目指すのか、はたまた今回の論文のようにより未分化なPrimedでいいのかはまだ一長一短があって難しいところです。ただ、それを補う技術さえあれば、かなり大きな可能性を秘めているのは間違いなさそうですね。
体のさまざまな部位になれる人間の万能細胞をブタなどの動物の胚に入れ、人間の臓器を作ることができれば、再生医療につながると期待されている。だが、人間とは異なる種の細胞を混ぜた状態で成長させるのが難しかった。
岡村さんらのグループは米国のソーク研究所で、ヒトES細胞を独自の方法で培養したうえで、マウスの子宮に着床した胚を取り出して移植。胚を試験管で1日半培養したところ、ES細胞はマウスの細胞と混じり、神経や筋肉などに成長する細胞に分化したことが確認できたという。従来の方法で培養したES細胞は胚の中で育たず、研究グループは「培養方法を変えることで、新しい性質を持ったES細胞を作ることができた」としている。
しかし、着床後に子宮から取り出した胚を戻して成長させる技術は確立されておらず、今回の研究成果を動物の体内で人間の臓器を作ることに、すぐに応用できるわけではないという。
岡村さんは「人間の細胞が着床後にどのように分化していくかを詳しく調べられるので、人間の発生学の研究には大きな前進になる」と話している。
(朝日新聞)
http://www.asahi.com/articles/ASH525K4ZH52PLBJ001.html
ES細胞培養:受精卵と混在でさまざまなヒト組織細胞に
ヒトのES細胞(胚性幹細胞)を特殊な方法で培養し、マウスの受精卵と混ざった状態でさまざまな細胞に変化する能力を持たせることに世界で初めて成功したと、近畿大の岡村大治講師(発生生物学)らが6日付の英科学誌ネイチャー電子版で発表した。移植用のヒトの臓器を動物の体内で作る技術につながる成果で、ヒトの受精卵が成長する過程の研究にも役立つという。
岡村講師が米ソーク研究所に在籍中の研究。マウスのES細胞やiPS細胞(人工多能性幹細胞)は、他の動物の受精卵に混ぜると一緒に成長して体のさまざまな細胞や組織になる。ヒトではこの性質はなく、研究が競争となっていた。
岡村講師らは、特定のたんぱく質の働きを妨げる物質「Wnt抑制剤」などでヒトのES細胞を培養すると、マウスの受精卵に混ぜても増殖を続け、筋肉や神経などのもとになる細胞に分化することを突き止めた。ただ、子宮に着床した後のマウス受精卵で、腹から下になる部分でなければ増殖・分化せず、「領域選択型幹細胞」と名付けた。
さらに、ヒトのES細胞は細胞を1個ずつばらばらにすると死んでしまうが、新たな培養法ではばらばらでも増殖を続けることが分かり、ES細胞の簡単な培養法としても注目される。
移植用の臓器を作らせる動物は、臓器の大きさがヒトに近いブタが想定される。岡村講師は「さらに技術開発が必要だ」と話している。
(毎日新聞)
http://mainichi.jp/select/news/20150507k0000e040092000c.html
人の多能性幹細胞に新能力 マウス受精卵と混じり変化 近畿大講師ら
さまざまな細胞や組織に変化する能力を持つ人の胚性幹細胞(ES細胞)や人工多能性幹細胞(iPS細胞)に、マウスの受精卵と混じり合って変化、増殖する能力を持たせることに成功したと近畿大農学部の岡村大治講師(発生生物学)らが6日付の英科学誌ネイチャー電子版に発表した。
傷ついた体の組織を人の多能性幹細胞で修復する治療法の研究が進む一方、臓器を人の体外で作るのは難しいとされる。新しい能力を持たせたことで、将来、ブタなどの動物の体内で人間の臓器を作り、臓器移植に使う研究に応用できる可能性があるという。
岡村講師らによると、「Wnt抑制剤」という化合物を加えるなどの新たな方法で人のES細胞を培養。着床後のマウスの受精卵に注入すると、下半身に成長する部位に定着し、神経や筋肉などの元となる細胞に分化した。iPS細胞も同様に増殖がみられた。これまで人のES細胞やiPS細胞は、マウスの受精卵に移植しても増殖や分化はしないとされていた。
国内では現在、倫理上の問題から、人の細胞を導入して動物の子を作ることは禁じられている。岡村講師は米ソーク研究所に在籍中に成果としてまとめており、「すぐに実用化に結びつくものではないが、人の発生の仕組み解明にも期待できる」と話している。
(産経新聞)
http://www.sankei.com/west/news/150507/wst1505070020-n1.html
ヒトのES細胞に新能力 近大、マウス胚に移植
近畿大学の岡村大治講師らはヒトの胚性幹細胞(ES細胞)やiPS細胞を特殊な条件で培養すると、マウスの胚の中で神経や筋肉の細胞に育つ性質を示すことを突き止めた。再生医療向けに移植用の臓器を動物の体内でつくる技術につながる可能性があるという。
岡村講師が米ソーク研究所に在籍していた時の研究成果で、英科学誌ネイチャー(電子版)に7日掲載された。
ヒトのES細胞やiPS細胞はあらゆる細胞に育つ能力を持つ。ただ通常の培養法では動物の胚に入れても混ざらず、こうした変化は起こらない。
研究チームは特殊な化合物やたんぱく質などを加えてES細胞を培養した。マウスから着床後の胚を取り出し、将来下半身になる部分にこの細胞を移植すると、神経や筋肉のもととなる細胞に育った。
培養条件の工夫によってES細胞の性質が変わり、マウスの胚の中で死滅せずに増え、成長したと岡村講師は考えている。iPS細胞も同様に増えた。
今回の技術はヒトの発生の仕組み解明に役立つほか、将来、ブタの体内で人間の臓器をつくり患者に移植する再生医療につながる可能性がある。ただ実現にはES細胞などを移植した後の胚を動物の子宮へ戻す技術や、臓器につながる神経や血管をヒトの細胞から作る技術なども必要という。
(日本経済新聞)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG07H31_X00C15A5CR0000/
人の多能性幹細胞に新能力 マウス受精卵と混じり変化
さまざまな細胞や組織に変化する能力を持つ人の胚性幹細胞(ES細胞)や人工多能性幹細胞(iPS細胞)に、マウスの受精卵と混じり合って変化、増殖する能力を持たせることに成功したと近畿大農学部の岡村大治講師(発生生物学)らが6日付の英科学誌ネイチャー電子版に発表した。
傷ついた体の組織を人の多能性幹細胞で修復する治療法の研究が進む一方、臓器を人の体外で作るのは難しいとされる。新しい能力を持たせたことで、岡村講師は「移植用に人の臓器をブタで作らせる技術や、人の発生の仕組み解明に役立つ可能性がある」と話す。
(47NEWS)
http://www.47news.jp/CN/201505/CN2015050601001461.html
動物胚でヒト細胞分化=ESで初確認、将来医療応用も-米ソーク研
一定の条件下でヒトの胚性幹細胞(ES細胞)を培養し、着床後のマウス胚に移植すると、細胞が定着、増殖し神経や筋肉の基となる細胞に分化することを、米ソーク研究所の岡村大治博士研究員(近畿大講師)らのグループが発見した。動物の胚で人間の細胞の分化が確認できたのは世界初という。論文は7日、英科学誌「ネイチャー」電子版に掲載された。
岡村博士研究員は「何年先になるか分からないが、さらに技術革新が進み倫理的な課題が解決されれば、ブタなどの動物で移植用のヒトの臓器を作製できる可能性がある」と話している。
研究グループは、特定のたんぱく質と小分子化合物を用い、培養液として牛の血清を使わない条件で、サルやヒトのES細胞を培養。マウスの子宮から取り出した着床後の胚の後極(将来下半身になる部分)に移植したところ、ES細胞が定着、拡散し分化したという。同様の条件で作ったヒト人工多能性幹細胞(iPS細胞)もマウス胚で定着、拡散したが、ES、iPSいずれも胚の前極側では定着、拡散しなかった。
将来的には、動物体内での人間の臓器作製のほか、着床後のヒト初期発生のメカニズムを明らかにし、流産を防止する治療法などの開発に発展する可能性があるという。
動物体内で人間の臓器を生み出す研究は、人間か動物かはっきりしない生物の誕生につながる恐れがあり、日本では現在承認されていない。
(時事ドットコム)
http://www.jiji.com/jc/c?g=int_30&k=2015050700138
どこのグループかと思いましたが、ソークと聞いてもしやと思ったところ、やはりベルモンテでしたか。
ほんと、何でもやりますね。この人は。
ヒトでのキメラは日本では禁止されていて、かなりグレーな研究ですが、最近のEpiSC関連の複数の論文から考えると、十分に考えられる結果で、誰かやるんじゃないかと思っていましたが、さすが速いですね。。
目的にもよるとは思いますが、厳密なnaive化を目指すのか、はたまた今回の論文のようにより未分化なPrimedでいいのかはまだ一長一短があって難しいところです。ただ、それを補う技術さえあれば、かなり大きな可能性を秘めているのは間違いなさそうですね。
2015-04-28 23:00:00
日本人に合うiPSを備蓄 京大、今秋から提供
テーマ:iPS細胞(応用)京都大学iPS細胞研究所(所長・山中伸弥教授)は28日、再生医療で使う治療用のiPS細胞を備蓄し、今秋から提供を始めると発表した。日本人で拒絶反応を起こしにくいiPS細胞をつくり、病気やケガの時の移植に備える。3年以内に日本人の3~5割をカバーできるようにする。必要なときに安価なコストで提供する体制を整え、iPS医療の普及を後押しする。
京大iPS研医療応用推進室の高須直子室長は28日の記者会見で「(iPS細胞の提供開始で)臨床に弾みがつくのではないか」と期待を示した。
iPS細胞をあらかじめ神経の細胞に成長させ、事故やケガで脊髄が傷ついた患者に移植するなどの備えができる。ただちに治療に入れば、治りやすくなる。
臓器や神経の治療では、桁違いに多くの細胞が必要になるだけに、安全性を確かめたiPS細胞を備蓄しておく利点が生きる。政府は2013年度から10年間にわたり、年27億円の予算を支援する。
これまでの再生医療は患者自身の細胞からiPS細胞を育て、傷んだ体の機能を取り戻す計画が先行している。本人のiPS細胞は、拒絶反応は避けられるが、コストが高く、移植までに半年以上かかる。理化学研究所が昨秋、目の難病治療の研究にかけた培養期間は10カ月で、費用は5000万~1億円ほどだった。
iPS細胞のタイプを示す細胞の型(HLA型)は数万種類を数え、日本人だけでも1万種類以上ある。一人ひとり少しずつ違い、他人のiPS細胞で拒絶反応が起きる原因になっている。HLA型が他人と完全に一致する確率は1万~100万人に1人とされる。
京大は日本赤十字社と協力し、特別なHLA型を持つ人を見つけた。この人からつくったiPS細胞は日本人の約20%の人で拒絶反応を起こしにくいという。血液の提供を受け、治療用iPS細胞の作製に取りかかった。
さらに22年度末までに、ほかにも日本人に合うHLA型の人を探す。すでに10人程度を絞り込み、数人から血液を採取した。3年以内に5~10人を突き止め、日本人の3~5割をカバーする。140人を特定すれば、日本人の9割に対応できるという。
備蓄が軌道に乗れば、患者からオーダーメードで培養するのに比べ、安いコストと短い期間でiPS細胞を提供できる見通し。ただ、1人の提供者からiPS細胞をつくり、備蓄用に安全性を検査するだけで2000万円以上かかる。運用の効率を上げる必要もある。
(日本経済新聞)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGG28H2Y_Y5A420C1EA2000/
今秋にもストック提供を開始 医療用iPS細胞で 京都大
京都大iPS細胞研究所は28日、拒絶反応が起こりにくいタイプの人工多能性幹細胞(iPS細胞)を備蓄しておくストックプロジェクトで、実際に再生医療で使用できる安全性を備えたiPS細胞の研究機関などへの提供を、今秋にもスタートすることを明らかにした。第1号は日本人の約20%に適合するiPS細胞になるという。
同プロジェクトは、日本赤十字社などと連携。献血した人などから拒絶反応が起こりにくいタイプの細胞を持つ人を探して同意を得たうえで提供してもらい、iPS細胞を作製して備蓄する。
すでに、日本人で最も多くの人に適合するタイプのiPS細胞を作製。現在は遺伝子に異常がないかといった安全性の検証を進めている。日本人の約20%で拒絶反応が起こりにくいiPS細胞を、今秋ごろ大学などの研究機関に提供できるという。製薬会社などにも有償で提供する。
さらに、現時点で拒絶反応が起こりにくいタイプの細胞を持つ人は十数人見つかっているといい、これから順次iPS細胞の作製を進める。平成29年度までに日本人の30~50%、34年度には80~90%をカバーできるiPS細胞をそろえることを目指している。
再生医療では、患者本人から作製するiPS細胞を使えば拒絶反応は起きないが、かかる費用と時間が大きい。そこで、あらかじめ拒絶反応が起こりにくいiPS細胞を作製して備蓄しておくことで、時間と費用を抑えることができると期待されている。
(産経新聞)
http://www.sankei.com/west/news/150428/wst1504280069-n1.html
京大研究所 iPS細胞を秋にも配付へ
京都大学iPS細胞研究所は、拒絶反応が起きにくい特殊なiPS細胞をこの秋をめどに希望する大学病院などに配付し、再生医療の臨床研究に役立ててもらうことになりました。
これは28日、京都大学iPS細胞研究所が明らかにしたものです。
体のあらゆる組織になるとされるiPS細胞は、病気やけがで失われた体の機能を取り戻す再生医療への応用が期待されていますが、患者1人1人から作り出すとコストがかかるのが課題です。このため京都大学iPS細胞研究所は、特殊なタイプの免疫を持つ人に協力してもらい他人に移植しても拒絶反応が起きにくいiPS細胞を作って誰にでも使えるようにする事業を進めていますが、この秋をめどに希望する国内の大学病院などに配付できるようになったということです。
目の網膜の病気や脊髄損傷などの治療を目指す臨床研究に応用される予定だということでiPS細胞研究所の金子新准教授は「1日も早く患者に届けられるよう確実に進めていきたい」と話しています。
(NHKニュース)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150429/k10010064591000.html
これで応用研究にさらに弾みがつきそうですね。
「将来の再生医療-遺伝子治療との融合-」もご参照下さい。
京大iPS研医療応用推進室の高須直子室長は28日の記者会見で「(iPS細胞の提供開始で)臨床に弾みがつくのではないか」と期待を示した。
iPS細胞をあらかじめ神経の細胞に成長させ、事故やケガで脊髄が傷ついた患者に移植するなどの備えができる。ただちに治療に入れば、治りやすくなる。
臓器や神経の治療では、桁違いに多くの細胞が必要になるだけに、安全性を確かめたiPS細胞を備蓄しておく利点が生きる。政府は2013年度から10年間にわたり、年27億円の予算を支援する。
これまでの再生医療は患者自身の細胞からiPS細胞を育て、傷んだ体の機能を取り戻す計画が先行している。本人のiPS細胞は、拒絶反応は避けられるが、コストが高く、移植までに半年以上かかる。理化学研究所が昨秋、目の難病治療の研究にかけた培養期間は10カ月で、費用は5000万~1億円ほどだった。
iPS細胞のタイプを示す細胞の型(HLA型)は数万種類を数え、日本人だけでも1万種類以上ある。一人ひとり少しずつ違い、他人のiPS細胞で拒絶反応が起きる原因になっている。HLA型が他人と完全に一致する確率は1万~100万人に1人とされる。
京大は日本赤十字社と協力し、特別なHLA型を持つ人を見つけた。この人からつくったiPS細胞は日本人の約20%の人で拒絶反応を起こしにくいという。血液の提供を受け、治療用iPS細胞の作製に取りかかった。
さらに22年度末までに、ほかにも日本人に合うHLA型の人を探す。すでに10人程度を絞り込み、数人から血液を採取した。3年以内に5~10人を突き止め、日本人の3~5割をカバーする。140人を特定すれば、日本人の9割に対応できるという。
備蓄が軌道に乗れば、患者からオーダーメードで培養するのに比べ、安いコストと短い期間でiPS細胞を提供できる見通し。ただ、1人の提供者からiPS細胞をつくり、備蓄用に安全性を検査するだけで2000万円以上かかる。運用の効率を上げる必要もある。
(日本経済新聞)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGG28H2Y_Y5A420C1EA2000/
今秋にもストック提供を開始 医療用iPS細胞で 京都大
京都大iPS細胞研究所は28日、拒絶反応が起こりにくいタイプの人工多能性幹細胞(iPS細胞)を備蓄しておくストックプロジェクトで、実際に再生医療で使用できる安全性を備えたiPS細胞の研究機関などへの提供を、今秋にもスタートすることを明らかにした。第1号は日本人の約20%に適合するiPS細胞になるという。
同プロジェクトは、日本赤十字社などと連携。献血した人などから拒絶反応が起こりにくいタイプの細胞を持つ人を探して同意を得たうえで提供してもらい、iPS細胞を作製して備蓄する。
すでに、日本人で最も多くの人に適合するタイプのiPS細胞を作製。現在は遺伝子に異常がないかといった安全性の検証を進めている。日本人の約20%で拒絶反応が起こりにくいiPS細胞を、今秋ごろ大学などの研究機関に提供できるという。製薬会社などにも有償で提供する。
さらに、現時点で拒絶反応が起こりにくいタイプの細胞を持つ人は十数人見つかっているといい、これから順次iPS細胞の作製を進める。平成29年度までに日本人の30~50%、34年度には80~90%をカバーできるiPS細胞をそろえることを目指している。
再生医療では、患者本人から作製するiPS細胞を使えば拒絶反応は起きないが、かかる費用と時間が大きい。そこで、あらかじめ拒絶反応が起こりにくいiPS細胞を作製して備蓄しておくことで、時間と費用を抑えることができると期待されている。
(産経新聞)
http://www.sankei.com/west/news/150428/wst1504280069-n1.html
京大研究所 iPS細胞を秋にも配付へ
京都大学iPS細胞研究所は、拒絶反応が起きにくい特殊なiPS細胞をこの秋をめどに希望する大学病院などに配付し、再生医療の臨床研究に役立ててもらうことになりました。
これは28日、京都大学iPS細胞研究所が明らかにしたものです。
体のあらゆる組織になるとされるiPS細胞は、病気やけがで失われた体の機能を取り戻す再生医療への応用が期待されていますが、患者1人1人から作り出すとコストがかかるのが課題です。このため京都大学iPS細胞研究所は、特殊なタイプの免疫を持つ人に協力してもらい他人に移植しても拒絶反応が起きにくいiPS細胞を作って誰にでも使えるようにする事業を進めていますが、この秋をめどに希望する国内の大学病院などに配付できるようになったということです。
目の網膜の病気や脊髄損傷などの治療を目指す臨床研究に応用される予定だということでiPS細胞研究所の金子新准教授は「1日も早く患者に届けられるよう確実に進めていきたい」と話しています。
(NHKニュース)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150429/k10010064591000.html
これで応用研究にさらに弾みがつきそうですね。
「将来の再生医療-遺伝子治療との融合-」もご参照下さい。
2015-04-27 23:00:00
iPS細胞から免疫細胞 がん患者治療へ
テーマ:iPS細胞(応用)理化学研究所などの研究チームが、iPS細胞からがんを攻撃する免疫細胞を作り出し、がん患者に移植して治療する臨床研究の計画を進めていることを明らかにしました。平成30年ごろの実施を目指したいということです。
臨床研究を計画しているのは、理化学研究所の古関明彦グループディレクターらと千葉大学病院の研究グループです。
免疫細胞の一種・NKT細胞は、がん細胞を攻撃して縮小させる作用がありますが、がんが大きくなると患者の体内にあるNKT細胞だけでは抑えられないということです。
このため研究グループではiPS細胞からNKT細胞を5000万個程度作り出し、患者に移植して安全性や効果を確かめる臨床研究の計画を進めているということです。
すでにヒトのiPS細胞からNKT細胞を作ることには成功しているということで、平成30年ごろをめどに舌がん=舌のがんのほか、顔やのどにできるがんを対象にNKT細胞を移植して治療する臨床研究を始めたいとしています。
古関グループディレクターは「体の中で広がったがんをこの方法で小さくできれば、手術の負担も小さくできる。多くの人が受けられる新しい治療法になる可能性があると考えている」と話しています。
(NHKニュース)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150422/k10010056351000.html
久しぶりの更新です。
最近はかなり応用に関連したニュースが増えてきましたね。
素晴らしいことだと思います。
昔はなんとかほとんどのiPS関連論文をフォロー出来ていましたが、最近は時間的な制約もあって自分の専門分野の論文をフォローするのが精一杯で、なかなかブログをアップできずに申し訳ないです。
今回はiPS細胞と免疫療法の組み合わせが個人的に興味があり、紹介させて頂きたいと思います。
将来への希望が膨らむ研究ですね。
臨床研究を計画しているのは、理化学研究所の古関明彦グループディレクターらと千葉大学病院の研究グループです。
免疫細胞の一種・NKT細胞は、がん細胞を攻撃して縮小させる作用がありますが、がんが大きくなると患者の体内にあるNKT細胞だけでは抑えられないということです。
このため研究グループではiPS細胞からNKT細胞を5000万個程度作り出し、患者に移植して安全性や効果を確かめる臨床研究の計画を進めているということです。
すでにヒトのiPS細胞からNKT細胞を作ることには成功しているということで、平成30年ごろをめどに舌がん=舌のがんのほか、顔やのどにできるがんを対象にNKT細胞を移植して治療する臨床研究を始めたいとしています。
古関グループディレクターは「体の中で広がったがんをこの方法で小さくできれば、手術の負担も小さくできる。多くの人が受けられる新しい治療法になる可能性があると考えている」と話しています。
(NHKニュース)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20150422/k10010056351000.html
久しぶりの更新です。
最近はかなり応用に関連したニュースが増えてきましたね。
素晴らしいことだと思います。
昔はなんとかほとんどのiPS関連論文をフォロー出来ていましたが、最近は時間的な制約もあって自分の専門分野の論文をフォローするのが精一杯で、なかなかブログをアップできずに申し訳ないです。
今回はiPS細胞と免疫療法の組み合わせが個人的に興味があり、紹介させて頂きたいと思います。
将来への希望が膨らむ研究ですね。
2014-09-12 09:00:00
世界初のiPS移植実施 目の難病患者に、神戸の医療機関で
テーマ:iPS細胞(応用)人工多能性幹細胞(iPS細胞)を使って目の難病治療を目指す理化学研究所などのチームは12日、iPS細胞から作った網膜細胞を患者に移植する手術を先端医療センター病院(神戸市)で実施したと発表した。iPS細胞が臨床に応用されたのは世界初で、再生医療での実用化に向けて大きな一歩となった。
同病院の平田結喜緒病院長、理研の高橋政代プロジェクトリーダーらが同日夜、神戸市内で記者会見し、手術の結果などを説明する。
理研などによると、移植手術を受けたのは「滲出(しんしゅつ)型加齢黄斑(おうはん)変性」という目の難病で、既存の治療法では効果がなかった患者。自分の皮膚細胞から作ったiPS細胞を使って、網膜の働きを助ける網膜色素上皮細胞を作り、シート状に加工して病変部に移植した。
移植は高橋氏らが進める臨床研究として実施。安全性の確認が主な目的で、1年間の経過観察と3年間の追跡調査で腫瘍ができないかなどを調べる。
チームは昨年2月、厚生労働省に臨床研究の実施を申請し、同7月に承認。厚労省の審査委員会は今月8日、使用する細胞の安全性に問題はないとして移植を了承した。
iPS細胞は体のさまざまな細胞に分化できる万能細胞の一種。京都大の山中伸弥教授が平成19年にヒトで作製に成功し、24年にノーベル医学・生理学賞を受賞した。
別の万能細胞である胚性幹細胞(ES細胞)が受精卵を壊して作るため倫理問題を抱えているのに対し、皮膚から作れる利点があり、病気やけがで損傷した組織を復元する再生医療への応用が期待されていた。
加齢黄斑変性は、網膜の中心にある黄斑という部分が老化により機能低下を起こし、視力が低下する病気。患者数は近年、急増している。iPS細胞を使った移植治療でも視力はやや改善する程度だが、チームは根治療法になる可能性があるとみて研究を進める。
(MSN産経ニュース)
http://sankei.jp.msn.com/science/news/140912/scn14091217200005-n1.htm
iPS細胞:世界初の移植手術 目の難病患者に
理化学研究所などが進めるiPS細胞(人工多能性幹細胞)を目の難病治療に使う臨床研究で、iPS細胞から作った網膜色素上皮細胞を70代の女性患者(兵庫県)に移植する手術が12日、共同研究機関の先端医療センター病院(神戸市中央区)で実施された。iPS細胞から作った細胞を患者に移植したのは世界で初めて。安全性の確認が手術の主な目的だが、視力の改善など有効性も調べる。iPS細胞の臨床研究はパーキンソン病や重症心不全なども控えており、今回の手術はiPS細胞を活用した再生医療実現への第一歩と位置づけられる。
臨床研究の対象は、悪化すると失明の恐れもある「滲出型(しんしゅつがた)加齢黄斑変性」。昨年8月、理研発生・再生科学総合研究センター(CDB)の高橋政代・プロジェクトリーダー(53)を中心に開始。目の網膜中心部(黄斑部)の傷ついた色素上皮細胞を摘出し、代わりにiPS細胞から作製したシート状の色素上皮細胞を移植する計画を進めていた。理研が、患者の皮膚細胞から作ったiPS細胞を使って細胞シートを作製し、先端医療センター病院が移植手術を担当した。
研究チームによると、投薬を中心とする現在の治療法では傷ついた網膜の修復はできず、今回の手術を受けた患者もこれまで治療を続けてきたが、症状が悪化していたという。
手術は、異常な血管ができて傷ついた色素上皮を専用の器具で取り除き、縦1.3ミリ、横3ミリの色素上皮細胞のシートで置き換えた。患者は3~7日後に退院し、定期的に検査を受ける。計6人の手術を計画しているが、2人目以降の時期は未定だ。
研究チームによると、色素上皮がiPS細胞治療の最初の臨床研究対象に選ばれたのは▽移植する細胞の数が少なくて済む▽がん化しにくい▽移植後の詳細な観察が可能--などが挙げられる。しかし、第1号だけに、iPS細胞や細胞シートの安全性の確認は慎重に行われ、患者の皮膚採取から細胞シート作製まで約10カ月かけた。
ノーベル医学生理学賞を受賞した山中伸弥・京都大iPS細胞研究所長(52)がiPS細胞を開発した当初は、がん遺伝子やウイルスを利用したためがん化が実用化への課題だった。今回は、山中所長らの最新の研究成果を生かし、がん遺伝子やウイルスを使わない方法を採用。マウスへの移植でがん化しないことも確かめた。
(毎日新聞)
http://mainichi.jp/select/news/20140913k0000m040001000c.html
iPS細胞の移植手術を実施 理研、世界で初めて
理化学研究所などのチームが12日、目の難病患者の皮膚から作製したiPS細胞(人工多能性幹細胞)を網膜の組織に分化させ、患者に移植する手術を実施したと発表した。iPS細胞を使った治療を人で試すのは世界初。手術の安全性を確認するのが目的で、計6人に実施する予定だ。同日夜に記者会見する。
理研発生・再生科学総合研究センター(CDB)の高橋政代プロジェクトリーダーを中心に研究を進め、先端医療振興財団(神戸市)の先端医療センター病院が手術を実施した。
手術を受けたのは、網膜の下の細胞が傷み、視力が落ちたり視界がゆがんだりする難病「加齢黄斑変性」の患者。兵庫県在住の70代の女性という。
(朝日新聞)
http://www.asahi.com/articles/ASG9C5QJKG9CPLBJ005.html
理研、目の難病にiPS細胞で世界初の手術
理化学研究所発生・再生科学総合研究センターと先端医療センター病院(ともに神戸市)は12日、iPS細胞(人工多能性幹細胞)から作った網膜細胞を、目の難病「加齢黄斑おうはん変性」の患者に移植する臨床研究の手術を行ったと発表した。
様々な組織や臓器の細胞に変化させられるiPS細胞を用いた治療は世界で初めて。
理研の高橋政代・プロジェクトリーダーらが移植用細胞の作製を、同病院の栗本康夫・眼科統括部長らが移植手術を担当した。
発表によると、患者は兵庫県在住の70歳代女性。数年前から症状の進行を食い止める治療を受けたが効果はなく、視力が徐々に低下していた。
手術計画では、全身麻酔をかけた後、目の表面に穴を開け、傷んだ網膜組織や、異常な血管を除去。その部分に、管状の特殊な器具を使って網膜細胞のシートを貼り付ける。手術は同病院でこの日午後1時40分頃に始まり、午後4時20分に終了した。
高橋氏らは患者の選定基準に従い、女性を第1例患者に選んだ。女性から採取した皮膚細胞に6種類の遺伝子を入れて、iPS細胞を作製。さらに特殊なたんぱく質を加えて約10か月かけて培養し、長さ3ミリ、幅1・3ミリの短冊状の細胞シートに加工した。
加齢黄斑変性は、網膜の中央にある「黄斑」を構成する細胞の一部が傷み、視界の中央がゆがんだり黒く欠けたりする病気。注射薬やレーザーで治療するが、完治はせず、患者によっては効果がないこともある。
(読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/science/20140912-OYT1T50105.html
世界初iPS手術、目の難病に実施 理研と先端医療財団
理化学研究所と先端医療振興財団(神戸市)は12日、神戸市にある同財団先端医療センター病院で、iPS細胞を使った世界初の臨床研究として目の難病患者に手術を実施した。京都大学の山中伸弥教授が世界に先駆けてマウスの細胞からiPS細胞を作り出したのが2006年。いよいよ医療応用に向けた動きが本格化する。
手術をしたのは「加齢黄斑変性」と呼ぶ難病を持つ兵庫県に住む70代の女性。この病気は年齢とともに視力が低下し、症状が進むと失明することもある。
理研の高橋政代プロジェクトリーダーを中心とする臨床研究で、細胞を移植する手術は同病院の栗本康夫・眼科統括部長が主導した。今回は移植した細胞が体内でがん化しないかなどの安全性の検証を主な目的としているが、症状改善にも期待を寄せている。
iPS細胞は病気やケガで損なわれた臓器などの機能回復を目指す再生医療の「切り札」といわれる。国も日本発の先端技術の実用化と普及を積極的に後押ししている。iPS細胞を作製した山中教授は12年にノーベル生理学・医学賞を受賞した。
今回の目の難病に続き、手足などが震えるパーキンソン病や、脊髄損傷などでもiPS細胞を治療に役立てようとする計画が進んでいる。
(日本経済新聞)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGG1200D_S4A910C1000000/
iPS、世界初の移植手術 目の難病患う70代女性に
理化学研究所と先端医療センター病院(神戸市)は12日、さまざまな細胞に成長できる人工多能性幹細胞(iPS細胞)から作った網膜の細胞を、目の難病「滲出型加齢黄斑変性」を患う兵庫県の70代女性に移植した。iPS細胞から作った細胞を人体に入れる手術は世界初。
がん化などの問題が起きないか確認するのが主な目的。京都大の山中伸弥教授が開発したiPS細胞を利用する再生医療の今後を占う手術として注目される。
理研などによると、患者の女性の皮膚から採った細胞に遺伝子を導入し、iPS細胞を作製。さらに目の網膜の色素上皮細胞に成長させ、移植用のシートを作った。
(47NEWS)
http://www.47news.jp/CN/201409/CN2014091201001410.html
iPS臨床、初の移植=目の難病患者に-安全性、効果検証・理研など
人工多能性幹細胞(iPS細胞)を用いた世界初の臨床研究を進めている理化学研究所発生・再生科学総合研究センター(神戸市)などのチームは12日、目の難病を患う兵庫県内の70代女性に、iPS細胞から作った網膜の細胞を移植する手術を行った。
臨床研究の主な目的は安全性の検証。移植した細胞が根付くか、がんになる危険がないかなどを4年かけて確認する。視力回復の効果があるかも合わせて調べる。
研究代表は高橋政代理研プロジェクトリーダー。手術は先端医療センター病院(同)で栗本康夫医師らが担当した。
移植の対象は、網膜に異常な血管が生えて視力が低下する「滲出(しんしゅつ)型加齢黄斑変性」の患者。薬など従来の治療では効果が得られない人を選んだ。
手術では、網膜のうち光を感じる「神経網膜」に栄養を送る「色素上皮」の傷んだ部分を除去。患者の皮膚から作ったiPS細胞を色素上皮の細胞に変え、シート状にしたものを代わりに移植する内容だ。
(時事ドットコム)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2014091200694
山中教授が全面支援=発表前に提供、ゲノム解析も-iPS臨床
iPS細胞を使った世界初の移植手術が実現するまでには、開発者でノーベル医学生理学賞を受賞した山中伸弥京都大教授の全面的な支援があった。
山中教授が所長を務める京大iPS細胞研究所は、iPS細胞を作る際に必要な環状DNA「プラスミド」を理研に提供した。理研の高橋政代プロジェクトリーダーは「論文の発表前から、前よりいいプラスミドができたら提供してもらってきた」と明かす。
さらに同研究所は、臨床手術で用いるiPS細胞の全遺伝情報(ゲノム)解析を実施。山中教授は今月、厚生労働省の審査委員会で解析結果を報告した。審査委は報告内容を検討し、移植実施に問題がないと判断、手術が可能になった。
高橋氏は山中教授がノーベル賞の受賞後、臨床研究をPRしてくれたと紹介。「常に精神的にも応援してもらっている」と話している。
(時事ドットコム)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2014091200713
iPSから網膜細胞 世界初の移植手術実施 神戸
先端医療センター病院(神戸市中央区)と理化学研究所発生・再生科学総合研究センター(同)は12日午後、人工多能性幹細胞(iPS細胞)から網膜色素上皮細胞を作り、目の難病患者の網膜を再生させる臨床研究で、1例目の移植手術を実施したと発表した。iPS細胞から作った細胞が人の体に移植されるのは世界初。
患者は失明の恐れもある難病「滲出型加齢黄斑変性」で、兵庫県内の70代女性。同病院などは皮膚組織を採取してiPS細胞を作り、網膜色素上皮細胞に変化させシート状にして移植した。今後、腫瘍ができないかなどの安全性や、視野の改善などの効果を検証する。
(神戸新聞)
http://www.kobe-np.co.jp/news/iryou/201409/0007324118.shtml
世界初iPS細胞使った手術実施
神戸市にある理化学研究所などの研究チームは、iPS細胞を使って目の網膜の組織を再生し、病気で失われた患者の視力を回復させようという世界初の臨床研究の手術を、12日実施したと発表しました。
手術を受けたのは「加齢黄斑変性」という重い目の病気の70代の女性で京都大学の山中伸弥教授が開発したiPS細胞が、実際の患者の治療に使われた初めてのケースになります。
(NHKニュース)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140912/t10014562731000.html
世界初の手術 iPS細胞の網膜を移植
ノーベル賞を受賞した京都大学の山中伸弥教授が開発した万能細胞「iPS細胞」から作られた組織を患者に移植する、世界で初めての臨床手術が12日に神戸で行われた。
世界で初めての手術は、神戸の理化学研究所の隣にある病院の中で行われた。この手術は患者の目の網膜にiPS細胞から作られた組織を移植するもので、手術は無事に成功した。
患者は70代の女性で、片方の目の網膜組織に傷がつき、視力が急激に低下する「加齢黄斑変性」という難病を抱えている。
この手術は、目の再生医療の第一人者である理化学研究所の高橋政代プロジェクトリーダーらが計画してきた。高橋氏たちは、患者の皮膚からiPS細胞を作製。約10か月間培養して、シート状の網膜組織に変化させた。
シートを移植する手術は、眼科医をはじめ、8人ほどの医療チームが、3時間弱かけて行った。高橋氏は執刀はしていないが、手術室で見守ったという。順調にいけば、患者は2~3か月後に症状の改善が見られるようになる。現在、患者は麻酔から目覚め、容体は安定しているという。
iPS細胞を使った臨床研究は神経細胞や血小板など他の組織でも進められており、今回の1例目の治療の行方に注目されている。
(日テレNEWS24)
http://news24.jp/articles/2014/09/12/07259042.html
久しぶりにブログ更新したらえらいビッグニュースが飛び込んできました!!
ついに始まったようです。
今後に期待しつつ、冷静に見守りましょう。
同病院の平田結喜緒病院長、理研の高橋政代プロジェクトリーダーらが同日夜、神戸市内で記者会見し、手術の結果などを説明する。
理研などによると、移植手術を受けたのは「滲出(しんしゅつ)型加齢黄斑(おうはん)変性」という目の難病で、既存の治療法では効果がなかった患者。自分の皮膚細胞から作ったiPS細胞を使って、網膜の働きを助ける網膜色素上皮細胞を作り、シート状に加工して病変部に移植した。
移植は高橋氏らが進める臨床研究として実施。安全性の確認が主な目的で、1年間の経過観察と3年間の追跡調査で腫瘍ができないかなどを調べる。
チームは昨年2月、厚生労働省に臨床研究の実施を申請し、同7月に承認。厚労省の審査委員会は今月8日、使用する細胞の安全性に問題はないとして移植を了承した。
iPS細胞は体のさまざまな細胞に分化できる万能細胞の一種。京都大の山中伸弥教授が平成19年にヒトで作製に成功し、24年にノーベル医学・生理学賞を受賞した。
別の万能細胞である胚性幹細胞(ES細胞)が受精卵を壊して作るため倫理問題を抱えているのに対し、皮膚から作れる利点があり、病気やけがで損傷した組織を復元する再生医療への応用が期待されていた。
加齢黄斑変性は、網膜の中心にある黄斑という部分が老化により機能低下を起こし、視力が低下する病気。患者数は近年、急増している。iPS細胞を使った移植治療でも視力はやや改善する程度だが、チームは根治療法になる可能性があるとみて研究を進める。
(MSN産経ニュース)
http://sankei.jp.msn.com/science/news/140912/scn14091217200005-n1.htm
iPS細胞:世界初の移植手術 目の難病患者に
理化学研究所などが進めるiPS細胞(人工多能性幹細胞)を目の難病治療に使う臨床研究で、iPS細胞から作った網膜色素上皮細胞を70代の女性患者(兵庫県)に移植する手術が12日、共同研究機関の先端医療センター病院(神戸市中央区)で実施された。iPS細胞から作った細胞を患者に移植したのは世界で初めて。安全性の確認が手術の主な目的だが、視力の改善など有効性も調べる。iPS細胞の臨床研究はパーキンソン病や重症心不全なども控えており、今回の手術はiPS細胞を活用した再生医療実現への第一歩と位置づけられる。
臨床研究の対象は、悪化すると失明の恐れもある「滲出型(しんしゅつがた)加齢黄斑変性」。昨年8月、理研発生・再生科学総合研究センター(CDB)の高橋政代・プロジェクトリーダー(53)を中心に開始。目の網膜中心部(黄斑部)の傷ついた色素上皮細胞を摘出し、代わりにiPS細胞から作製したシート状の色素上皮細胞を移植する計画を進めていた。理研が、患者の皮膚細胞から作ったiPS細胞を使って細胞シートを作製し、先端医療センター病院が移植手術を担当した。
研究チームによると、投薬を中心とする現在の治療法では傷ついた網膜の修復はできず、今回の手術を受けた患者もこれまで治療を続けてきたが、症状が悪化していたという。
手術は、異常な血管ができて傷ついた色素上皮を専用の器具で取り除き、縦1.3ミリ、横3ミリの色素上皮細胞のシートで置き換えた。患者は3~7日後に退院し、定期的に検査を受ける。計6人の手術を計画しているが、2人目以降の時期は未定だ。
研究チームによると、色素上皮がiPS細胞治療の最初の臨床研究対象に選ばれたのは▽移植する細胞の数が少なくて済む▽がん化しにくい▽移植後の詳細な観察が可能--などが挙げられる。しかし、第1号だけに、iPS細胞や細胞シートの安全性の確認は慎重に行われ、患者の皮膚採取から細胞シート作製まで約10カ月かけた。
ノーベル医学生理学賞を受賞した山中伸弥・京都大iPS細胞研究所長(52)がiPS細胞を開発した当初は、がん遺伝子やウイルスを利用したためがん化が実用化への課題だった。今回は、山中所長らの最新の研究成果を生かし、がん遺伝子やウイルスを使わない方法を採用。マウスへの移植でがん化しないことも確かめた。
(毎日新聞)
http://mainichi.jp/select/news/20140913k0000m040001000c.html
iPS細胞の移植手術を実施 理研、世界で初めて
理化学研究所などのチームが12日、目の難病患者の皮膚から作製したiPS細胞(人工多能性幹細胞)を網膜の組織に分化させ、患者に移植する手術を実施したと発表した。iPS細胞を使った治療を人で試すのは世界初。手術の安全性を確認するのが目的で、計6人に実施する予定だ。同日夜に記者会見する。
理研発生・再生科学総合研究センター(CDB)の高橋政代プロジェクトリーダーを中心に研究を進め、先端医療振興財団(神戸市)の先端医療センター病院が手術を実施した。
手術を受けたのは、網膜の下の細胞が傷み、視力が落ちたり視界がゆがんだりする難病「加齢黄斑変性」の患者。兵庫県在住の70代の女性という。
(朝日新聞)
http://www.asahi.com/articles/ASG9C5QJKG9CPLBJ005.html
理研、目の難病にiPS細胞で世界初の手術
理化学研究所発生・再生科学総合研究センターと先端医療センター病院(ともに神戸市)は12日、iPS細胞(人工多能性幹細胞)から作った網膜細胞を、目の難病「加齢黄斑おうはん変性」の患者に移植する臨床研究の手術を行ったと発表した。
様々な組織や臓器の細胞に変化させられるiPS細胞を用いた治療は世界で初めて。
理研の高橋政代・プロジェクトリーダーらが移植用細胞の作製を、同病院の栗本康夫・眼科統括部長らが移植手術を担当した。
発表によると、患者は兵庫県在住の70歳代女性。数年前から症状の進行を食い止める治療を受けたが効果はなく、視力が徐々に低下していた。
手術計画では、全身麻酔をかけた後、目の表面に穴を開け、傷んだ網膜組織や、異常な血管を除去。その部分に、管状の特殊な器具を使って網膜細胞のシートを貼り付ける。手術は同病院でこの日午後1時40分頃に始まり、午後4時20分に終了した。
高橋氏らは患者の選定基準に従い、女性を第1例患者に選んだ。女性から採取した皮膚細胞に6種類の遺伝子を入れて、iPS細胞を作製。さらに特殊なたんぱく質を加えて約10か月かけて培養し、長さ3ミリ、幅1・3ミリの短冊状の細胞シートに加工した。
加齢黄斑変性は、網膜の中央にある「黄斑」を構成する細胞の一部が傷み、視界の中央がゆがんだり黒く欠けたりする病気。注射薬やレーザーで治療するが、完治はせず、患者によっては効果がないこともある。
(読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/science/20140912-OYT1T50105.html
世界初iPS手術、目の難病に実施 理研と先端医療財団
理化学研究所と先端医療振興財団(神戸市)は12日、神戸市にある同財団先端医療センター病院で、iPS細胞を使った世界初の臨床研究として目の難病患者に手術を実施した。京都大学の山中伸弥教授が世界に先駆けてマウスの細胞からiPS細胞を作り出したのが2006年。いよいよ医療応用に向けた動きが本格化する。
手術をしたのは「加齢黄斑変性」と呼ぶ難病を持つ兵庫県に住む70代の女性。この病気は年齢とともに視力が低下し、症状が進むと失明することもある。
理研の高橋政代プロジェクトリーダーを中心とする臨床研究で、細胞を移植する手術は同病院の栗本康夫・眼科統括部長が主導した。今回は移植した細胞が体内でがん化しないかなどの安全性の検証を主な目的としているが、症状改善にも期待を寄せている。
iPS細胞は病気やケガで損なわれた臓器などの機能回復を目指す再生医療の「切り札」といわれる。国も日本発の先端技術の実用化と普及を積極的に後押ししている。iPS細胞を作製した山中教授は12年にノーベル生理学・医学賞を受賞した。
今回の目の難病に続き、手足などが震えるパーキンソン病や、脊髄損傷などでもiPS細胞を治療に役立てようとする計画が進んでいる。
(日本経済新聞)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGG1200D_S4A910C1000000/
iPS、世界初の移植手術 目の難病患う70代女性に
理化学研究所と先端医療センター病院(神戸市)は12日、さまざまな細胞に成長できる人工多能性幹細胞(iPS細胞)から作った網膜の細胞を、目の難病「滲出型加齢黄斑変性」を患う兵庫県の70代女性に移植した。iPS細胞から作った細胞を人体に入れる手術は世界初。
がん化などの問題が起きないか確認するのが主な目的。京都大の山中伸弥教授が開発したiPS細胞を利用する再生医療の今後を占う手術として注目される。
理研などによると、患者の女性の皮膚から採った細胞に遺伝子を導入し、iPS細胞を作製。さらに目の網膜の色素上皮細胞に成長させ、移植用のシートを作った。
(47NEWS)
http://www.47news.jp/CN/201409/CN2014091201001410.html
iPS臨床、初の移植=目の難病患者に-安全性、効果検証・理研など
人工多能性幹細胞(iPS細胞)を用いた世界初の臨床研究を進めている理化学研究所発生・再生科学総合研究センター(神戸市)などのチームは12日、目の難病を患う兵庫県内の70代女性に、iPS細胞から作った網膜の細胞を移植する手術を行った。
臨床研究の主な目的は安全性の検証。移植した細胞が根付くか、がんになる危険がないかなどを4年かけて確認する。視力回復の効果があるかも合わせて調べる。
研究代表は高橋政代理研プロジェクトリーダー。手術は先端医療センター病院(同)で栗本康夫医師らが担当した。
移植の対象は、網膜に異常な血管が生えて視力が低下する「滲出(しんしゅつ)型加齢黄斑変性」の患者。薬など従来の治療では効果が得られない人を選んだ。
手術では、網膜のうち光を感じる「神経網膜」に栄養を送る「色素上皮」の傷んだ部分を除去。患者の皮膚から作ったiPS細胞を色素上皮の細胞に変え、シート状にしたものを代わりに移植する内容だ。
(時事ドットコム)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2014091200694
山中教授が全面支援=発表前に提供、ゲノム解析も-iPS臨床
iPS細胞を使った世界初の移植手術が実現するまでには、開発者でノーベル医学生理学賞を受賞した山中伸弥京都大教授の全面的な支援があった。
山中教授が所長を務める京大iPS細胞研究所は、iPS細胞を作る際に必要な環状DNA「プラスミド」を理研に提供した。理研の高橋政代プロジェクトリーダーは「論文の発表前から、前よりいいプラスミドができたら提供してもらってきた」と明かす。
さらに同研究所は、臨床手術で用いるiPS細胞の全遺伝情報(ゲノム)解析を実施。山中教授は今月、厚生労働省の審査委員会で解析結果を報告した。審査委は報告内容を検討し、移植実施に問題がないと判断、手術が可能になった。
高橋氏は山中教授がノーベル賞の受賞後、臨床研究をPRしてくれたと紹介。「常に精神的にも応援してもらっている」と話している。
(時事ドットコム)
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2014091200713
iPSから網膜細胞 世界初の移植手術実施 神戸
先端医療センター病院(神戸市中央区)と理化学研究所発生・再生科学総合研究センター(同)は12日午後、人工多能性幹細胞(iPS細胞)から網膜色素上皮細胞を作り、目の難病患者の網膜を再生させる臨床研究で、1例目の移植手術を実施したと発表した。iPS細胞から作った細胞が人の体に移植されるのは世界初。
患者は失明の恐れもある難病「滲出型加齢黄斑変性」で、兵庫県内の70代女性。同病院などは皮膚組織を採取してiPS細胞を作り、網膜色素上皮細胞に変化させシート状にして移植した。今後、腫瘍ができないかなどの安全性や、視野の改善などの効果を検証する。
(神戸新聞)
http://www.kobe-np.co.jp/news/iryou/201409/0007324118.shtml
世界初iPS細胞使った手術実施
神戸市にある理化学研究所などの研究チームは、iPS細胞を使って目の網膜の組織を再生し、病気で失われた患者の視力を回復させようという世界初の臨床研究の手術を、12日実施したと発表しました。
手術を受けたのは「加齢黄斑変性」という重い目の病気の70代の女性で京都大学の山中伸弥教授が開発したiPS細胞が、実際の患者の治療に使われた初めてのケースになります。
(NHKニュース)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140912/t10014562731000.html
世界初の手術 iPS細胞の網膜を移植
ノーベル賞を受賞した京都大学の山中伸弥教授が開発した万能細胞「iPS細胞」から作られた組織を患者に移植する、世界で初めての臨床手術が12日に神戸で行われた。
世界で初めての手術は、神戸の理化学研究所の隣にある病院の中で行われた。この手術は患者の目の網膜にiPS細胞から作られた組織を移植するもので、手術は無事に成功した。
患者は70代の女性で、片方の目の網膜組織に傷がつき、視力が急激に低下する「加齢黄斑変性」という難病を抱えている。
この手術は、目の再生医療の第一人者である理化学研究所の高橋政代プロジェクトリーダーらが計画してきた。高橋氏たちは、患者の皮膚からiPS細胞を作製。約10か月間培養して、シート状の網膜組織に変化させた。
シートを移植する手術は、眼科医をはじめ、8人ほどの医療チームが、3時間弱かけて行った。高橋氏は執刀はしていないが、手術室で見守ったという。順調にいけば、患者は2~3か月後に症状の改善が見られるようになる。現在、患者は麻酔から目覚め、容体は安定しているという。
iPS細胞を使った臨床研究は神経細胞や血小板など他の組織でも進められており、今回の1例目の治療の行方に注目されている。
(日テレNEWS24)
http://news24.jp/articles/2014/09/12/07259042.html
久しぶりにブログ更新したらえらいビッグニュースが飛び込んできました!!
ついに始まったようです。
今後に期待しつつ、冷静に見守りましょう。
2014-09-12 01:00:00
iPS細胞、より受精卵に近い状態に 英ケンブリッジ大が成功
テーマ:iPS細胞(基礎)英ケンブリッジ大の高島康弘研究員とオースティン・スミス教授らは、ヒトの胚性幹細胞(ES細胞)やiPS細胞を、より受精卵に近い状態の細胞に変えることに成功した。2つの遺伝子を操作して一時的に働きを高めた。効果的な不妊治療などにつながる成果と期待される。米科学誌セル(電子版)に12日、発表した。
高島研究員らはマウスのES細胞で働く2つの遺伝子「NANOG」と「KLF2」に着目。ヒトのES細胞やiPS細胞を遺伝子操作して、より受精卵に近い細胞を作った。
皮膚などの細胞からiPS細胞を作り、精子や卵子に成長させることができれば、不妊治療などに役立つ可能性もある。本当に生殖細胞ができたかどうかは受精させて確かめる必要がある。研究チームは今後、サルなどの霊長類でも同じ細胞が作れるかを試みる。
文部科学省が作った指針はヒトのiPS細胞から生殖細胞を作ることは認めているが、倫理的な観点から受精させる実験を禁じており、今後、議論を呼びそうだ。
高島研究員によると、作製した細胞はブタの体内でヒトの移植用臓器を作る技術の開発や、再生医療や生物学の実験に使うiPS細胞の質を高めることにもつながるという。
(日本経済新聞)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG1104J_S4A910C1CR0000/
高島さんおめでとうございます!
これでHanna、Huck-Hui、Jaenisch、AustinとHuman naiveの論文が出揃いましたね。
どれが真のNaiveか、はたまたどれでも駄目かは今後の研究次第。
キメラ実験ができないHumanでの実験はそろそろ頭打ちなのではないでしょうか。
ブタやサルでの実験がますます重要になってきますね。
私も頑張らなくては。。
プレスリリースはこちら。
論文はこちら。
Cell Volume 158, Issue 6, p1254–1269, 11 September 2014
Resetting Transcription Factor Control Circuitry toward Ground-State Pluripotency in Human
Yasuhiro Takashima, Ge Guo, Remco Loos, Jennifer Nichols, Gabriella Ficz, Felix Krueger, David Oxley, Fatima Santos, James Clarke, William Mansfield, Wolf Reik, Paul Bertone, Austin Smith
http://www.cell.com/cell/abstract/S0092-8674(14)01099-X
Current human pluripotent stem cells lack the transcription factor circuitry that governs the ground state of mouse embryonic stem cells (ESC). Here, we report that short-term expression of two components, NANOG and KLF2, is sufficient to ignite other elements of the network and reset the human pluripotent state. Inhibition of ERK and protein kinase C sustains a transgene-independent rewired state. Reset cells self-renew continuously without ERK signaling, are phenotypically stable, and are karyotypically intact. They differentiate in vitro and form teratomas in vivo. Metabolism is reprogrammed with activation of mitochondrial respiration as in ESC. DNA methylation is dramatically reduced and transcriptome state is globally realigned across multiple cell lines. Depletion of ground-state transcription factors, TFCP2L1 or KLF4, has marginal impact on conventional human pluripotent stem cells but collapses the reset state. These findings demonstrate feasibility of installing and propagating functional control circuitry for ground-state pluripotency in human cells.
高島研究員らはマウスのES細胞で働く2つの遺伝子「NANOG」と「KLF2」に着目。ヒトのES細胞やiPS細胞を遺伝子操作して、より受精卵に近い細胞を作った。
皮膚などの細胞からiPS細胞を作り、精子や卵子に成長させることができれば、不妊治療などに役立つ可能性もある。本当に生殖細胞ができたかどうかは受精させて確かめる必要がある。研究チームは今後、サルなどの霊長類でも同じ細胞が作れるかを試みる。
文部科学省が作った指針はヒトのiPS細胞から生殖細胞を作ることは認めているが、倫理的な観点から受精させる実験を禁じており、今後、議論を呼びそうだ。
高島研究員によると、作製した細胞はブタの体内でヒトの移植用臓器を作る技術の開発や、再生医療や生物学の実験に使うiPS細胞の質を高めることにもつながるという。
(日本経済新聞)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG1104J_S4A910C1CR0000/
高島さんおめでとうございます!
これでHanna、Huck-Hui、Jaenisch、AustinとHuman naiveの論文が出揃いましたね。
どれが真のNaiveか、はたまたどれでも駄目かは今後の研究次第。
キメラ実験ができないHumanでの実験はそろそろ頭打ちなのではないでしょうか。
ブタやサルでの実験がますます重要になってきますね。
私も頑張らなくては。。
プレスリリースはこちら。
論文はこちら。
Cell Volume 158, Issue 6, p1254–1269, 11 September 2014
Resetting Transcription Factor Control Circuitry toward Ground-State Pluripotency in Human
Yasuhiro Takashima, Ge Guo, Remco Loos, Jennifer Nichols, Gabriella Ficz, Felix Krueger, David Oxley, Fatima Santos, James Clarke, William Mansfield, Wolf Reik, Paul Bertone, Austin Smith
http://www.cell.com/cell/abstract/S0092-8674(14)01099-X
Current human pluripotent stem cells lack the transcription factor circuitry that governs the ground state of mouse embryonic stem cells (ESC). Here, we report that short-term expression of two components, NANOG and KLF2, is sufficient to ignite other elements of the network and reset the human pluripotent state. Inhibition of ERK and protein kinase C sustains a transgene-independent rewired state. Reset cells self-renew continuously without ERK signaling, are phenotypically stable, and are karyotypically intact. They differentiate in vitro and form teratomas in vivo. Metabolism is reprogrammed with activation of mitochondrial respiration as in ESC. DNA methylation is dramatically reduced and transcriptome state is globally realigned across multiple cell lines. Depletion of ground-state transcription factors, TFCP2L1 or KLF4, has marginal impact on conventional human pluripotent stem cells but collapses the reset state. These findings demonstrate feasibility of installing and propagating functional control circuitry for ground-state pluripotency in human cells.