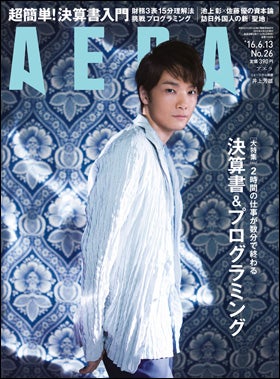不登校にならない方法をもっと早くに教えてほしかった
子どももママも未来に希望が持てる家庭療育
おうち療育アドバイザー浜田悦子です。
こんにちは^^
今日は、新小学4年生の
不登校気味のお子さんを持つ
ママのお話しをご紹介します。
**ここから**
診断のつかないグレーゾーンです。
1年生の頃から
周りと比べで幼いところがありましたが
マイペースのところが逆に
周りから可愛がられることにもつながっていました。
自分の好きなことには
よく集中して遊んでいたので
周りと同じようにできなくても
個性を伸ばしてあげたらいいと思っていました。
でも、2年生の後半あたりから
学校に行きたがらなくなり
3年生の後半では
ほとんど学校に行けなくなってしまいました。
1年先、2年先が
こんなに大変になるって、
もっと早く誰かに教えてほしかったです。
**ここまで**
きっとママは、
好きなことや長所を伸ばしてあげたくて
「成長を待つ」
というサポートで
見守ってこられたのかもしれませんね。
確かに、1年生の頃って
周りも幼い部分がありますし
授業中に話すのはもちろん、
立つ、泣く、ケンカする・・・
そんなことはよくある光景です。
周りと比べてできないことがあっても
マイペースなお子さんもいるし
慣れるのに時間がかかるお子さんだって
たくさんいます。
例えば、1年生の頃に
次の授業の準備の際、
先生の指示が聞き取れず
固まっているとします。
先生が気付いてくれて
「〇〇くん、準備しようね」
と個別に声をかけてくれたとしても、
何をどう準備すればいいのか
分からない子もいます。
また、
「周りのお友達を見て真似をしようね」
と声をかけたり
アドバイスをしたりすることがあるかもしれません。
でも、
他のお友達がみんな
同じ行動をしているとは限らないので
余計に混乱してしまうのです。
1.一斉指示が聞き取れない
2.先生が個別に指示を出す
3.周りを見ても分からない
これは、
脱走や固まるという
問題行動を引き起こしたり、
授業への取り組む姿勢を低下させ
授業つまらない・・・
分からない・・・
という、学習の問題行動へも
つながってしまいます。
まだ1年生だし、
難しいことやらないよね?
カンタンなことだし、
何とかやっていけるでしょ?
と先生から特に報告がないと
「なんとか頑張っている」
と思いますよね。
多少できないことには目をつむり
子どもの得意を伸ばしてあげようと
広い心で見守っているママもいるかもしれません。
2年生の後半から
行き渋りがはじまったということは
2年生になり、
先生やお友達が変わったという理由だけではなく、
1年生のころから、不快や苦痛やストレスを
感じているお子さんも少なくありません。
「成長を待つ」は
重要な大切なサポートだと
わたしもそう思っています。
ただ、グレーゾーンの気質があるならば
お子さんが
自分ができないことや
困っていることに対して
見守ってほしいと感じているかどうか?
は、イコールではない時があります。
分からないことがあっても
「分からない」と
言えないことがあったり、
「教えて」と言えないことがあります。
「マイペースな子」として
あたたかく見守られていることが
本人にはストレスに感じていることもあります。

行き渋りや不登校ぎみのお子さんへの対処は、
早ければ早いほど軌道修正がラクになります。
「うちの子も学校へ行けてない・・・」
と一人で抱え、自分を責めて、
将来の心配をしていませんか?
「どうしてもっと早くに対処しなかったの?」
と責められるのが辛いと感じたり、
相談することで、
「グレーゾーンじゃなくて、発達障害ですね」
と認定されてしまうんじゃないか?と
不安で相談できないのかもしれませんね。
でももし、
お子さんもママも
困っていることがあったら
早めに対処していきましょうね。
発達障害やグレーゾーンがあっても
学校に元気に通う!
みんなと一緒に活動できる!
自分の興味や長所を伸ばして力を発揮できる!
そんな子育ては可能です。
4月22日から始まる
「おうち療育プログラム」では、
行き渋りや不登校のお子さんをお持ちの
お母さんも受講可能です。
子育てで問題を抱えている時、
母親として情けない・・・
他の人と一緒に受講するなんて恥ずかしい
と感じて受講をためらってしまう方もいると思います。
私が講座の中で大切にしているのは、
どんなことがあっても受容するという姿勢です。
受容する力は、
発達障害児の子育てでは
一番必要な資質だと思っています。
同じような悩みを抱えるお母さん同士、
悩みを共有し、共感し、
受容しながら、一緒に成長することで
お子さんもどんどん成長していきます。
あなたにとって、
あったかな心強い場となって、
前向きな気持ちで子育てできるように
お手伝いしますね!
4月22日開催の
詳細はこちらです。
このようなQ&Aの記事が読みたい方は
ぜひ、メルマガにご登録してみてくださいね!
**掲載していただきました!!**
●毎日新聞デジタル(2022年2月13日)
突然の休校・休園 親子でどう過ごす?コロナ禍で必要なメンタルケア
●中日新聞(2021年12月28日)
「この人」発達障害・グレーゾーンの子どもと家族を支える
●朝日新聞デジタル(2021年10月1日)
朝日新聞(名古屋版 夕刊2021年12月15日):
グレーゾーン?発達障害?その時親親は…?2千人と関わった指導員の視点
●毎日新聞(2021年8月31日):
新学期の「登校しぶり」 ヘルプサイン出しづらい子への向き合い方
(ひよこクラブ:2018年3月号)
(執筆・監修)
ユーキャン 子ども発達障がい支援アドバイザー講座
神奈川、横浜、川崎、東京、千葉、埼玉、
茨城、栃木、群馬、23区、青葉区、静岡、
浜松、山梨、仙台、大阪、神戸、京都、
名古屋、石川、和歌山、岡山、福岡、
全国からご相談いただいております。
発達障害、グレーゾーン、発達の遅れ、
発達遅滞、知的障害、療育、家庭療育、
癇癪、パニック、こだわり、きょうだい喧嘩、
他害、暴言、宿題の悩み、身支度、着替え、
登園拒否、登校拒否、不登校、友達関係、
おまかせください。
(AERA:2016年6月号)