キンドル本作りに熱中していたら
ブログを更新するの忘れてたよ
KDP(キンドル・ダイレクト・パブリッシング)の『プリーズ・リクエスト・ジャズ50』が発売になりました。アマゾンから電子書籍のジャズ本を出したよ!つーことです。
ePubのプログラミングに悪戦苦闘。3月13日にリリースはしたのですが、なかなかiOS対応( iPad、iPod Touch、iPhone)にならなくてプロモーションが出来ないままに2週間も経ってしまいました。
データを作り直して再アップロード、本日やっとiOS対応になったので、さあっ!販売開始です。

Please Request Jazz 50 Vol.1 tommyTDO(TDO books)定価:298円
まぁ、これでオレも「ジャズ評論家」になったということだね(笑)。てか、本を出せば誰でも評論家つー世の中の雰囲気もどうかと思うけどね。素人との区切りがないから、今までは本を出す事が専門家のパスポート、証明書みたいになっていたんだよね。オレがジャズ本を出したのは事実だから、これをもってジャズ評論家というのも仕方がない。かなりヘボイジャズ評論家ということになった(笑)。いつだって好きに、いろんな本が出せるのだからいいことだ。
実際は、「キンドル作家」と言って欲しいね。そっちの方がめざしているいるものだからさ。
プリーズ・リクエスト・ジャズ50_1 (TDObooks)/tommyTDO
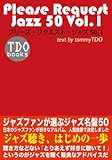
¥298
Amazon.co.jp
ブログを更新するの忘れてたよ
KDP(キンドル・ダイレクト・パブリッシング)の『プリーズ・リクエスト・ジャズ50』が発売になりました。アマゾンから電子書籍のジャズ本を出したよ!つーことです。
ePubのプログラミングに悪戦苦闘。3月13日にリリースはしたのですが、なかなかiOS対応( iPad、iPod Touch、iPhone)にならなくてプロモーションが出来ないままに2週間も経ってしまいました。
データを作り直して再アップロード、本日やっとiOS対応になったので、さあっ!販売開始です。

Please Request Jazz 50 Vol.1 tommyTDO(TDO books)定価:298円
まぁ、これでオレも「ジャズ評論家」になったということだね(笑)。てか、本を出せば誰でも評論家つー世の中の雰囲気もどうかと思うけどね。素人との区切りがないから、今までは本を出す事が専門家のパスポート、証明書みたいになっていたんだよね。オレがジャズ本を出したのは事実だから、これをもってジャズ評論家というのも仕方がない。かなりヘボイジャズ評論家ということになった(笑)。いつだって好きに、いろんな本が出せるのだからいいことだ。
実際は、「キンドル作家」と言って欲しいね。そっちの方がめざしているいるものだからさ。
プリーズ・リクエスト・ジャズ50_1 (TDObooks)/tommyTDO
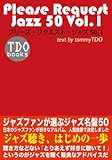
¥298
Amazon.co.jp











