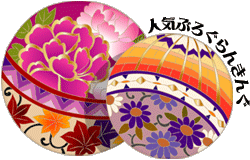うさ吉…。
只今、転職を模索中です。
転職するってことは、いまの職場や仕事から離れるってことなのですが…
ちょっと寂しい気がしてます。
かなり好きな仕事だったのですけどね、
先立つ物がなくては、生活していけませんので…
しょうがないです(⌒-⌒; )
せっかく、松本検定、マイスタークラスを取ったのにねぇ( ;´Д`)
松本検定とは。
松本市いろいろを知ってもらおうという検定でして。
ボランティアガイドさんは、コレを持っていないとなれないという資格です(・ω・)ノ
資格取得者の特典は、
取得時から2年間、松本市内の博物館入場無料 と、いうもの。
うさ吉は、仕事でガイドをしているので、松本検定に受かってなくてもガイドできたのですが、
せっかくなので、昨年・今年と受けまして、ようやく取得となりました(≧∇≦)
その勉強の中で知った民話をご紹介します( ´ ▽ ` )ノ
雑炊橋
むかしむかし。
梓川(あずさがわ)と言う川には橋がかかっておらず、川をへだてた村と村は、すぐ近くなのに、行き来する事が出来ませんでした。
清兵衛(せいべい)とおせつも、そんな子どもたちで。
二人は毎日の様に川をへだてては大声で叫び合いました。
そして月日は流れて、やがて二人は十六才になりました。
ある日の事、雨上がりの空に大きな美しい虹がかかりました。
それがあまりにもきれいだったので、おせつは家を飛び出すと夢中で虹を追いかけました。
そして谷沿いの道を二里(約八㎞)ほど下ったところにある舟の渡し場で、
おせつは同じ様に虹を追いかけてきた清兵衛と出会ったのです。
清兵衛はにっこり笑うと、舟で川を渡っておせつのところまで来ました。
「ああ、やっとの事で会えたなあ」
「うん。谷に橋があれば、いつでも会えるのにね」
二人は時の立つのも忘れて語り合い、そして二人でうんと働いて、いつか谷に橋をかけようと約束したのです。
「きっと、橋をかけようね」
「ああ、きっとだ」
それからというもの、二人は懸命に働きました。
清兵衛は山にこもると一生懸命に木を切り倒し、
おせつは米のご飯をやめて安いアワに草花を入れただけの粗末な雑炊をすすり、夜遅くまで機(はた)を織り続けました。
こうして二人が約束をしてから九年後。
とうとう清兵衛が腕の立つ大工を連れて村に帰って来たのです。
おせつはこの知らせを聞いて、涙を流して喜びました。
今まで雑炊をすすって機を織って貯めたお金が、やっと役に立つのです。
両方の村人たちも工事に協力して、それから半年後に立派な橋が出来上がりました。
おかげで二つの村は、いつでも行き来が出来る様になりました。
また橋が出来ると、この橋を渡って山を越える飛騨(ひだ)の道も開かれて、小さな村はいつの間にか宿場(しゅくば)として栄えるようになりました。
人々はこの橋を、『雑炊橋』と呼びました。
そして、その渡りぞめには、両岸からおせつと清兵衛を形どった人形を車にのせて引き渡す行事が伝えられているのです。
ーーー・ーーー・ーーー
まんが日本昔ばなしでも紹介されていたそうです(・ω・)ノ
『雑仕橋』というタイトルで、紹介されていました(・ω・)ノ
江戸時代、松本の高見書店に住んでいた十返舎一九は、
この伝承を取材して『雜食橋由來』(1819年(文政2年))という絵入り草子本の中に取り入れたそうです。
結構、有名なお話だったのです…(⌒-⌒; )
なんで知らなかったんだろう?