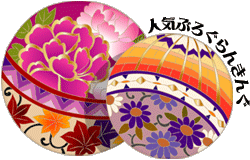只今、西遊記のモデルとなった玄奘三蔵の旅をご紹介しております(・ω・)ノ
陳褘(チンイ)こと、玄奘三蔵(602~664)。
なんと!
色白で。
美男子で、
秀才。
ただし、大柄…
…だったそうです( ̄▽ ̄)
13才で出家し、仏教を学びましたが満足できず、
国禁を犯して27才でインド留学へと向かいます。
それは命がけの取経の旅でした。
それは命がけの取経の旅でした。
ゴビ砂漠、タクラマカン砂漠、パミール高原、カラコルム峠を越え、やっとの思いでインドの仏教大学ナーランダに到着。
長安出発のときにいた40人の同行者は、途中の猛獣・山崩れ・急流などで死者が続出し、
長安出発のときにいた40人の同行者は、途中の猛獣・山崩れ・急流などで死者が続出し、
偉人といわれる人には色々な伝説が残っていますが、玄奘にも、もちろん! あります。
玄奘三蔵と般若心経
玄奘三蔵が弟子たちを連れて長安をたった、旅の始めの頃。
ある寺に立ち寄った時のことでした。
インドから来た老僧がハンセン病で苦しんでいました。
寺の者や、玄奘の弟子たちは、病僧の姿と、
自分も移るのではないかという恐怖のために、皆逃げだし。
老僧は1人で病床に伏せていました。
玄奘は病僧の苦しむ姿を大変切なく思い、手厚く看病しました。
薬をすすめ、食事など一切の世話をしました。
このインド僧はお礼にと、1巻の経典を玄奘に授けました。
サンスクリット語で書かれていたため、内容は全くわかりませんでしたが、
玄奘は大層喜んで、この経典を道中のお守りとし、懐にしまい、大切にしました。
その後、旅の途中の難儀で、弟子たちの全てを亡くし、玄奘が独りでインドのナーランダ寺に着くと、
玄奘が看病した病僧がそこにいました。
驚く玄奘にその僧は、
『よくぞ、たどり着いた。
われは観世音菩薩なり』
と微笑み告げて、空に消え去ったそうです。
玄奘帰国後、この経典を漢訳したのが現在の「般若心経」です。
長い旅の中でたくさんの苦難を乗り越え。
玄奘三蔵ただ一人が生き残ってインドにたどり着いたのは、懐に入れていた般若心経のおかげと言われており。
般若心経が、旅行のお守りのお経ともいわれる所以です。
ーーー・ーーー・ーーー
ハンセン病は日本でいうライ病のことです。
今は、感染力が弱い事や、感染源や感染経路がわかり、治療法や治療薬も確立しています。
しかし、六世紀だけでなく、ごく最近まで大変に恐れられ、差別の対象となっていた病気でした。
重篤な状態になると、皮膚がかなり変化し、恐ろしい面相になる事があったからです。
また、重篤な状態になると、感染する確率が高くなるのです。
しかも、痛くも痒くもないのに、皮膚がどんどん変化して行き、
死亡率7%という低さのため、異形な姿のまま、生き続けることになるので…
なので、皆、ハンセン病を恐れていました。
そんな病人を、心優しい聖人・玄奘三蔵が放っておけるはずないです。
そして、彼が介抱した病僧は実は観音菩薩。
世界中に似た話はありますけど、なんだかとても、ありがたい感じがします(^ ^)
でも、般若心経が旅行のお守りとは、知りませんでした。
勉強になりました(・ω・)ノ
つづく。
いつもありがとうございます(≧∇≦)