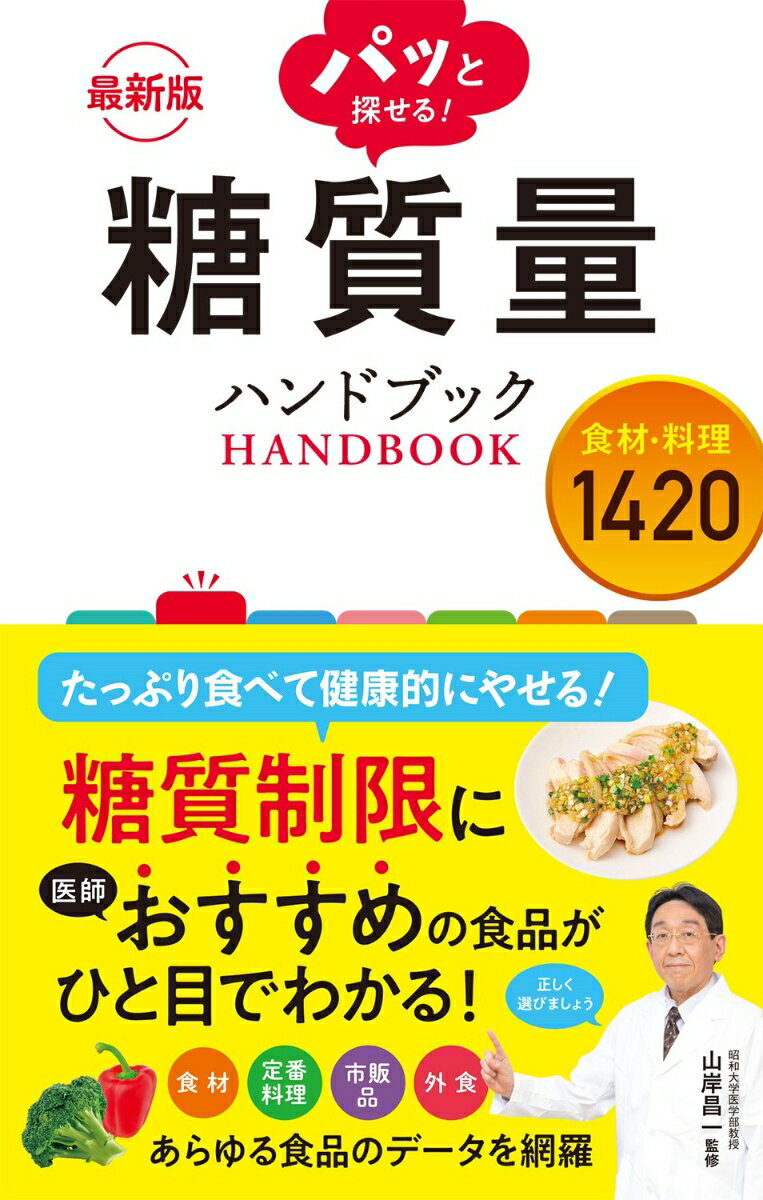夫が退院
管理入院をしていた夫が昨日帰ってきました。
急病による入院ではないため、さっそく今日から仕事に行っています。
10日間も休んじゃったから今月はもうあんまり休みもらえないんじゃないか…![]()
そんなわけで、入院中はいろいろ検査したり、管理栄養士さんによる食事指導があったわけですが、自宅でも糖質を計算する必要が![]()
インシュリンを打つ上で、食事に含まれる糖質を把握して、その時の血糖値によって何単位打つか決めるんだって。
市販の食品に書かれているものを参考にしたり、そういう数値が書かれているレシピ本を参考にしたりと、それはそれは面倒くさい![]()
結局、作る人がそういう計算をある程度しないと、見た目での計算は無理だからさ…
ま、でもとりあえず、今は仕事もなくて暇だから、慣れるまでの間はレシピ本とにらめっこしながら食事メニューを決めようかと。
オリジナルで作ると計算が面倒くさいので、レシピ本見ながらやろうと思います。
なので、自分の記録のためと続けるために、ブログにも残してみようと思います。
11/17の夜ごはん
★鶏しゅうまい(1個15g✕7)
★カツオたたき(スライス玉ねぎのせ5切れ)
★ブロッコリーのにんにく蒸し(3個)
★すまし汁(180cc)
★ご飯(発芽押麦入り)200g
★糖質オフの発泡酒350ml1缶
〈合計糖質量→約102g〉
糖質量は素人計算なので、正確ではないと思います。
病院では特に体を動かすわけではないので、3食で1600キロカロリーだったそうです。
ご飯の量は150gだったそうですが、全然足りなかったと言ってました。
なので、帰宅後はちょっと増やしてくれとのことで200gにしましたが、おかずがかなりボリューミーだったので、150gでもイケるかもとのこと。
ダイエット目的ではないので全く糖質オフというものではなく、あくまで糖質量を計算してインシュリンの量を決めて血糖値をコントロールするというものなのですが、病院と変わらない糖質量(1食100g前後)にできました。
ちなみに、鶏しゅうまいは〈鶏ひき肉・木綿豆腐・玉ねぎ・人参・ぶなしめじ〉で豆腐や野菜でかさ増し。
すまし汁は、〈ぶなしめじ・人参・絹豆腐・とき卵〉と具だくさんに。
ブロッコリーのにんにく蒸しは、香味ペースト少々と水少量をフライパンで蒸しただけ。
ご飯は、3合の白米に対して50gの発芽押麦を混ぜて炊いたもの。
写真撮るの忘れてしまって…
夫のおかずはワンプレートで別盛りするので、今度から撮ってもらいます。
11/18の朝ごはん
★鶏しゅうまい(前日の残り)2個
★すまし汁(前日の残り)180cc
★納豆1パック
★ご飯(発芽押麦入り)200g
★牛乳200ml
〈合計糖質量→約88g〉
前日の残りものを食べたので、計算が楽でした。
そして、夫セルフだったため、またもや写真なしです。
11/18お昼ごはん(お弁当)
★ご飯200g(発芽押麦入り)
★豚肉にんにく味噌焼き(ぶなしめじ入り)
★卵焼き(あおさ入り)
★ひじき煮(市販品)
★ブロッコリーにんにく蒸し
★赤ウインナー
〈合計糖質量→約83.5g〉
作業があるので、間食用に塩むすび(100g)とバナナも持たせました。
今までご飯の量、結構盛り盛りだったんだな〜と思いました。
200g計量して入れてみると、だいぶ少なく感じました。
ちなみに、豚肉のにんにく味噌焼きは、味噌とにんにくと焼鳥のたれを混ぜたもので豚ロースに下味漬けてから焼きました。
残ったお肉を食べたらおいしかった![]()
お昼にまた焼いて食べようかな?
ちなみに、夫がいない時の食事は糖質量の計算はいたしません![]()
が、多少意識はしながら…あわよくば自分のダイエットにも役立てばラッキー♡くらいな。
一応、自分が普段食べているご飯の量を計ってみたら100g弱だったので、ご飯の量を調整しながらおかずメインで食べたらいい感じで糖質オフできそうだなーと思いました。
そうそう、糖質量を調べるにはそういうのが数値化されているハンドブックやレシピ本か必要になるため、昨日の退院後に夫と本屋に行って買ったんですよね。
で、私も頑張ろうと思って1冊レシピ本を買ったわけですよ。
そしたらですよ…
家に帰ってから、普段あまり見ない本棚を久々に見てみたら…
同じレシピ本が既にあったという…![]()
久々にやらかしました、同じ本を買う失態![]()
気合い入りすぎか![]()
というわけで、また夜ごはんのメニューをこれから考えたいと思います。
あぁ、面倒くさいよぅ![]()
血糖コントロールのために準備したもの
![]() 料理をする私が参考にする本
料理をする私が参考にする本
![]() 外食が多い夫が参考にする本(栄養士さんにすすめられた本)
外食が多い夫が参考にする本(栄養士さんにすすめられた本)