ゆめな国のお話し →その3
古代の日本(ヤマト)の隅すみ」には、「ドアと玄関」→「戸と関」がありました。
むつ・陸奥(道のおく)には、八戸、二戸⇔大陸への扉には、佐賀関→かまど関→下関がありました。
─━─ ━─扉─━
━─扉─━ ─━─
─━─
北のドアを抜けた源氏の源義経がチンギス・ハーンとなり?西の玄関から![]() 平家の北条氏を追い詰めた?という人もいます。
平家の北条氏を追い詰めた?という人もいます。
亡ぼしたはづの白旗の地に赤旗⇔滅ぼしたはずの平家の地に源氏→南朝の落人?とても不思議な「酸化と還元」があるように見えた・・
その扉の向こうには「外地」があり 「内地」には、北の佐伯部・蝦夷と南の久米部・隼人という「内部かつ外部」の「おに」という人々は⇔中央→畿内に住んでいました。
「内地」には、北の佐伯部・蝦夷と南の久米部・隼人という「内部かつ外部」の「おに」という人々は⇔中央→畿内に住んでいました。
その間にいたのは、空海(佐伯真魚)の父親でありました。
http://ameblo.jp/yuukata/entry-11288485860.html
籠目(カゴメ)かごめ後ろの正面はだれ?の後ろには、醤油→「しお」がありました。
素麺、うどん、ラーメン、餃子にシウマイ、メリケン粉・・
海水→かんすい←淡水
塩(しお)の道がありました。
「おに」は「外地」から「内地」に「竹」を植えていました。そして、もともと日本になかった「竹」は繁殖しました。後のち「かぐや姫」が登場します。
竹細工職人には「おに」という人々が多くいました。
日本海・若狭の塩田⇔湊川には「おに」の「おや分」がいた⇔瀬戸内海の塩![]() 瀬戸内海のような日本海は重要な場所でありました。それに関わる人々が存在しておりました。
瀬戸内海のような日本海は重要な場所でありました。それに関わる人々が存在しておりました。
共通点は南朝と塩(しお)?の気がしました。
南朝→赤穂藩の浅野氏は、白い塩を作っていました⇔北朝→吉良氏はどうやって?![]() ?とたずねました。当時、鉄の釜で作る塩(しお)は酸化鉄により赤みをおびていました。
?とたずねました。当時、鉄の釜で作る塩(しお)は酸化鉄により赤みをおびていました。
おそらく、それは深く関係している・・
他にも「扉」があったのか?
─━─ ━─扉─━
━─扉─━ ─━─
─━─
↓↓その扉の向こうには↓↓
![]() …―…―
…―…―![]() →
→
あの時、http://ameblo.jp/yuukata/entry-11022081424.html
徐福は、ワン・ワールド体制から逃げてきました。白黒はっきりさせる「秦」国はわずか15年で亡びました。
聖徳太子は日本人ではなく⇔倭人でありました。白黒思想ではなく⇔シマウマ信仰のような完成させることのできない呪術的な祭祀国家の律令制にしていました。それを造ることは壊す事でありました→白黒はっきりさせる時代には、聖徳太子不信仰が生まれました。けれども、イルミネイトの一員になりたい人々は、聖徳太子の敷いた「律令制」を完成させようとしている→
漢民族は土間住まいで⇔初期・越人の住まいは高床家屋で、履物を外していました。稲作をする彼らは、天候を気にしており、祈祷などを行い「祭祀国家」とも結びつきます。
その人々は、船の家に住んでいたり、鵜飼いの魚釣りをしていました。水深が深くなると、海女(あま)のように人が潜るのである。
越人(えつひと)は入れ墨をしていた←と魏志倭人伝には記されている。
彼らは一時期、朝鮮半島の南→任那に住んでいた。

日本史探訪〈3〉律令体制と歌びとたち (角川文庫)/角川書店
しばらくすると、騎馬民族が北方よりやってきました。
ここ最近、否定的な意見の多い→江上波お教授の「騎馬民族説」であるが⇔「征服王朝」と「祭祀王朝」は、重ね合わさり→「馬と船」は、やってきたかもしれない‥
あまり高麗(コマ)の存在は、日本では知られていない。しかし地名には、多く見られる。
東京都狛江市、狛犬もそうだという人もいます。
高麗(コマ)は時代によって、中国のような明⇔清⇔モンゴルのような元⇔朝鮮⇔満州など、領土面積、民族は大きく代替したり消えて現れていました。
馬、牛、鉄、塩、牧、そして「船」は付随しておりました。
韓人や倭人とは、華南の「越」人である。主に長江河口域に住み、稲作と漁撈を生業(なりわい)とし、高床式の住居に住む「越」という人々でした。
古代の日本海・北陸地方を「越の国」という。そこには、「うら玄関」があったのだという。
江戸時代には越智越人という歌人がいました。越智氏は、日本海、瀬戸内海、太平洋、かなり広い範囲に登場します。
古代と中世⇔日本海と瀬戸内海の「扉」がありました。
─━─ ━─扉─━
━─扉─━ ─━─
─━─
南北朝時代、南朝の楠木正成は、兵庫の湊川を重要視していました。日本海と瀬戸内海には「塩の道」があった。その道は、日本列島に多く、非常に広い範囲を巡っていました。「交通の要衝」は、太平洋、東西南北、後ろには「おに」という人々がいました。楠木正成はその「おや分」でありました。思想的には「何か」をもっていました。
彼は、北条氏に対して「寝返った事」があるので、おそれていました。しかし、おもしろいことに北条市の伊予守と左馬頭という官職の組み合わせとも関わっていました。
左馬頭は院の厩(うまや)の別当を兼ねていて淀川沿いの「牧」を抑えており、伊予守は瀬戸内海の入口を抑えていました![]() この両方の官職を兼ねると瀬戸内海の入口の淀川から出口まで抑えることでありました。
この両方の官職を兼ねると瀬戸内海の入口の淀川から出口まで抑えることでありました。
古代の「記紀」には伊予の二島という海賊の島が登場し、藤原純友の乱、近代では西園寺氏が城を構えていた宇和町とも通じています。
続・日本の歴史をよみなおす (ちくまプリマーブックス)/筑摩書房
越智氏、河野家、宇都宮氏など源平戦と南北朝を頻繁に代替していました。越智氏から→河野家→北条氏、伊藤博文、一遍上人など、日本列島を広く回っていました。古代には額田王もいました。
空海を山に案内した狩場太郎という「犬飼部」もおりました。品部という職能組織には、鵜飼部とか、鳥飼部、服織部(はとりべ)は機織り、錦織部は縫いの?弓削は弓を作る。ト部は占い、矢作部は矢作り、玉造など、瀬戸内海にはその時の名残りがあるようです。

西園寺家は、山の後ろ→山背⇔宇佐の秦氏(はたうじ)を通して→東西南北、山と海、馬、牛、鉄、塩、牧、そして「船」は、阿多隼人とも通じていました。
![]() …―…―
…―…―![]() →
→
はなしはもどって、
東夷とよばれた夏人は、長江流域の東南アジア系の原住民であったという。会稽(カイケイ)山が越人の聖地で、福建省、広東省、広西省からベトナムにかけて活動していた越人が夏人の末裔を自称しているという。
前333年
「越」国が楚に亡ぼされると⇔越人が散らばり→前219年に琅邪(ろうや)を出発したという徐福伝説がある。のち燕人が朝鮮半島に進出する前に「越」人が日本列島に到着したという。

日本に渡来した徐福船団の出港地は、山東半島の琅邪(ろうや)だという。
前219年に、徐福は、亡命のような引越し計画をしていた。当時の琅邪には、楚人・越人・呉人という長江流域出身の住民が多く、彼等は秦帝国の圧政から逃れたいと思っていた。
「越」はBC473に「呉」を破り、「越」は山東半島の西南・邪琅(ろうや)に遷都した⇔しかし、BC333年頃、「越」は西方の「楚」に亡ぼされた。
琅邪は楚の領土となった。さらに、前223年に、「楚」も「秦」に亡ぼされた。

…―…―→
紀元前450年
春秋時代の呉越戦争で「呉」が亡びた同時期に 大規模な水田跡が九州で見つかる。長江文明の象徴である水耕稲作文化の揚子江一帯の呉人が前5世紀頃、「呉」滅亡とともに大挙して日本列島に漂着していたという説もある。
大規模な水田跡が九州で見つかる。長江文明の象徴である水耕稲作文化の揚子江一帯の呉人が前5世紀頃、「呉」滅亡とともに大挙して日本列島に漂着していたという説もある。
…―…―→
よつて、楚人は「越」人であり呉人でもありました→
徐福は一族と共に筑紫に渡来する→
琅邪国(現・山東省沂南県)→その頃、山東省は「斉」であり?徐福の出身地である琅邪の西北にある夏家村の伝承によると、徐福の妻は「夏」姓であり、この村の出身だという。

徐福船団は、楚・越・呉を主体に、斉・夏も含まれていたとおもう。つまり?徐福船団の主力は、楚人のような斉人→秦人(はたびと)だという。
「秦国」誕生の前後⇔崩壊の前後にも、日本にやってきました。
秦人(はたびと)⇔漢人(あやひと)という人々は、斉・夏・楚・越・呉も含まれていたはづである。
またそれ以前、日本に住んでいた人々と融合していました。
魏志倭人伝には、その人々は「倭人」と記されていた。
越人は「うら玄関」からやってきた?の?
- 塩の道 (講談社学術文庫 (677))/講談社

- ¥840
- Amazon.co.jp
- 古代日本の塩/雄山閣

- ¥3,990
- Amazon.co.jp
- 日本の地名 (岩波新書)/岩波書店
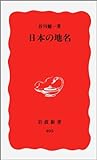
- ¥798
- Amazon.co.jp




