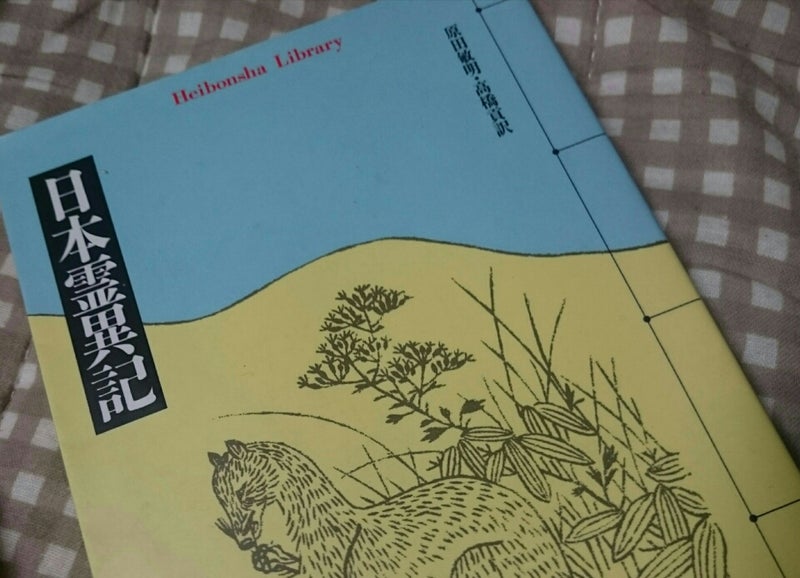
平安時代に成立した、現存する日本最古の説話集『日本霊異記』。正式には『日本国現報善悪霊異記』という名前で、仏教思想の影響を受けた因果応報的な説話など116の説話がおさめられています。
作者である薬師寺の僧・景戒は、紀伊国出身の人物とされています。説話の舞台は関東から九州まで多岐にわたりますが、作者の出自からか、紀伊国を舞台にした説話が最も多いそうです。
今回はこの『日本霊異記』におさめられている、日高が舞台の2つの説話をご紹介します。(出典:原田敏明・高橋貢 訳『日本霊異記』平凡社ライブラリー)
◆信じる者は救われる

日高川の河口に馬養と祖父麿という二人の男がいました。二人は漁師に雇われており、網を引いて魚をとっていましたが、昼夜の別なくこき使われ、辛い思いをしていました。ある日嵐が訪れ、河口には水があふれ、たくさんの木が流れていきました。馬養と祖父麿は雇い主から、流れ出た木を取りに行くよう言われます。二人はいかだを組み上げ、大荒れの川に漕ぎ出しました。
しかし流れは荒く、いかだはばらばらになってしまいます。二人は必死に木片にしがみつきますが、そのまま海まで流されてしまいました。二人はただ、「南無釈迦牟尼仏、この災難を救いたまえ」ととなえるしかありませんでした。
数日後、二人は淡路国(淡路島)に流れ着きます。事情を知った土地の人は同情し、二人の世話をしてくれました。祖父麿は、「故郷に戻っても、雇い主にこきつかわれて、殺生をやめられないだろう」と思い、淡路にとどまって僧になりました。馬養はしばらく淡路にとどまり、故郷へと戻ります。馬養の妻は、思いがけない夫の帰宅に大いに驚きました。妻子との再会を喜んだ馬養は、その後は俗世間を避け、仏道を修行したそうです。
海上での災難は多いとはいえ、二人が助かり、生きながらえることができたのは本当に釈迦如来のおかげであり、二人の信心によるものでしょう。
*『大海に漂流し、つつしんで釈迦の名をとなえ、助かった話(下巻第二十五)』
◆過ちより徳を求めよ

日高郡の「別の里」という所に、生まれつき性格の悪い紀吉足という人がいました。ある日吉足は、伊勢の沙弥という自度僧(国が認めた僧ではなく、私的に出家した僧)と出会います。彼は、あちこちを回ってお経をとなえる代わりに食物を求めていました。
吉足は食物を与えるどころか、沙弥が集めた稲をまき散らし、衣服をはぎ取って殴りかかります。沙弥は近くの寺(道成寺? )に逃げ込みましたが、吉足はそれを捕まえ、「経をとなえて、おれを呪文でしばってみろ」と詰め寄りました。沙弥は仕方なく、お経を一度唱えて逃げます。するとその直後、吉足は地面に倒れ込み、そのまま亡くなってしまいました。
身なりがいやしいからといって、はっきりとした過ちのない者の欠点を探すようなことをしてはいけなません。欠点を探せば、どんなにすぐれた者でも悪口を言われるような欠点はあります。逆に徳を探せば、誰でもほめられるような徳はあるのです。
*『いやしい僧の乞食を打って、現に急に悪死の報いを得た話(下巻第三十三)』
◆日高と『日本霊異記』
日高が舞台の2つの説話、いかがだったでしょうか。少し日高の人々が悪く書かれすぎな気がしますが、1000年以上前の人々の考え方がよく分かる説話だと思います。
皆さんもぜひ一度、『日本霊異記』を手に取ってみてください。
―――――――――――――――――――――――
ランキングに参加しています!
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
和歌山県ランキングへ