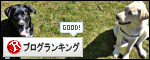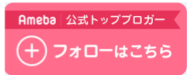子供の頃中華料理で一番好きだったのが酢豚。
が、甘すぎると家族全員が嫌い、食卓には八宝菜が登場する頻度の方が高かった。
反対に私はその八宝菜が苦手な料理の1つでした。
滅多に作ってもらえないので、外で中華を食べる時は必ず酢豚を選んでいました。
今じゃ昔とは全く逆で、甘くない八宝菜の方が食べやすくて好き。
でも、たまに食べたくなる酢豚。
しかも炒飯にたっぷりぶっかけて。
イギリスには中華やインディアンのテイクアウェイ(お持ち帰り)ショップが至る所にあります。
日本で言うならほっともっとみたいな感じのお店。
イギリスに留学し、初めて中華のテイクアウェイショップで買った料理も、酢豚でした。
その酢豚が衝撃的でした!
日本の酢豚のように野菜やパイナップルが入っておらず、フリッター衣の豚のみで、ソースは別の容器に入っていてディップして食べるスタイル。
「こんな感じの酢豚」なんですが、これが最高に美味しかった!
なんでもすぐにはまっちゃう私は、その酢豚にもはまりにはまり、足しげくその店に通っていました。
でも、イギリスでもその店だけでした。
他の店では日本の酢豚と同じような作り方。
一時期自分で自宅再現しようと思い試みましたが、やっぱ家庭のコンロではあのサクサクフリッター衣は実現できず、ソースをつけると衣がべちゃっとなって美味しくないのであきらめた。
こうして類似の酢豚のレシピを見つけたので、次回作る時はそのレシピを試してみようかなと思っています。
昨日の酢豚に使った豚ヒレ300g強は、ゴロゴロ大きく切り分け、塩麹、酒各大さじ1、チューブニンニクと生姜、ブラックペッパーで下味をつけました。
薄力粉と片栗粉を半々に合わせた粉をしっかりまぶし、カラッと油で揚げています。
ソースのレシピは「こちら」です。
ただ、毎回作る度もっとソースを多めにしておいたら良かったと思うので、昨日は1.5倍に増量し、オイスターソースも小さじ2ほど使用。
そして、私だけじゃなく殆どの人がするように、いつもは水溶き片栗粉でとろみをつけるんですが、今回は自然なとろみだけで片栗粉は不使用。
炒飯にぶっかけて食べるのには、ソース増量、片栗粉不使用は大正解でした。
また、オイスターソースを少量加えたことで味に深みがでて、最高に美味しい仕上がりに。
春雨の中華サラダを作ろうと思い生きくらげを買ってきたら、それを見た旦那がきくらげと卵の中華スープが飲みたいと言うので、それも追加で作りました。
子供の頃から中華のテイクアウェイをしょっちゅ食べている旦那も、テイクアウェイ定番メニューの1つ、酢豚は大好き。
次回は昔食べて衝撃を受けたスタイルの酢豚を作って食べさせて上げたいのですが、上手に作れるでしょうか...
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
15品入セール
8700円の77%オフ
1980円(税・送料込)
3月18日まで!
私が試した時の感想などは
「こちらのブログ」でご紹介。
有機野菜・無添加食品の宅配ネットスーパー【らでぃっしゅぼーや】
ふぞろい食材お試しセット
16品+完熟パイン
5300円相当が62%オフ
1980円(税・送料込)
3月18日まで!
こちらもお得感ありあり!
「こちらのブログ」で詳しくご紹介。
到着後一度感想を聞く電話がありましたが、
定期購入を勧めるセールストークもなく気軽に試せるセットです。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
インスタグラムやっています。
是非フォローして下さい!
ブログでご紹介した食材、調味料、調理器具などは、
楽天マイルームでご紹介します。
インスタグラムに投稿したお料理は、
フェースブックページでもご覧いただけます。
ページのフォローもよろしくお願いいたします。
お帰り前には下の3つのランキングボタンをクリックしていただけたら、
私のブログのランキングがアップします。
こちらもどうぞよろしくお願いいたします。
ブログのフォローもよろしくお願いいたします!