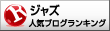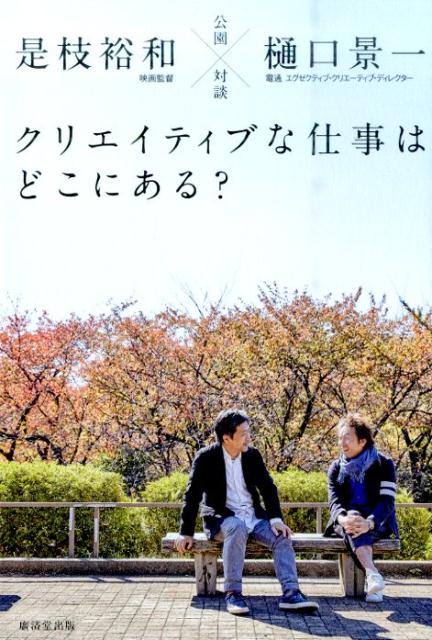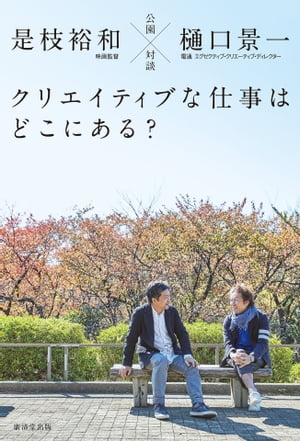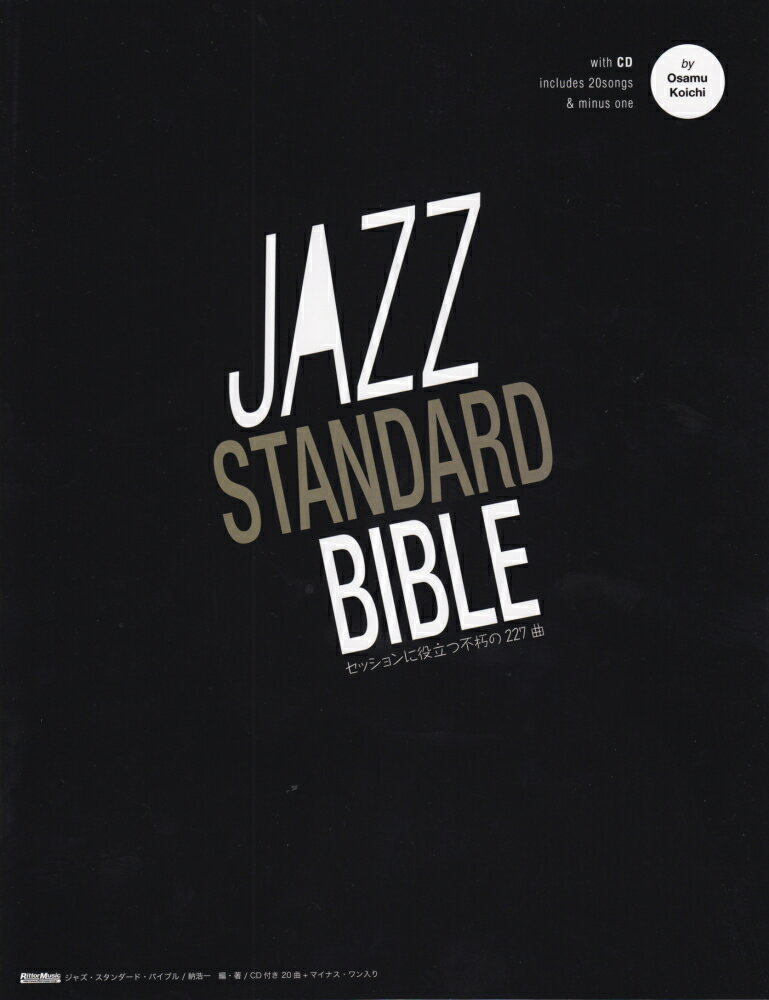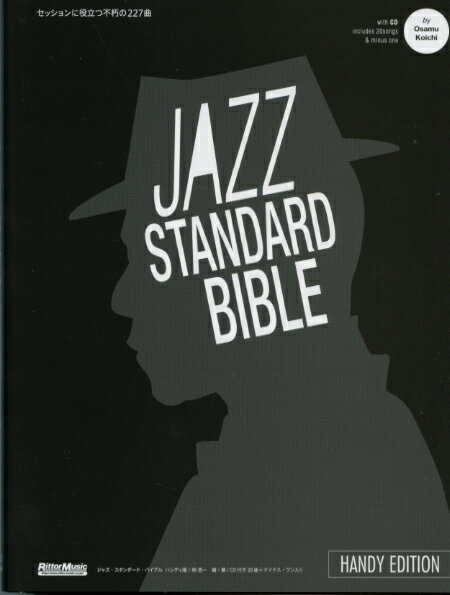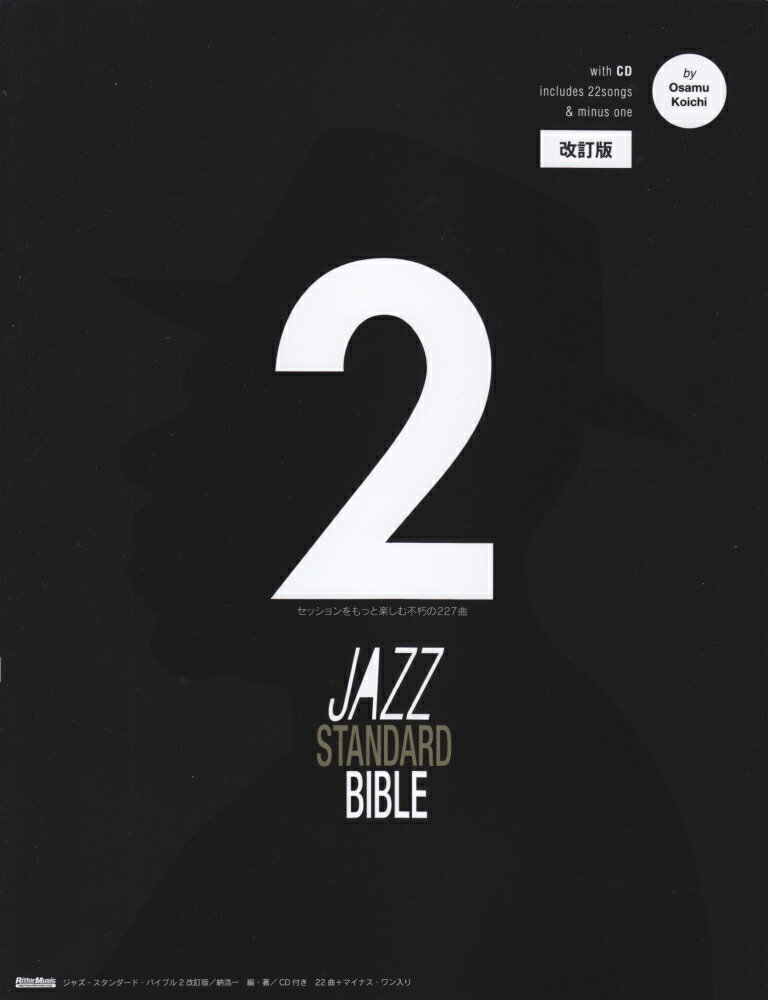参考文献 〜「公園対談 クリエイティブな
仕事はどこにある?」(是枝裕和×樋口景一)
「公園対談 クリエイティブな仕事はどこにある?」(是枝裕和×樋口景一)
目次
はじめに 樋口景一
春篇 仕事人としての位置づけ
なぜ、この仕事についたのか
とにかく映画が好きだった
隣の人が何をやっているかわからない会社
勝手に育つしかない
ここで仕事人生が変わった
こいつらを殺してから辞めよう
自分の居場所はここにあった!
「クリエイティブな仕事」なんてない
「自分」は人の間にしかない
「仕事のスタイル」とは何か
まったく異なる価値観をもつ人たちとの出会い
仕事を進めるときのアクセルとブレーキ
どれだけ多くの人の生き方に触れるか
仕事に影響を与えた人との出会い
テレビはジャズで、映画はクラシックだ
仕事で出会った人に影響を受ける
大切なのは「答え」でなく「問題」
「問題の適切な投げかけ」が大事
恋愛とストーカーの違い
なぜ日本人は「答え」をほしがるのか
夏篇 仕事人としての成功と失敗
インプットの作法
仕事の八割は情報収集で決まる
顔が見えない情報に振り回されてはいけない
先を考える前に飛び込んでみる
才能を開花させるもの
「勇敢さ」を基準に仕事をする
「創造」の声のもとに組織はできる
大切なのは、成長し続けること
賞をとるために仕事をする人
仕事の経験値を上げる
自分のなかを探しても何もない
仕事の一番の魅力は違った価値観に出合うこと
秋篇 仕事人としての閉塞感
人が成長するときに必要なもの
「見て見ぬふり」で部下を育てる
あえて組織に異物を入れる
自分の仕事を楽しく語る
結果を目的と勘違いしていないか
まずリテラシーを鍛える
〈ようこそ先輩〉で子どもに教わったこと
自分の仕事を楽しく語れる人間になる
仕事の壁を乗り越える
厳しくされても人は成長しない
「二八歳の壁」を乗り越える出会い
冬篇 仕事人としてどんな未来を選ぶか
世界標準の仕事をするために
スカイプでは伝わらないこと
日本が韓国より遅れている理由
なぜほかの会社と違うのか
目的と手段が逆転していないか
検索サイトは間違ったことをしたのかもしれない
ホリエモンの考え方には同意できない
自分に向いている感じが気持ち悪い
一つの会社で働き続けるメリット
ノウハウや価値観は継承されているか
古い会社から新しいものが生まれている
「最短」からは面白いものが生まれない
「役割」を取り払って考えてみる
17の質問
おわりに 是枝裕和
ジャズベーシスト 池田 聡 のブログ
↓ぜひ応援よろしくお願いします↓