京の冬の旅(3月18日で終了)で特別公開されていた
東福寺光明宝殿
に行きました
京の冬の旅 「東福寺光明宝殿」
東福寺は昨年秋に紅葉を見に行った時に、龍吟庵と即宗院の特別公開を見たので(ブログに書けなかったけど)、季節ごとに訪れていることになります
今回は光明宝殿
10時よりも前に行ってしまったので、並びましたが、とくに混んでいるというわけではありません(早起きの人が集まってたという感じ)
はじめに障壁画など見せていただきましたが、
私はここには仏像を観るという目的で来ました
本命は、もともと万寿寺にあったといわれる阿弥陀如来坐像なんですが
この像については、ひとまず置いておいて
光明宝殿に安置される金剛力士像について、つらつらと考えてみたことを、だらだらと書いてみようかと思います
問題意識がアレで、これといった結論もない、ふらふらした話ですが、どうぞお付き合いください
東福寺光明宝殿
金剛力士像(重文) 伝運慶作 鎌倉時代
まず東福寺光明宝寺にあるこの金剛力士像は通例のものと左右逆で向かって左側が阿形、右側が吽形です
むむ?左右逆の阿吽?…これどこかで聞いたことありませんか?
あの東大寺南大門の金剛力士像も左右が通常と逆の配置でしたよね?
東大寺南大門の金剛力士像も運慶・快慶など慶派仏師の力作でしたよね
東福寺の寺伝によれば、なんと東福寺の金剛力士像も運慶作として伝わっているそうです
現在認定されている運慶の作品のリスト(→こちら)に東福寺金剛力士像は入っていません が、
が、
少なくとも慶派仏師の手になるとは考えてよいようです(『古寺巡礼京都3 東福寺』淡交社、2009)
では、東福寺金剛力士像を一体ずつ見てみます
まず、吽形(うん)(207.7㎝)
見て見て!! 面白いポーズをしていますよ
なにかを凝視しているような表情をしています
「なんじゃこりゃ?」
どうやら道端で何か拾ったみたいなのです
だって、右手の親指と人差し指で何かをつまんでいますよ
現在はつまんだものが欠失しているのでしょうか?残念ですね
私が想像するには、視線方向がだいぶ下の方に向いているので、元々はネズミを捕まえて、ネズミのしっぽをつまんでいるところだと思いますよ(←真に受けないでね )
)
こんな感じにつまんでる?
それにしても、この吽形、ちょっとディズニーアニメ「アラジンのジーニー」🧞♂️に似ていませんかね?(真に受けないでね)
↓アラジンのジーニー
次にお隣の阿形(203.0㎝)を見てみると、吽形の拾い物に驚いていますよ
「ややっ ❗️❗️
おぬし、何を拾ったんだ?
 」
」
 」
」この下向きの視線の方向から推理するに、吽形がしっぽをつまんで逆さにしているネズミの方向を凝視しているのではないかと思われます
阿形くんは、マッチョなくせに小さなネズミが苦手なんですね(絶対違うので、真に受けないでね)
ところで、この東福寺金剛力士像の二体が慶派の金剛力士像ということなので、
同じ慶派作、かつ金剛力士像とまるでキーワードがそっくりな
「東大寺南大門の金剛力士像」
とちょっと比べてみたくなりますね
(比べることで、東福寺金剛力士像の吽形がつまんでいたものを明らかにしたい!)
↓東大寺南大門金剛力士像
向かって左 阿形(836.3㎝)、右吽形(842.3㎝)
東大寺南大門の金剛力士像は、東福寺像同様阿吽の左右が通常と逆です
向かって右の吽形を見てみると…右手の向きが東福寺像とは全然違いますね
こんなポーズでは、ネズミつかんでませんねぇ…おかしいなあ
阿形のほうは、「ややっ!?」って感じが少し東福寺と似てますね…でも東福寺の阿形みたいに白目をむいてませんねえ…おかしいなあ

でも、ちょっと待ってください
東大寺南大門の金剛力士像って、大きすぎない?
東福寺の2体がほとんど等身サイズだったのに比べると、東大寺南大門像の大きさは桁外れに大きく、 これじゃ比較できなくない??
ご参考↓
うーむ……🤔🤔
……ということで、
もはや完全に遊びですが
東福寺金剛力士像と比較できる像を改めて探してみました
ここで条件を改めて考え直し
①慶派、②金剛力士像、③それほど大きくない(等身大くらい)
という3条件で脳内(ポンコツ)検索をかけてみると…
↓こちらがヒットしました
興福寺国宝館金剛力士像
向かって左から吽形(153.7㎝)、阿形(153.7㎝)
こちらの像は通常の阿吽の配置です
この二体は興福寺旧西金堂の安置仏で、鎌倉時代に再興されています
大正2年(1913)の修理の時に阿形の右足枘(ほぞ)から墨書が発見され、それによれば正応元年(1288)10月10日に像が修理されて西金堂に戻されたこと、修理を担当した仏師は大仏師善増、絵所大仏師観実であることがわかったそうです
さらに江戸時代の『興福寺濫觴記』(おー!よくこんな難しい漢字が変換できたものだ)には、この金剛力士像が春日大仏師定慶作であり、やはり正応元年(1288)に大仏師善増と大仏師観実が修理したと記されているそうです
(足枘の中から出てきた修理記録と江戸時代の記録が一致しているわけです)
ちなみに定慶は、康慶の弟子といわれており(下の系図参照)、興福寺東金堂の文殊菩薩(私の好みじゃないお顔 )を制作しましたが、国宝館の金剛力士像については定慶が作者である確証はないようです(定慶または定慶周辺仏師の作といわれているそうです)
)を制作しましたが、国宝館の金剛力士像については定慶が作者である確証はないようです(定慶または定慶周辺仏師の作といわれているそうです)
( 慶派系図)
ま、定慶作かどうかは今の私にとってはどうでもよいことで …
…
東福寺像と興福寺像が、
①慶派
②金剛力士像
③ほぼ等身
だから、
「比較してみたらどうなるの?」
とふと思ったわけです
そして、
裏テーマとしては東福寺金剛力士像の吽形の右手がつかんでいるもの(もっともこの右手が後補じゃないという前提ですが)は何だったのか?似ている条件の興福寺像をみたら、それがわかるのではないのか?を明らかにしたかったのです
手にもっていたものが、あわよくばネズミ🐀だったら、すご~く面白いな~
という動機が主導力となって、ここまで進めたのでした
で、結論はどうなのよ?
・興福寺の吽形もネズミ持ってるの?
・阿形はやっぱりびっくりしているの?
ここから再度興福寺像を観察していきま〜す!
まず、吽形 を見てみましょう!
を見てみましょう!
 を見てみましょう!
を見てみましょう!えっ??えーっっ??
右手がないじゃん!?
これじゃ、わからないではないですか!
視線もこっちを向いていて、手元を見ていたとは思えないぞ!!
次!阿形は?
おっと、こちらも左手がない!
口をあけてはいますが、果たしてこれは威嚇なのか、驚きなのか、この表情だけでは私には読み取れません

結局、
結論もなにもないのですが(すんません)
わかったことは次のようなことです
1.鎌倉時代の慶派関係の金剛力士像は、少なくとも
❶奈良東大寺南大門
❷興福寺西金堂
❸京都東福寺
の三ヶ所にあった
(摂政九條道家が、奈良の最大の寺院東大寺と興福寺の名前をとって京都最大の大伽藍を造ったのが東福寺なので少なからず因縁があるのよね)
2.そのうち東大寺と東福寺の金剛力士は左右が逆の配置であること
3.この三組の中では、東大寺南大門の金剛力士像はその大きさともに、表情にも迫力がありずば抜けた出来栄えの像であること…
東大寺南大門金剛力士像 運慶・快慶と仲間たち作(8.3〜8.4m)
4.東福寺像は表情がお茶目で、是非とも一度は拝観したい像であること
東福寺光明宝伝金剛力士像 伝運慶作 (2mちょっと)
5.興福寺像は一番小さいのに頑張っている像であること
案外、寄り目で、ほんとはそんなに怖くないこと(え?)
興福寺国宝館金剛力士像 伝定慶作
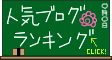
人気ブログランキング














