気がつけば9月も終わりで創造大会から1月以上経っていました![]()
なかなか文章に起こすのが難しくて・・・
これから何回かに分けて創造大会についてかきますが、真新しい何かがあるといわれるとそういうわけではありません。和久先生のおっしゃりたいことは「子どもの目の輝くとき」という本の中に凝縮されているかと。ただ、大会ではもう少し具体的にあそびを感じる手立てを学ばせていただけたのでそれについて記録できたらと思います。
***
今回お話にあげるのは、山口県にある保育園3歳児クラスの1年間のお話。
どの保育園もそうであるように、この園もまたベテランの先生の想いを新人である先生にどう伝えていくかという課題を抱えていたそうです。言葉を並べても、ビデオ等をみせても、それだけでは埋まらない何かがあると。その溝を埋めるためには保育者自身が実際に変化していく子どもの姿を肌で感じ取っていかないことには難しいと考えた園長先生は、3歳児クラスの運営を新人の先生に任せてみることを決断したのだそうです。
4月:
ざわつく3歳児さんはなかなか集中することができない。積み木を出しても崩すことに夢中で走り回る子たちもいる。そのなかで、担任の先生はどんなときにこどもが目を輝かせるのかを注意深く観察し、多くの子がモザイクに興味を示すことを発見。そこでこのクラスではモザイクを中心として1年を観察していこうと決めた。
⇒通常、3次元(立体)の世界であるボール・ケルンブロック(立方体・直方体)に触れさせてからモザイクという2次元(平面)の世界につなげていきます。こどもにとっては、現実の世界が3次元なので2次元よりも感じやすいからなのだそうです。ただ、大人になると逆に2次元の世界のほうが物事をつかみやすくなるそうで、担任の先生もそこに目をつけられたのではないかなと。園長先生はどうなるかハラハラしつつも口出しをしないと決めて見守っておられたそうです。
5月:
モザイクをただばらばらに置いていただけだった4月から、保育者が並べてみせるとそれをまねして列を作ったりくっつけて遊ぶようになる。形ができることを感じ始める。
端午の節句の時期は、風車を六角のパターンボードで作り飾っていた。
↑これらを組み合わせて、先生のを模倣して風車を作っていました。
7月:
あさがおを育てていて、それをモザイクで表現。(上記と同じ六角のパターンボード)
つるの部分はてぐすにビーズをさして巻き付ける。実際に育てたあさがお・図鑑から得た情報を造形(色水活動)・童具(モザイク活動)と関連性を持たせる取り組みが始まる。
8月:
モザイクで道を作り始める。最初2人からスタートしていたが、だんだんお友達の刺激を受けてみんなが参加し始め、いままでバラバラだったクラス内にすこしつながりが出てくる。モザイクを全部使い果たしたときにwaku-block30を提案するとこれもまたどんどんつなげてまたまた足りなくなる。そして円弧モザイクなどほかの童具をどんどんつないで遊んでいく。
⇒はじめて「使い切った」「やりきった」という達成感を感じた子どもたちのすっきりした顔。その集中力にただただ驚く保育者。
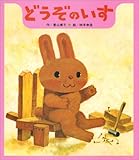 | どうぞのいす (ひさかた絵本傑作集) 1,080円 Amazon |
「どうぞのいす」を読んでから、木っ端を用いた椅子を作る。
積み木の箱に詰める遊びも始まる。
12月:
モザイクと積み木でクリスマス・リースを作ると、子どもたちから「どうやって作ったの?」という質問が出る。それまでは各々が作りたいように作っていたけれど、保育者の刺激を受けてもっと違うものを作りたいという意欲が出てくる。そしてそれをアレンジしてまた次々に面白いものを創り上げていく。
1月:
左右対称の雪の結晶を作る。角度・色の配置などの秩序を感じて並べるようになる。
3月:
ひな壇を積み木で作る。構造遊びへの展開を見せ始める。
ーーーーー
・多動でなかなかみんなと一緒に遊べなかった男児。
みんなが集中していても我関せずで一人違う遊びをしていた。1学期はずっと走り回って参加しなかったが8月から少し積み木を触る姿が見られる。しかし12月くらいまでなかなか集中するというところまでいかない。それが3学期になってから積み木に触れる回数が増え、そこからは一気に積み木の世界へ入り込みすごく集中するようになった。その積み木の遊びの意欲の高まりと比例して生活面での自立も一気に進むようになった。
・おとなしくてなかなかみんなの輪に入れなかった女児。
恥ずかしがり屋でみんながやっていても隅っこでいつもそっと遊んでいた。みんなの様子を観察してから動く感じでなかなか積極的にこうしたいということがなかった。しかし1月の雪の結晶をすごく気に入り、その時に初めて周りを気にすることなく自分はこうしたい!と意見を言えるようになった。そこで自分の意見を言えたことで大きな自信を持ち、作品もどんどん豊かになっていった。
----
担任の先生の気づき。
ほんのちょっとしたきっかけが、子どもたちに試行錯誤を与えるきっかけとなる。大人としてはその過程がもどかしいときもあるけれど、自分たちで発見した時の驚きの目を実際に肌で感じると、その遠回りの道こそが大事であったと気づかされる。
***
ついつい入口はこうじゃなきゃいけないと頭でっかちに考えがちですが、興味を持ったものからでいいのですよね。なぜなら童具のすばらしさは「関係性をみつけること」にあるから。要はどの切り口からでもつながりを感じ取れるということです。
この園の子たちは卒園制作で「童具共育」にのっているような大作を創り上げます。
この時紹介があったのは「城」でしたが、萩城・岩国城ときて卒園制作で松江城を作ったのだとか。図鑑に載っている模型を細かく観察し、実際に遠足で足を運んで観察をし(図鑑だけではわからない仕組みを聴き)、つくり上げていきます。
童具共育にあがっている例。
複雑にみえても一つずつは基本ができていれば難しくない。ケルンブロックでの構造あそびをムスメとしているが、その理解が深まるにつれ大きな積み木あそびも複雑化しているのを感じる。

