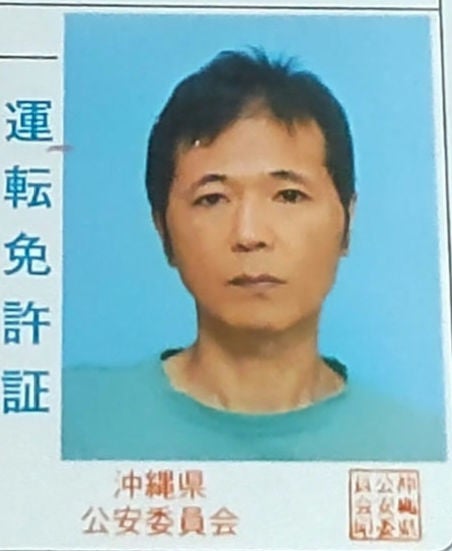お試しブログ
ブログの説明を入力します。 反物製作にお繋ぎお忍びお試し
プロフィール
テーマ
カレンダー
ブログ内検索
2016年02月15日(月)
エイちゃん
テーマ:下書き台風が過ぎ去った後、
町が穢れ (けがれ / 汚れ) たように見える反面 ⇔ 浄め (清め / キヨメ) られたように見える感じをしました。
町だけでなく、山でも木も倒れ、これまで蔭に隠れていた木が光を浴びて大きくなる場合が見られました。
台風は厄 (わざわい / 災い) であるけど、台風のお蔭 (おかげ) で大きくなる木、または台風に倒れなかった木は強い木 / 実力の木と云われ、人間社会においてはそれを『成り上がり』と呼んでいます。
ー・→
『成り上がり』というと?‥

『エイちゃん』を思い浮かべる人が多いようです。
ー(・・? ー・ー
一説によると、

室町時代に起きた 「応仁の乱」 が『成り上がり』という言葉を生んだと云われています。
「応仁の乱」 とは、室町幕府の将軍・足利家の後継者争い (内紛) から起きた争乱で、応仁の乱以降、社会秩序は乱れ、もはや朝廷や貴族の権威も薄れ、将軍の統制力も皆無、世は無法地帯、そしてこれまで身分が低い者でも地位の高い者を倒す『下剋上 (げこくじょう)』の時代 → 戦国時代 (不安定な時代) に突入して行きます →
その下剋上の時代に『成り上がり』という言葉も流行し、家来の家来が主君を倒し、乗っ取ったり各地で見られました。そうした不安定な戦国時代 (下剋上の時代) に、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康といった武士が登場します。
これまでの 「守護大名」 と『戦国大名』はダイブ違い、「応仁の乱」 以前と以後の『武士』の意味もまた大きく異なるといいます。

室町時代と江戸時代の間に戦国時代 (下剋上の時代) がありました。
室町時代に起きた 「応仁の乱」 をきっかけに戦国時代 (室町時代) が始まり → 織田信長と豊臣秀吉が登場する戦国時代 (安土桃山時代) に通じたようです。
晩年の織田信長は安土城を居城とし、豊臣秀吉は伏見城を居城としていました。伏見城に 「桃の木」 が植えられていた事から伏見城は『桃山城』とも呼ばれていたので、織田信長と豊臣秀吉の時代を 「安土桃山時代 (戦国時代) 」 といい。また、最近の教科書では 「安土桃山時代 (戦国時代) 」 とは記さづ ⇔『織豊時代 (戦国時代) 』と記す教科書もあるという。
ー・ー
不安定な戦国時代、

戦国時代 (室町時代) 、
戦国時代 (安土桃山時代)、
戦国時代 (織豊時代)、
(・・? 3つ戦国時代 (下剋上の時代) があったといいます。