- 闇屋になりそこねた哲学者 (ちくま文庫)/筑摩書房
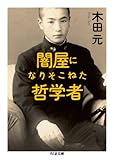
- ¥756
- Amazon.co.jp
戦後の混乱期、東京の闇市で働いていたエピソードが有名な哲学者の自伝です。
実存的な問題意識から哲学を志し、20歳を過ぎてから大学に入学した人です。
ちなみに、哲学の話はともかく、今回のテーマと関係するので少し触れておくと、実存的な危機意識や不安といったものは、何も哲学者の専売特許ではなく、程度の差はあれ全ての人間が共有する問題だと思います。
著者は、本当に学びたいことができて、そこではじめて学問を志したとされる人です。
そのことから、「勉強は自分が本当にやりたいと思ったときに始めればいいんだ」みたいな考え方の代表例として、一般誌などに採り上げられることがよくあります。
私も最初はそれを真に受けて、この人は20歳を過ぎてはじめて勉強というものを始めた人なんだな。それまでは勉強とは無縁な人だったんだな…という風に著者のことを捉えていました。
でも、違いました。
著者は、闇屋になる前まで、つまり戦争終結までは、広島の海軍兵学校の学生でした。
つまりは、当時のスーパーエリートでした。
当時の、睡眠時間なんて普通に削って1日20時間近く当たり前に勉強するような、そんな学生たちの中でもスーパー出来のいいほうの学生です。著者も当然、現在の学生・受験生とは比べものにならないくらいの「勉強」をしてきたはずです。
騙された・・・というより、むしろ、「なんだよー。やっぱりなぁ~」と思いました。
「勉強は自分が本当にやりたいと思ったときに始めればいいんだ」みたいな台詞は、それまで無茶苦茶勉強してきた人が言うことが実際には多いし、それまで無茶苦茶勉強してきた人が言うことにこそ意味があるからです。
もちろん、人生の途中から心を入れ替えて勉学に励むようになった人が言っても構わないのですが、そういうタイプの人(たとえば中卒で財界の大物にまで上り詰めたような人)は、むしろ、「もっと早く気づくべきだった」としきりに後悔の弁を述べることが実際には多いです。
つまり、生涯を通じて無茶苦茶勉強してきたタイプであれ、途中から始めたタイプであれ、本物の勉強家というのは、総じて自己評価の規準が一般人に比べて異常に厳しいものです。
本物の勉強家は(どちらのタイプであれ)自らを甘やかす(正当化する)ような物言いはしないのが普通です。極端に言えば、本物の勉強家というのは、自己の勉強のあり方を恥じることが習慣のようになっているのです。彼らは常に、自らの来歴そして現状に懐疑の目を差し挟み続けることを忘れません。その習慣こそが、彼らを本物の勉強家にしてきたわけです。
反対に、本質的な意味で勉強をしない人というのは、自己に対する規準が甘く、自らの現状・来歴を正当化しがちです(司法試験受験生・弁護士の多くも、試験勉強以外の勉強をほとんどする習慣がないという意味でこのカテゴリーに入ります)。
彼らに(試験勉強ではない)勉強の話をすると、返ってくる答えはいつも決まっています。
「勉強はさ、試験が終わってからすればいいじゃん」
「そういうのは、必要になったときでいいと思うんだよね」
…この答えは、表面だけをみれば、今回のエントリーで紹介した木田さんの主張(=勉強は自分が本当にやりたいと思ったときに始めればいい)と同じです。
しかし、実質的な意味内容は違いますし、むしろ真逆の答えともいえます。
私自身は、これはどちらが正しいor間違っているという話ではなく、根本的な人間観(理念)の違いなのだと思っています。
ちなみに、「勉強するのは試験が終わってからでいい」と言っていた彼らが、実際に合格(または撤退)した後に宣言通りに勉強を始めるかというと、もちろん99%そうはなりません。
単純に、人は今できていないことは将来もできないからです。
人間は変わらない生き物だからです。
ともあれ、著者は、大変な受験競争を勝ち抜いてきたにもかかわらず、それまでは真剣に勉強をしたという自覚がなかったわけです。
そういう人が、学生時代にどんな「勉強」をしてきたかが書かれています。
著者は、若い時から学校の勉強や試験勉強にあまり苦労しなかったそうです。
親からひとつのシンプルな方法を教えてもらっていて、それを実践していたからです。
その方法とは、
「ただしつこく繰り返すだけ」
・・・あぁ、またしてもこれです。
このブログの読者には、「またそれか」と思われてしまうかもしれません。
しかし、著者が語る行間からは、「こんなに簡単で楽なやり方があるのに、なんで皆そうしないんだろう」とでも言いたげな雰囲気が伝わってきます。
著者は語学の達人でもありました。
学生時代までに勉強した英語、哲学者(ハイデガー研究者)としての専門であるドイツ語だけでなく、メルロ=ポンティなどフランス語の哲学書も翻訳していますし、ギリシャ語・ラテン語にも堪能だったようです。
本格的な哲学研究に移行してから後も、著者は受験時代に培った試験勉強のノウハウを駆使して、これら大量の語学を修得していったようです。
その部分から少し引用します。
毎日やらないと駄目です。
昨日のことは覚えていても、一昨日のことは忘れるものです。
あまり忘れると嫌になってやめることになります。
どんな人でも五日間つづけて見たものは覚えるものです。
特に記憶力がよくなくても、このやり方でやれば覚えられます。
能力なんか関係ない。全てはやり方ですよ・・・という著者の声が聞こえてきそうです。
著者の勉強法は、極めて単純ですが、しかしとても理に適った方法です。
著者の言うとおりに勉強すれば、たしかに誰でもできるようになるのでしょう。
現在でも十分以上に通用するこの単純明快な勉強法は、すでに戦前から存在したものなのです。
戦前から、分かっている人は分かっているし、分かっていない人は分かっていない。
現在でも、分かっている人は分かっているし、分かっていない人は分かっていない。
勉強法を取り巻く状況が、戦前から何ひとつ変わっていないことに驚きます。
きっと、勉強法は、100年前から少しも進化していないのです。
優れた方法論は、100年前からずっと変わらず、誰でも手の届くところに置かれている。
その上で、それを手に取る人と、手に取らない人がいる。ただそれだけの話なのです。
進化論的にいえば、競争の過程で徐々に優れた方法論が選択(劣った方法論が淘汰)されていくはずですが、人間界では必ずしも進化論どおりに事は運ばないようです。
その証拠に、優れた方法論を手に取る人と取らない人の割合は、今も昔も、ずっと変わらないままです。
「しつこく繰り返せ」と言われて、素直にそうできる人と、言われてもできない人がいる。
どんなに「この方法でやれば楽だし結果も出るよ」と言われても、できない人は永遠にできません。
大袈裟にいえば、それが人間という存在者の宿命なのでしょう。
方法論の最大の難所は、様々な方法論の中から、優れた方法論をどのようにして選択することができるか、といった各方法論間の選択の困難さにあるのではありません。
そうではなくて、方法論の最大の難所とは、そもそもその人に方法論を選択する気があるのか、という精神論的な二者択一の次元にこそあるのです。
結局、その人が本気でなければ、どんな優れた方法論にも意味はないということです。
ここでいう「本気」とは、狭義の努力とは違います。
狭義の努力とは、要はマラソンみたいなものです。やる気と忍耐力が全てです。
こういったやる気と忍耐力は、大半の司法試験受験生が備えています。
繰り返します。
ここでいう「本気」とは、努力のことではありません。
努力は、誰にとってもある程度はシンドイものです。
しかし、「本気」のほうはそうではありません。
ある人にとっては空気を吸うように簡単なことであり、ある人にとっては「本気」になるくらいなら三振(失権)したほうがマシだ、と思えるくらいツライものです。
ある受験生がどちらの陣営に属するかは、受験開始前に決まっています。開始後に陣営の変更が行われることはありません。・・・いえ、「極めて稀だ」ということにしておきましょう。
人間は変わらない生き物です。
これは当然です。
もし変わったら、その人はその人でなくなってしまうからです。
たとえば、「過去問を解け」と言われて素直に解く人は、普通はどんな試験でも合格します。
しかし、本性的に過去問を解きたくない人が「過去問を解け」と言われて、もし言われるままに解いてしまったら、その人は自分が自分であるための最も大事な“何か”を失ってしまいます。
自分が自分であること。 これはほとんど人間の実存的な欲求です。
三振(失権)の脅迫なんかと交換できるような「安い」ものではないのです。
このように、自分が自分でいられるなら、人はどんな不幸でも基本的には受け入れます。
司法試験に限らず、そんな例は世界中に遍在しています。
人は変わりません。
このことは間違いありません。私自身、身をもってそのことを確認しました。
しかし、個体レベルなら、あるいは変わることもありうるかもしれません。
少なくとも、そう信じるのでなければ、人間なんてやっていられないのは確かです。
おすすめ度⇒B