将来、字を教える先生になりたいと思う学生の方に向けて、私が思う理想的なステップアップの流れをお伝えします。
山田硬筆教室では、字を書くことに慣れてきたら日本書道教育学会の段級取得をおすすめしていますが、年齢と実力に合わせて硬筆検定の受験もおすすめしています。(出来れば硬筆だけでなく、小学3年生からは毛筆も一緒に受講するとさらに良いと思っています。)
なかなか理想通りにはいかないと思いますが
私自身の経験をふまえて
私が思う、将来、字を教える先生を目指す場合の理想的なステップアップの流れをお伝えします。
【ステップ1】
小学校卒業までに、ひらがな、カタカナ、楷書の書き方をマスターし、字の整え方やポイントを覚え、自信を持ってきれいな字が書けるように練習していきましょう!まずは、お手本をよく見て、お手本と同じように書けるようにしていきます。学校で金賞をもらえる子や競書の本の写真版に載る子は将来先生になれる素質が充分あると思います。段級が四〜五段以上の子は書き順などもしっかり覚え、6年生のうちに硬筆検定5級にチャレンジしてみてください。
【ステップ2】
中学生になったら、お手本を見て、そっくり真似て書くだけでなく、お手本を見なくても上手に書けるよう意識して練習していきましょう!出来れば段級取得をしながら、硬筆検定4級〜3級合格を目指すことをおすすめいたします。楷書のほかに行書や連綿、変体仮名についても学びはじめると良いです。色々な書体を書き分けられるようにしていきましょう。
【ステップ3】
高校生になったら、上記の内容に加え、古典のかなの臨書や変体仮名や草書の読み書きも学び、流れるような線で綺麗に書けるように練習していきましょう。そして、草書やかなも読めるようになったら硬筆検定3〜2級の合格を目指しましょう。
【ステップ4】
高校卒業後は、日本書道教育学会のペン硬筆師範コースに2年間(月2〜4回)通い、師範取得を目指すことをおすすめいたします。段級取得はそのまま継続していき、写経や随意課題も出品していきましょう。余裕があれば草書や旧字体、書写体を覚える勉強もはじめましょう。
【ステップ5】
師範取得後は、開業準備または教室を開きながらゆくゆくは最高段位の会友、硬筆検定の準1級、1級取得を目指すことをおすすめいたします。合格率は非常に低いので草書をたくさん暗記して書けるようにならないと合格は厳しいです。
※毛筆の場合は、中学生になると楷書、日常的な文字のほかに、つなげて書く行書、芸術的な表現の漢字、かな、調和体、臨書など古典的な要素を含んだ大人と同様の課題をおこなっていきます。課題が増えて大変ですが、出来ることなら硬筆だけでなく毛筆検定も並行して受験していくとさらに良いと思います。
日本書道教育学会と日本書写技能検定は別の会ですが、両方を学ぶことで書く技術と知識がしっかりつきますので、先生を目指す場合にはどちらか片方だけでなく出来れば両方学ぶことをおすすめいたします。
以上が、私が思う先生を目指す場合の理想的なステップアップの流れです。
難しそうなことをたくさん書きましたが、段級や資格取得を目指さず、今より少しでもキレイな字が書けるように無理せず楽しみながら受講することももちろん選択肢としてありますし、そのような通い方をする方は多く、大歓迎ですので安心してください。
ただ、今回は
字を書くことが好きで、得意分野で、いつか先生になりたい!と思う方に向けての記事を残しておきたいと思いましたので、あえて理想を書いています。
目指す人は、ほんの少数かもしれません。
でも、埼玉県の小学生の硬筆展を見に行くと何千点?もの素晴らしい作品を目にします。
それだけたくさんの素質ある小学生がいるということです。
しかしながら、残念なことに字が上手でも小学生までで硬筆を辞めてしまう子が多いのが現状です。
中学英語が大事なように、中学〜高校で学ぶ硬筆(毛筆)も重要なのです。そこをやらずに大人になるのと、辞めずに少しずつ積み重ねていったのでは大きな大きな差になります。
中学生からは部活や試験や受験もあり、なかなか理想通りにはいかないかもしれません。ですが、字を書くことが好きで、将来先生を目指す方には、少しずつでも、このような流れを意識してステップアップしていってほしいと思います。
私自身は、中高は字を習わず、20歳くらいで師範を目指しはじめ、22歳くらいで師範取得をして、そのあとに硬筆検定の内容を勉強してきましたので、やる気と根気さえあれば大人になってからでも、けして遅くはなく大丈夫だとは思っていますが、早い段階で師範取得を出来たことは良かったと思っていますし、硬筆師範取得後に毛筆の「かな」を学んだことや、硬筆検定の内容を一通り学んだことで知識が深まったと思っていますので、先生を目指す方は、一つの資格で満足せず、たくさんのことを学んでいく姿勢を忘れないでいてほしいと思います。
私自身「学びながら教え、教えながら学ぶ」というスタンスで歩んできていますので、教室を開いて12年の今でも勉強中です。きっと私だけでなく、字を教えている先生方はいくつになっても学び続けています。
私が小学4〜5年生の頃、将来硬筆のお手本を書く人になりたいと強く思ったことがあり、師範取得後にどこよりも癖のない、習う人にとって一番良いお手本が書けるようにと字を磨いてきました。大好きな硬筆だけは極めたいという思いがあるので、これからもまだまだ勉強していきたいと思っています。
資格取得するには、字をきれいに書くだけでなく、暗記することも多くて大変ではありますが、目標を持つことで、年々成長を感じることができますし、着実に実力が備わっていきます。
ゆっくりでいいので、長い長い道のりをあきらめずに歩み、資格を取得することや、先生になることを目指してもらえたら嬉しいです!

大人になってから先生を目指す場合は、
まず大事なポイントを理解したほうが効率よく学んでいけますので、こちらのeラーニング講座2つを受けていただくことをおすすめいたします。
そのうえで、
段級取得で最高段位を目指すこと、そして、写真の硬筆書写検定五級対応の本(左上)、4〜1級までの合格のポイントの本+毛筆書写検定ガイドの本や、新しく出た二〜三級のドリルを取り寄せて、受験はしなくとも本に載っている内容を把握して一通り勉強しておくといいと思います!これらを2年程おこなった後に2級以上の資格を取得するか、師範のお免状がもらえる師範コースに2年通われると良いと思います。
以上です。
先生を目指す方の参考になれば幸いです。
段級取得の競書についてはこちら
硬筆検定 試験内容についてはこちら
硬筆検定 二級、三級のドリルはこちら
日本書道教育学会 硬筆師範コースついてはこちら
神田書学院 所在地 受講日について
講師育成講座についてはこちらをご覧ください。
 日本書道教育学会|月刊書道誌
日本書道教育学会|月刊書道誌 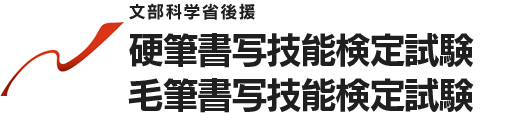 過去の問題例|一般財団法人 日本書写技能検定協会
過去の問題例|一般財団法人 日本書写技能検定協会  講師育成開業サポートについて
講師育成開業サポートについて