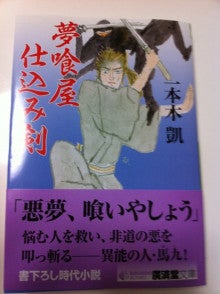- 前ページ
- 次ページ
携帯を見つめながら、思う。永井君は察しがいい。君には確かに兄がいる。
「でも、言えないよな」
ガクからも口止めされているし、気安く口を滑らす類でもない。
ガクはガクで考えがあるだろうし。それは僕が意見するまでもない。
「しかし、君たち。似ているところ、あるよ」
二人を前に言える機会があると、面白い。そう思いながら僕はのんびりと、部屋で寝転がる。
一つ終わったような気がする。でも、その途端「スタートせよ」って煽られているように感じて仕方がない。
それは声。耳を澄ませば必ず聞こえる、自分をポジティヴにする、力強い声。
僕は起きあがり、パソコンを開く。そして、検索する。
「募集。塾の講師。経験者優遇」
了
「でも、言えないよな」
ガクからも口止めされているし、気安く口を滑らす類でもない。
ガクはガクで考えがあるだろうし。それは僕が意見するまでもない。
「しかし、君たち。似ているところ、あるよ」
二人を前に言える機会があると、面白い。そう思いながら僕はのんびりと、部屋で寝転がる。
一つ終わったような気がする。でも、その途端「スタートせよ」って煽られているように感じて仕方がない。
それは声。耳を澄ませば必ず聞こえる、自分をポジティヴにする、力強い声。
僕は起きあがり、パソコンを開く。そして、検索する。
「募集。塾の講師。経験者優遇」
了
「名字が」
「そう、『永井』だ。俺の調べた現在住居の地区と南が家庭訪問に行った場所も一致した。だから俺は行った」
「会ったのか」
ガクは首を横に振った。
「見に行っただけだ。南の言ったように、立派な家に住んでいた。出来てくるまで待った。怪しいことを承知で。
はっきり見たよ。姿、形、そして、声。スーパーまで付けていった。そこで知人と会って話し込んでいた。普通のおばさんだった。でも、俺の持っている古い写真の面影そのままだった。確かに母親に間違いはなかった。もう充分だったよ。それで」
「——そうか」
「母親の唯一の思い出は、チーズケーキだ。手作りの、チーズケーキ。美味しかったんだ。その味は、忘れない」
学食の窓から透き通った冬の空が、青く輝いている。
「これで、俺がここにいる理由が無くなったわけだ」
センター試験を受けたにも拘わらずこの大学に来た理由。
「そうだよ。母を見つけるためだ」
ガクは、続けた。
「ここにいる理由が無くなったからと言って、この大学を辞めると言うことには繋がらない。他に強力に引き寄せる何かが、今のところ見あたらない」
ガクは、察したかのように笑った。
「安心しろ。辞めないから。四月からは三年だ。忙しくなるぞ」
「そう、『永井』だ。俺の調べた現在住居の地区と南が家庭訪問に行った場所も一致した。だから俺は行った」
「会ったのか」
ガクは首を横に振った。
「見に行っただけだ。南の言ったように、立派な家に住んでいた。出来てくるまで待った。怪しいことを承知で。
はっきり見たよ。姿、形、そして、声。スーパーまで付けていった。そこで知人と会って話し込んでいた。普通のおばさんだった。でも、俺の持っている古い写真の面影そのままだった。確かに母親に間違いはなかった。もう充分だったよ。それで」
「——そうか」
「母親の唯一の思い出は、チーズケーキだ。手作りの、チーズケーキ。美味しかったんだ。その味は、忘れない」
学食の窓から透き通った冬の空が、青く輝いている。
「これで、俺がここにいる理由が無くなったわけだ」
センター試験を受けたにも拘わらずこの大学に来た理由。
「そうだよ。母を見つけるためだ」
ガクは、続けた。
「ここにいる理由が無くなったからと言って、この大学を辞めると言うことには繋がらない。他に強力に引き寄せる何かが、今のところ見あたらない」
ガクは、察したかのように笑った。
「安心しろ。辞めないから。四月からは三年だ。忙しくなるぞ」
「高校受かったから報告するよ。私立だけど」
「おめでとう。私立なんだね」
「そこ、将棋が強いから」
その後彼は続けた。
「もう一度奨励会試験受けることにしたよ」
僕はその言葉を聞いて、安堵、というより、救われたような気になった。
「先生、ありがとう。先生ってさ」
「なんだ」
「先生って、お兄ちゃんみたいだよ」
そうか、お兄ちゃんか……。
永井君と再会の約束をして、電話を切った。
「お兄ちゃんというのは……」
それは一月末、試験最後の日、ガクと今年度最後の昼食を取った時のことだ。
「南の生徒、将棋の好きな彼」
「ああ、永井君だけど」
「彼、俺の、弟だ」
「えっ」
「正確に言うと、父親が違う」
「と言うと」
「俺の両親は俺が四歳の時に別れた。理由は聞いてない。どう転んでも良い方向にはいかないから、知ったとしても意味はない。俺が父親に引き取られたことからある程度の予想はつく。
父の実家は寒い地域だから、体になかなか合わなくてね。そのたび俺は体調を崩した。そういうときって、父親は役に立たない。痛感したよ。
母がどこにいるのか分からなかった。一度も会わせてもらえなかったから。父は俺が八歳の時に再婚した。そうなると俺を母に会わせる理由も無くなった。
俺は、母に会いたかったか。どうだと思う?」
「それは、当たり前だろう」
「そうだ。俺は、会いたかった。母の姿をあまり覚えてはいない。だから美化してしまうのは分かっている。しかし、それが会いたいという気持ちを否定する理由にはならない。
高校に入り、行動の自由が出来た。だから俺は調べる事にした。簡単じゃなかったが、高三になっておおよその場所と現在の名字が分かった」
「名字が」
「おめでとう。私立なんだね」
「そこ、将棋が強いから」
その後彼は続けた。
「もう一度奨励会試験受けることにしたよ」
僕はその言葉を聞いて、安堵、というより、救われたような気になった。
「先生、ありがとう。先生ってさ」
「なんだ」
「先生って、お兄ちゃんみたいだよ」
そうか、お兄ちゃんか……。
永井君と再会の約束をして、電話を切った。
「お兄ちゃんというのは……」
それは一月末、試験最後の日、ガクと今年度最後の昼食を取った時のことだ。
「南の生徒、将棋の好きな彼」
「ああ、永井君だけど」
「彼、俺の、弟だ」
「えっ」
「正確に言うと、父親が違う」
「と言うと」
「俺の両親は俺が四歳の時に別れた。理由は聞いてない。どう転んでも良い方向にはいかないから、知ったとしても意味はない。俺が父親に引き取られたことからある程度の予想はつく。
父の実家は寒い地域だから、体になかなか合わなくてね。そのたび俺は体調を崩した。そういうときって、父親は役に立たない。痛感したよ。
母がどこにいるのか分からなかった。一度も会わせてもらえなかったから。父は俺が八歳の時に再婚した。そうなると俺を母に会わせる理由も無くなった。
俺は、母に会いたかったか。どうだと思う?」
「それは、当たり前だろう」
「そうだ。俺は、会いたかった。母の姿をあまり覚えてはいない。だから美化してしまうのは分かっている。しかし、それが会いたいという気持ちを否定する理由にはならない。
高校に入り、行動の自由が出来た。だから俺は調べる事にした。簡単じゃなかったが、高三になっておおよその場所と現在の名字が分かった」
「名字が」
「せめて入塾テストとか受けさせても」
「一樹に恥を掻かせたくないんですよ。それに、これ以上ショックを与えたくありません」
言葉がなかった。
ショックという言葉がぴったりだった。彼はやっぱり「見捨てられた」と思っているのか。
いや、そんなことはない。そうしてはいけないのだ。
「あの、一つ提案があるのですが」
「提案、ですか?」
「僕を、家庭教師、一樹君の家庭教師にしてくれませんか」
「家庭教師、ですか」
「はい、ぜひ」
「はあ、でも……」
「お願いします。力になれるはずです」
「では、せっかくですから——」
「よろしくお願いします」
明後日の五時に行く約束をして電話を切った。
勢いで言ってしまった。もちろん家庭教師なんてしたことがない。どうやっていいか分からない。でも、やるしかない。彼の為に。ちょっとだけ、自分のために。
昨日、高校受験すべての日程が終了した。二月の二十五日だ。結局僕は一樹君の他、秀吉クラスの八人にも声をかけた。既に他の塾に入り込めた子や、家庭教師を雇った生徒もいた。中には僕や塾の事を罵倒した母親もいたが。最終的に一樹君を含め、四人の家庭教師を担当した。そのうち二人は元茶髪の女の子達で、一緒に見て欲しいとのことで、どちらかの家に集まり、面倒を見た。
自分のテストもあった。今回も徹夜して勉強した甲斐があり、再試はなかった。
携帯が鳴った。永井君からだ。
「一樹に恥を掻かせたくないんですよ。それに、これ以上ショックを与えたくありません」
言葉がなかった。
ショックという言葉がぴったりだった。彼はやっぱり「見捨てられた」と思っているのか。
いや、そんなことはない。そうしてはいけないのだ。
「あの、一つ提案があるのですが」
「提案、ですか?」
「僕を、家庭教師、一樹君の家庭教師にしてくれませんか」
「家庭教師、ですか」
「はい、ぜひ」
「はあ、でも……」
「お願いします。力になれるはずです」
「では、せっかくですから——」
「よろしくお願いします」
明後日の五時に行く約束をして電話を切った。
勢いで言ってしまった。もちろん家庭教師なんてしたことがない。どうやっていいか分からない。でも、やるしかない。彼の為に。ちょっとだけ、自分のために。
昨日、高校受験すべての日程が終了した。二月の二十五日だ。結局僕は一樹君の他、秀吉クラスの八人にも声をかけた。既に他の塾に入り込めた子や、家庭教師を雇った生徒もいた。中には僕や塾の事を罵倒した母親もいたが。最終的に一樹君を含め、四人の家庭教師を担当した。そのうち二人は元茶髪の女の子達で、一緒に見て欲しいとのことで、どちらかの家に集まり、面倒を見た。
自分のテストもあった。今回も徹夜して勉強した甲斐があり、再試はなかった。
携帯が鳴った。永井君からだ。