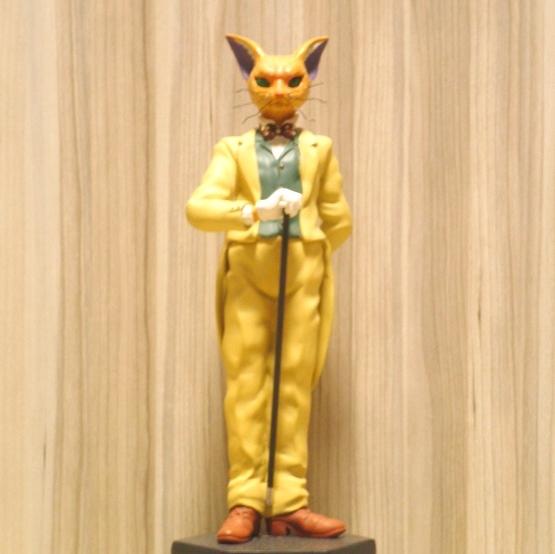※この雑感②は、2022年に書かれたものです
受験指導
●この10年くらいの間に2人の子どもに受験指導をしました。
「指導」といっても大したものではなく、ようするにこのブログに書いてある方法論をそのまま実行するように言っただけです。つまりは過去問主義です。
その中で見えてくるものがあったので少しその話を書きます。
●ちなみに、受験というのは(最初は)中学受験です。個々の教科を教えるようなことはあまりしていません(せいぜい国語くらい)。基本的には他人(塾講師・家庭教師)任せです。
といっても、他人任せであるがゆえに多少の問題は発生しました。
中学受験というのは、SAPIXならSAPIXの方針が完全に徹底されていて、その方針から外れたことは時間的にほとんどできません(まあ私の頃もそうでしたがよりそんな感じでした)。
家庭教師のほうも同じで、中学受験の勉強方法は、資格試験や大学受験よりもはるかにマニュアル化が徹底されていることを知りました。
●しかし、最も合理的な方法論=過去問主義であることは明らかなので(苦笑)、過去問主義を心置きなく実行するため、仕方なく6年生からはSAPIXをやめて家庭教師一本(週3くらい)にするという「暴挙」に出ました。
●すでに過去問主義が最良の勉強法であるとの確信を抱いてはいました。わざわざブログを始めたのはそれを伝えるためでしたし、自分もそうしましたし、もし誰かにアドバイスをするなら、それ以外に選択肢はないと思っていました。
しかし、いざ全責任をもって引き受けるとなると、私のようなちゃらんぽらんな人間でも、多少以上の躊躇を感じたことを告白せざるを得ません。
●でもとにかく信じた道を行くしかないと思って、その道を進み(進ませ)ました。
やることは簡単で、6年生の初めから赤本(+科目によっては基本問題集)をひたすらぐるぐるです。自習でぐるぐる。家庭教師を横に付けてぐるぐる。
●そういえば、「小学生は記憶力がいい」とか誰が言ったのか。そんなことは全くありませんでした。3日前にやった問題でも、子どもはすぐに忘れます。だから過去問の答えを覚えてしまって意味がなくなる、といった心配は全く無用でした。何度も間違えて、何度もやり直しました。
●過去問主義への転回
そこそこ順調に運んだように書いてしまいましたが、実は最初の段階で躓きがありました。
そもそもこのような(塾をやめるという)大きな賭けにでることになった理由は、5年生の段階で当初の第一志望であったA校の合格が絶望的に思えたからでした。
このまま授業→模試を繰り返しても到底届く「距離」ではない。そこで、一か八か過去問主義でやってみるか、ということになったわけです。
●過去問主義の限界
結論からいうと、この試みは失敗に終わりました。ひょっとすれば私の指導力が足りていなかったのかもしれませんが、まず彼はその中学の過去問を「読む」ことができなかったのです。横に家庭教師を付けて解説させてもダメでした。特に算数が難しかったです。答えを棒暗記することはできても、数字を入れ替えるだけで(実質的に)同じ問題が解けなくなってしまいます。
●どこかのエントリーで「日本語のできないイラン人に過去問主義が採用できるか」という思考実験をしたことがありますが、まさにその状態でした。
過去問(問題と解答)が読めなければ、過去問主義は実行できません。
6年生の夏ごろに、第一志望をB校に変更することになりました。
●B校の過去問は(家庭教師の説明付きであれば)もちろん正解はできませんが、解くこと&読むこと(説明を理解すること)はできました。
私も「これなら何とかいけるかも」と思い、そのまま進むことにしました。
●私のブログを読まれてきた方には、「まあ、それなら行けるんじゃないの?」と思っていただけるかもしれませんが、実際にはかなりハラハラドキドキの1年間でした。
10回ほど受けた模試のうち、「合格可能性40%」を取れたのは1度だけ。残りは全部20%(0%とは言わないんですよね)だったので。
まあ、普通ならここで「志望校変更」となるところです。
●春。皆さんご想像の通り、晴れてB校に合格しました。
最後は家庭教師の先生も、「模試の成績はダメだけど、なんか受かる気がします」と言うようになっていました。当り前です。その学校の(過去の)入試問題がすらすら解けるんですから。
●これが過去問主義の力です。
過去に出題された問題がすらすら解ければ、本番の問題も解けます。
これ以上に当たり前の理屈はありません。
●ちなみに入試の成績も真ん中よりは上だったようです。
特に驚いたのは、社会と理科の成績でした。いずれも知識問題が多く、さすがに過去5年内に出た問題がもう一度出る確率は非常に低い教科です。それなのに、ふたを開けてみるとこの2教科もかなり得点できていたようでした。
言語化することのできない過去問の不思議の一端を見た気がしました。
「試験委員」の思い出
●そういえば、私は中学生のとき、(学級委員や風紀委員などのいわゆる委員会で)「試験委員」というのをやったことがあります。授業開始前の10分間のHRの時間に成績には入らない小テストが行われていたのですが、その問題を配ったりする仕事です。
問題は基本的に先生が作成していました。ところがある日、私が呼び出され(たぶん面倒くさくなったんでしょう)「○○←私、明日からお前が問題作れ」みたいな話になってしまいました。
条件は一つで、「教科書に書いてある内容をそのまま、あるいは、教科書に書いてある内容から正解を導ける問題を作ること」でした。
同学年の生徒全員が私の作った問題を解くわけですから、私も気合を入れて、色んな工夫を加えながら問題を作ったのを覚えています。
その結果出来上がったのは、皆さんご想像の通り、いたずらに難しい問題になるわけです。気合を入れて、工夫を凝らしたりすると、ほとんどの場合、受験者のレベルを度外視した碌でもない問題が出来上がるのは世の常です。
新司法試験の初期(サンプル・プレ・第一回あたり)はその身近な実例でしょう。
●何の話をしたいのかというと、試験問題というのは、その向こう側に生身の人間がいるということです。当り前じゃないかと思うかもしれませんが、本当にそうでしょうか。皆さん、試験というと何だか客観的で無機質な「制度」のようなものが向こう側からやってくるように考えていないでしょうか。
●知識問題ばかりの教科ですら、過去問を完璧にしていると必要以上に得点できてしまうという「謎」としか言いようのない先ほどの現象は、やはり繰り返し過去問を解く中で、出題者の思考パターンやクセといった表面的に認知できる以上の潜在的な「情報」が入ったからだとしか解釈できません。
受験指導ふたたび
●中学受験に話を戻します。
もうひとりも、兄と同じB校を第一志望にすることになりました。勉強方法はもちろん過去問ぐるぐるです。
彼女は兄貴よりも多少出来がよく、模試の成績は「合格可能性50%」が2~3回、たしか一度は60%を叩き出すという優秀さでした(といっても半分以上は40%以下でしたが)。
すでに上の子の経験があるのでもうこれだけで100%受かった気になってしまいますが、通常はこの成績でようやく「受かるか受からないか五分五分」といったところかと思います。
●春。もちろん結果は合格でした。これが過去問主義の力です。
過去に出題された問題がすらすら解ければ、本番の問題も解けます(しつこい)。
●どうやら(ぐるぐるし過ぎて)入試の順位が一桁台だったようで、保護者が初年度からよく分からない「なんとか委員」のようなものをやらされる羽目になってしまいました。親がその委員をやってると子どもが一桁合格であることがバレてしまうので、しばらくの間「○○ちゃんってすっごい出来る子なんだよね」みたいな事実誤認が蔓延ることになりました。
●もちろん一桁合格は過去問主義というドーピングのなせる業でしたから、入学以降、彼女の成績はどんどん下降していき、「出来る子」という称賛(誤解)は次第に「出来ない子」という陰口(正解)に置き換わっていきました。
しかしまあ、これもまた過去問主義の力なのです。
●その後、大学受験か近づいてきて、「中学受験のリベンジ」をしようかという話にもなったのですが、結局二人とも(付属校なので)そのまま内部推薦で大学に進学する予定です。
●こうして、私の試験に対する切迫した関心はとりあえず活動休止を迎えました。
試験からは多くのことを学びました。何より、私は試験という制度が大好きでした。
過去問主義の(とりあえずの)総括
●過去問主義は万能ではありません。
過去問の問題と答えが読めない場合、過去問主義は実行できません。その場合は、諦めるか、(もし時間があるなら)私の嫌いな(かどうかはどうでもいい)「積み上げ型学習」から始めるしかなさそうです。
ようするに、「弁護士になりたい」というイラン人には、とりあえず日本語のマスターから始めてもらうしかない、というのが(あくまでもとりあえずの)私の考えです。
●ちなみに、「もっと上手な指導者ならもっと上手にできたんじゃない?」という台詞は言ってはならない、というのが私の比較的強めの主張です(もちろん言ってはならないだけで、そういう指導者が存在するならそれはそれで素晴らしいことです)。
なぜかというと、方法論とは、そういう個々の指導者の「上手いor下手」とは独立した客観的な武器(マニュアル)として、いつでも誰でも使える形で世界に置かれていなければ本質的に用をなさないからです。
●もっとも、このことを司法試験で積み上げ型を採用する言い訳にしてはいけません。
司法試験の問題と解答を読めないなんて人はほとんどいません。もし現時点で読めないという人がいるなら、その人は「向いていない」人です。それでもやりたいというならやってもいいですが、私はおすすめしません。
●過去問主義の意義
過去問主義は万能ではありません。
いくら教えても過去問が読めるようにならない子どもを御三家に入れることはできないし、いい歳して満足に漢字も読めないロースクール生(←実際にローにいた)を弁護士にすることも(少なくともそのままでは)できません。
●しかし、
過去問主義が、その人のその試験に対する得点力を最大化する
のは(最低限)確かなようです。この点だけは保証できます。
●過去問主義で受からない人が、その他の方法なら受かるなんてことは(その人が過去問主義とよほど相性が悪いのでなければ)ほとんどあり得ないでしょう。
過去問主義が、あなたを合格の一番近くまで運んでくれることは間違いありません。
「伸びる時期」と成功体験
●私は、積み上げ型学習の「急がば回れ」的発想には基本的に反対です。
ですが、それとは少し異なる↓以下の2つの一般論には意味があると思っています。
●一つは、人にはそれぞれ「伸びる時期」があるということです。
特に子どもなどは、1年前には何もできなかった(言ってる意味すら理解できなかった)ことが、たった1年待つだけで難なくできるようになってしまうことがよくあります。成人以降でも(広い意味でいえば)こういった現象は中年期くらいまでは普通にみられます。
たとえ今できなくても、時機を待つことでできるようになることは結構あるのです。
●もう一つは、成功体験です。
たとえば私は、「司法試験合格のために、まずはそれより易しい行政書士試験にチャレンジすることが一見回り道のようで近道だ」みたいな考え方には(さんざん述べてきたように)大反対です。
積み上げるのではなく、目的そのものに向き合うことが、正しい考え方であることはブログに書いてきた通りです。
●しかし一方で、
①司法試験など夢のまた夢であるような「能力」(←他に表現しようがない)の人
②そもそも何かに合格したり、不合格になったりといった経験すらしたことがない人
③普通に司法試験に合格するような人の「普通」がどういうものか想像すらできない人
etc…が、突然一念発起して人生の一発逆転を賭けて司法試験に参入(突入)してくることには大いに違和感があります。こういうタイプの人はほとんどが受かりません(多くの人は受験まで到達することもない)。
●そういう類の人に「目的とするものと同じことをしなさい」と言っても、そもそも彼らは「目的とするもの」を「する」ということが、一体どういうことをすることなのかが実のところ何も分かっていないので、彼らが彼らの頭の中だけで勝手に想像した(自分にとって都合のよい)「する」をするだけになるのです。
●(高校時代の思い出)
高1のときだったでしょうか。ある地元の大して有名でもない予備校の夏期講習にうっかり参加してしまったときの話です。私は平凡な公立高校の生徒でしたが、もちろん「平凡」とはいっても学区内ではそれなりの(東大に入る奴もまあ一応はいるよねくらいの)高校ではありました。
その予備校の夏期講習には、学区でも真ん中以下の高校の生徒が多数来ていました(ちなみに私の時代の「真ん中以下の公立高校」というのは、その高校の生徒の大半が大学に行かない・行けないことを意味していました)。
●授業開始前、その、高校受験の偏差値45くらいの学校に通っている生徒3人(A・B・C)が↓こんなことを話しているのが聞こえてきました。
A「早稲田とか慶応とかってさ、俺たちでも頑張れば行けるのかな」
B「俺たちじゃ無理だろー。ああいうとこ行くのは○校の奴らとかだろ」
C「でもさ、浪人とかして、そいつらより長く勉強すれば行けんじゃないの?」
A「そうだよ。○校の奴らより1年とか2年長く勉強すればいいだけだよ」
B「えぇー、俺は慶応入れるんだったら、1・2年遅れても全然いいけどな」
C「そうだよ。浪人して行けばいいんだよ」
●その後、3人は、「浪人」という当時ではむしろそうしなければ早慶なんて行けないのが当然だと思われていた「方法」について、まるで今まで誰も思いつかなかった斬新なアイデアをゼロから創造したかの如く興奮しながら、
「じゃあ俺は早稲田に行く!」「俺は慶応かな。だってなんかカッコいいじゃん」
みたいな話で盛り上がっていました(←これ、ほんとの話ですからね)。
そもそも、「浪人」という既存のワードを使って「創造」(妄想)をしている時点で、自分たちの会話の矛盾に気づいてもよさそうなものですが…。
●なぜこういうことになるか。
それは、彼らが人生で何もやったことがないからです。
試験で合格とか不合格とかそんなレベルで「やる」必要はありません。中間テスト程度でもいいのです。たった1週間でもいいから、何かを真剣にやったという経験が、その結果、成功or不成功に至ったという経験が、人生で一度もないことが、彼らの「素っ頓狂発言」の原因です。
こんな具合だと、何を考えてもすべてが妄想にしかなりません。
●このABCによく似た司法試験受験希望者を(Twitterなどで)稀に見かけます。こういう方には、是非とも(たとえば)行政書士試験あたりから始めてみることをおすすめしたいです。
ここで大事なのは、行政書士試験(合格)は、けっして司法試験の「前段階」「準備段階」ではない、ということです。そういう風に「積み上げ型」のプロセスとして位置づけてはダメです。
そうではなくて、行政書士試験それ自体を目的とするのです。そうやって行政書士試験そのものに向き合い、その目的を完全に達成するべく努力するのです。
●その結果得られるのは、司法試験に向けた法学的な準備ではありません。
ここで得られるのは、何かを目的に据えて、その目的に向かって努力をした結果、その目的を達成することができたという成功体験です。
言いかえると、何かを妄想ではなく現実に(←ここ大事)やってみたという経験です。
●司法試験にあっさり受かるような類の人は、人生で(細かくみれば)こういった体験を何十回と繰り返してきています。どこかで書きましたが、こういう類の人は、たとえば運転免許証試験さえ目的達成のためのタスクと見做したりします。
彼らが「強い」のは当たり前です。彼らは司法試験だけに強いのではなく、ありとあらゆる試験的なものに強いです。それは、このような(大量の失敗を含む)成功体験の蓄積ゆえなのです。
どうでもいい話
●雑感①で書いた日本○○が、私の予想(期待?)通りの成績でペナントレースを終えたことは素直に嬉しかったです。個人的には2022年の救いのひとつでした。
ふざけたことを言って(やって)いる人や組織が、正当にふざけた結果を得ることに、私たちは(公正という意味での)正義(ある種の真っ当さ)の感覚を覚えますが、現実にはなかなかそうならないことも多いので。
●日本○○というと思い出すのは、このチーム、昔は本拠地が東京だったんです。
かつて巨人ファンだった私は、幼い頃、両親に連れられて生まれてはじめてプロ野球(巨人戦)を観に行きました。もう相手チームがどこだったかも覚えていません。
ただひとつ覚えているのは、客席番号の下何桁かが何番とかだと「当たり」みたいな宝くじ的な企画があって、それに当選したことです。球場に当たり番号が表示されたときは、飛び上がるように喜びました。
●「ジャイアンツグッズが貰える」 そう思いますよね、普通。子どもでなくったって。
ところが、試合終了後、所定の受け取り場所に行って出てきたのは、「ハム」でした。
ハムです。人生であれ以上にデカいのを見たことがないレベルのハムです。もちろん縛られてるやつです。憧れのジャイアンツの試合に初めて来て、いきなり「当たり」が出て、それで貰ったのがハムです。
「なんでハムなんだ!」 親に抗議しました。親は「本拠地がどうこう…」とか言っていましたが、子どもの私にはよく理解できませんでした。
●「巨人戦で当たりが出て、ハムが出てきた」というこのエピソードは、今でも忘れられない子ども時代のちょっとしたトラウマとして記憶されています。
●日本○○の監督の話に戻りますが、日本に限らず世間の人々は、往々にして外形的パフォーマンス(今の言葉でいえばブランディング)ばかりに気を取られて、その人の本質(内容)を見ようとしません。
この監督には、本当に独自な(創造的な)ものなど一切ありません。その目を引く外見や言動からいったん目を離して、彼の言っている内容それ自体をよく聞けば、彼の思想(なんてものがあればですが)や言動が、戦前の修身から戦後の道徳教育に代表される、日本の近代教育の最大公約数によって作られていることが分かります。
●一言でいえば、積み上げ式の精神論(戦前)と、中身のない個性礼賛(戦後)です。
真に個性のある人間は、特に個性的になろうと色々いじくらなくたって、自ずと個性的になってしまいます。この「なってしまう」ことこそが個性の本質であって、外形をいじくりまくって個性を「演出」することは何も個性的なことではない。私には、彼のあの奇抜な外形は、彼自身の凡庸な中身(積み上げ式精神論)を覆い隠すためのコーティングにしか見えません。
●さっき、「かつて巨人ファンだった」と書いたのは、もちろん今は違うからです。
長嶋さんという(私は現役時代を知らないし、正直どうでもいい)かつての大スターが、かつては大スターだったという理由だけで、指揮官としての無能さを一切問われず監督に居座り続けたことに耐え切れなくなり、気がついたときには大好きだった巨人が大嫌いになっていました。
●私は試合をしっかりと見ていたので、たとえば彼がある若手選手を、他の監督なら絶対にやらないような非情な方法で制裁(ようするに公開処刑あるいは見殺しに)し、再起不能にしたことなどをよく覚えています。
●このときは解説の(ジャイアンツ関係者の)堀内氏も、さすがに「こんなことをしたら、この選手は二度と立ち上がれなくなりますよ」と(抑制的ながらも)怒りをあらわにしていました。
でも、「ミスタージャイアンツ」は、何をしても許されるのです。
私には堀内氏の言葉(怒り・警鐘)は痛いほど伝わりましたが、普段からジャイアンツファンを名乗っていた人たちは、その時どう感じていたのでしょうか。是非聞いてみたいところです。
私が想像するに、きっとこういうとき、彼らは「聞いていない」のです。自分にとって都合の悪い話は、上手に(卑劣に)スルーしているのです。
政治に限らず、党派性は常に人を盲目にします。
●私は、彼のネームバリューや個性的とされるキャラクターに興味はありませんでした(もっとも、さすがに長嶋氏には「個性的」と言わざるを得ないキャラクターは存在したと思います)。
私は、そういう外形ではなく、あくまでも指揮官としての采配(内容)を見ていました。
彼が言われるほどには人間的に魅力に富んだ人物ではなく、指揮官としても無能であることは、試合をしっかり見ていさえすれば自明でしたが、ほとんどのジャイアンツファンにはその現象すら認識できていなかったと思います。
●以上、雑談でした。
私が「党派性」から離れて内容しか見なくなったきっかけのひとつです。
ロースクール制度の不当性
●「党派性」で思い出したので、最後にもう一度だけ、ロースクール制度が如何に不当なものかをきちんと確認しておきたいと思います。
●ロースクール制度が正当といえるためには、何らかの一般的に通用するメリットが言えなければなりません。
●「私にとっては良かったんです![]() 」
」
↑こんな台詞をいくら言ってもダメです。こんな一般化できない個人的意見をどれだけ集めたところで、そんなのはまさに「それってあなたの感想ですよね」にしかなりません。
●「私にとっては良かったです」なんて、親から裏口入学のお金を出してもらった学生が、
「裏口入学という制度を悪く言う人がいるけど、私にとっては良かったもんねー」
と言うのと構造的には何も変わりません。単にローは合法なだけマシというだけです。
●いくつか検討してみましょう。
ロースクールが出来たことで、よりお金がかからなくなったか ⇒×
ロースクールが出来たことで、より時間がかからなくなったか ⇒×
ロースクールが出来たことで、より多くの人に門戸が開かれたか ⇒×
ロースクールが出来たことで、撤退を自己決定できるようになったか ⇒×
日本のような(歪な)ロースクールが他の先進国に存在するか ⇒×
●公平に○も探してみましょう。
ロースクールが出来たことで、大学は得をしたか ⇒○
ロースクールが出来たことで、大学(教授)が好き勝手できるようになったか ⇒○
ロースクールが出来たことで、貧乏人を排除することができたか ⇒○
ロースクールが出来たことで、金持ちを有利にすることができたか ⇒○
ロースクールが出来たことで、撤退を強制できるようになったか ⇒○
●一番最後の「○」だけが、私がかろうじて「ロースクールの意義」をみとめるところです。
いささかパターナリスティックな発想ではありますが、たしかに司法試験も法曹の職も、人生を賭けてまで手に入れに行くものではない(そのように考えてはいけない)と思うので、個人ではなかなか決断することができない撤退を強制できる制度が存在すること自体は必ずしも悪いことではない、と考えることは(一応は)できると思います。
●なお、
「ロースクール制度の意義(教育内容)が検討されてないじゃないか」
「それ以前までの制度(旧司)の弊害が検討されてないじゃないか」
と文句を言いたくなった方は、(そんなに長くないので)↓これを読んでください。
(一番下の、【人間の党派性と誤魔化しの一考察】 のところだけで結構です)
●読むのが面倒な方のために以下要約すると、
(様々な不公平性の塊である)ロースクール制度が、それでも正当と言えるためには、
①その制度がなければ、十分な適格性を備えた法曹を養成するのは難しい
ということが(あくまでも「あなたの感想」ではなく一般論として)言えなければなりません。
●そして、それが言えた場合、論理必然的な帰結として、
②その制度ができる前の制度(旧司)は、①を欠くため、ダメな制度であった
ということが(少なくとも傾向的には)言えるはずです(←言えなければおかしい)。
実際、①と②は本当によく聞かれる台詞です。
●ところが、ですよ。その①②から(またまた)論理必然的に導かれざるを得ないはずの、
③したがって、旧司で合格した法曹の多くは、法曹の適格性を欠いたダメな法曹である
という台詞は、「ふざけるのもいい加減にしろ」と言いたくなるくらい全然言われていません。
●もっと簡単にいえば、旧司組の先輩法律家たちに向かって、正面切って
「あなたがた旧司組は、法曹の適格性を欠いた人が多いですね」
と言い放った人を私は知りません。
●…もちろん、↑これがどれほど意地の悪い指摘であるかは私も承知しています。
他ならぬ皆さんこそが、本当はそんなこと1ミリも思っていない、ということを私もよく知っているからです。
●まあ、ようするに一言でいいますが、皆さん、自分が強く関わったものを、自分が強く関わったという理由だけで、無闇に擁護しすぎなんですよ。
ほんと、体制順応すぎて気味が悪いです。
●今回はロースクールの話ですが、人生の大事な場面で↑こういう態度に傾いていく人間は、実際は「今回」に限らず、人生の様々な場面でこういった「阿り」を繰り返します。
日本の弁護士さんには広義の「野党精神」を持った方が多いですが、しかし性根が↑こんなんだから、力の大きいものが寄ってくるとすぐそれに取り込まれるんです(別に弁護士に限らず日本人はみんなそうなんで安心してください)。
出羽守は私も嫌いです。しかしここは断言してもいいですが、たとえばアメリカで同様の制度改悪が行われたとしたら、学生から、弁護士から、そして大学教授からだって、もっとはるかに大きな声が上がったはずです。日本人みたいに唯々諾々と黙って従いはしなかったはずです。
●もちろん、声を上げたところで現実(制度)は変わらないでしょう。それが普通です。
社会には完全にイノセントな制度なんて滅多にありません。ほとんどの制度が、矛盾を孕んだ、特定の人や組織の利益のために(も)ある、多分に不当なものです。それは仕方がない。
●それは仕方がないですが、しかし、そんなものに「自分が強く関わった」という理由だけで、いちいちいちいち「私には良かったです!」「良かったんですっ!」「先生!」なんて阿っていたら、それはもうほとんど「地上の楽園」と変わらないじゃないですか。
●矛盾があるのは普通のことだし、不当な制度から利益を得ることがあるのも仕方ありません。この俗世界を生きる以上、誰もが何らかの利権の内側にいて、そこから何らかの利益を享受している。そういうものから完全に自由になることはできません。
しかし、それに「おかしい」とツッコむことができなければ、現実は永遠に止揚されません。
●問題なのは、おかしな制度がある(出来る)ことではないのです。
(そんなものは、100mも歩けば3つくらいは見つけることができるでしょう)
●問題なのは、どこからどう見てもおかしい制度を、(あなたが)正しく「おかしい」と、社会正義を実現すべき弁護士になってまで、つまりは、ロースクールの拘束から解放されてまで(←ここが一番大事)言えないことです。
●言っておきますが、これは普通の意味で洗脳ですからね。
試験が好きだった理由
●なぜ私が試験が好きだったのか。
どこかで書こうと思っていましたが、やっぱりこの流れで書くのが一番いいかなと思います。
●理由は単純です。
日本の(諸々の)試験ほど、客観的で公正な制度はないからです。
外国人からみても、日本の試験制度ほど平等なシステムはない(少ない)ようです。
●私は必ずしも試験が得意な人間ではありませんでした。いえ、必ずしも・・・ではなく、ほとんど人生を通して、私はむしろはっきりと試験に弱いほうの人間だったと思います。
●しかし、私にとっては、人生を通して客観的な試験(入学試験や予備校の模試など)よりもずっとずっと不得意(苦手)であり続けたものがありました。
それは、学校教育制度内における教師からの評価です。
●もう少し具体的にいえば、学校の通知表の成績・・・はまだマシとして、散々だったのは教師からの(主観的)評価です。小中高の12年間を通して(極めて稀な例外を除いて)私は教師たちから一貫して嫌われていました。
●もちろん、思い返せば私にも大いに問題はありました。
まず、このブログで何度も書いてきた通り、私は生来の(正真正銘の)怠け者でしたから、小学校から高校まで、授業を「聞いた」という記憶がほとんどありません。当てられたらその場でアドリブで答えるだけで、授業中はずっと脳内映画(?)を鑑賞しているか、教科書などにひたすらマンガを書いているかでした。
中間・期末テスト前の3日間くらいを除いては、家で勉強をした記憶もほぼありません(ただそんなのは一般的な日本人としてはごく普通だと思うんですけどね)。
割と細かい性格でしたし、倫理的に不真面目だったわけではないので、遅刻や欠席や忘れ物や素行不良などはほとんどなかったのですが、こと勉強に限っていえば、学校生活全般を通じてほぼ何もしていません。
●不真面目というよりも、より正確にいえば「生命力」を欠いた人間でした(まあ今に至るまでずっとそうですが)。子ども(青少年)に特有の生命力がないので、学校生活においても、教師が好きそうな(大人の目に分かりやすくそれとして映るような)「生徒らしさ」のようなものがカケラもなく、そのことが更に教師の不興を買う原因になったと思います。
●私にも、たとえばロースクール制度なんかに阿ってみせる能力(=忖度力)があればよかったのですが、不幸にも私にはそんな風に都合よく自分を騙すことができるようなハイスペックな「能力」は備わっていませんでした。
●中3のとき、通っていた中学にあった「説教部屋」と呼ばれる問題児が生活指導を受ける場所(⇒いつもはただの茶室)に、(元)担任から呼び出しをされたことがあります。
過去、この説教部屋に呼ばれたことがあるのは、バイク(←ここでアウトだろ)で事故った子、万引き、シンナー、売○(援助○際という言葉はまだなかった)、走行中の電車に爆竹を投げ入れた子(←このあと少年院に行った)、夜の校舎窓ガラス壊して回った15歳(笑)etc…多彩な顔触れの生徒たちでしたが、いずれもいわゆる「問題児」たちです。私のような素行に(全く何も)問題のない生徒が呼ばれるのは異例でした。
●説教部屋からクラスに戻ると、学校の番長(←当時はこんなのがまだいた)から、
「○○(←私の名前)、お前、いったい何やったんだ」
と直々に訪問…というか弔問…というか尋問(?)を受ける名誉に与りました。
●説教部屋で何度も何度も繰り返し言われた台詞は↓これ(だけ)です。
「○○(←私の名前)、お前、もうちょっとどうにかならないのか」
●「もうちょっと?」「どうにか?」・・・???
サンドウィッチマンじゃないですが、私には「ちょっと何言ってるか分かりません」でした。
学校の評価が悪かったといっても、成績は400人中30番くらいでしたし、(業者や自治体が行う)より客観的な試験だと10番くらいでしたから、私自身の素行の問題のなさを併せて考えると、私が特に狙い撃ちされる理由など、どこにもないとしか考えられませんでした。
●もっとも、この(元)担任の先生に対しては、(ただただ私に対する不快感を露にするだけの教師が多かった中で)私に対する教師一般の不満を何とか言語化しようと努力してくれたという点では感謝をしています(ただ、もうちょっと実社会の観点から具体的に言ってほしかったな)。
●ちなみに、この「説教部屋」のエピソードを後に中村さんにしたのですが、意外にも中村さんには「すっごい分かる」と言われてしまいました。
私には私自身の人生全体(つまりは学校にいないときの私)が教師に見えているはずがない(見えてたら超能力じゃん)と思っていたのですが、家庭教師等々の経験が豊富な中村さんが言うには、「目の前にいる生徒が、目の前にいないときに何をしているか or していないか、そういうことを含めて教師には見えている」のだそうです。
私も大人(?)になり、まあたしかにそういうものなのかな、と今や思えるようになりました。
●思い出話を書いていたら話が壮大に逸れました。
ようするに、学校教育時代を通して私が教師に嫌われ続けた理由は、極度にやる気がなく、実際ほとんどやっていないにもかかわらず、しかしまあまあ成績上位な生徒だったからです。
教師にとって、こういう生徒ほど気に入らない存在はいません。
●学校という社会では、求められるのはプロセスであって、結果ではない。
↑これが、私が学校教育で学んだほとんど唯一の知識です。
●試験の話に戻りますが、やる気のない人間が試験に強いはずがありません。
なので、別に私は、試験に強かったから試験が好きになったのではありません。
そうではなくて、試験の客観的側面、つまりは試験の点が高かろうと低かろうと、ただ結果だけを評価してくれるという試験のもつ風通しのよさ(透明性・公平性)が、(教師の主観的評価によってずっと辛い思いをしてきた)私には救いだったわけです。
それが私が試験が好きだった理由です。
中村さんの思い出 ~その二~
●論文不合格をきっかけに覚醒し、驚異の1日20時間勉強を開始した中村さん。
ちょうど秋から冬にかけての3ヶ月くらいの間、(勉強会ではにこやかな顔をしていたものの)やってること自体を冷静にみればそれはほとんど狂気の沙汰と言ってもよく、この間の中村さんの集中力には尋常でないものがあったと思います。
●私は特に具体面で付き合えることはないので、たしか一緒に答練の問題を書いたりしていました。私の答案スタイルは「極限まで短く書く」というもので、このブログと正反対…。
対する中村さんは(急激な実力の向上もあってか)もの凄い早さで全ページを埋めてしまうことが多かったように記憶しています。
●この時期は特に民訴・刑訴を中心にやっていました。
いちおう2人の答案スタイルの違いが鮮明だったので、比較対象にはなったかな…と思いたいところですが、まあ正直そんなに役に立てたとは思っていません。
●あるとき、ふと中村さんが自分の(盛りだくさんな)答案を評して、「なんか僕、ベテ化してきてるような気がする」と(反省気味に)呟いたのを印象深く覚えています。
答案を長く書いて「反省」する人がいる、という事実に軽くショックを受けました。
●ともあれ、この時期ほぼ文字通り「狂気」の如く徹底的に訴訟法を詰めたことが、中村さんのプロセス重視の方法論(4段階アルゴリズム)を生みだしたのではないか、と私は勝手に思っています。
●年明け。
中村さんの怒涛の勉強三昧に終止符が打たれる時がやってきます。
冬の寒い気候で、中村さんが風邪を引いてしまったと記憶しています。
たしか勉強会もお休みしたような。いずれにしても年末年始でしたし、ここでふわっと一息ついたことで、これまでの溜まりに溜まった疲れが一挙に放出されたのだと思います(というか放出されなかったらヤバかったと思います)。
●年明け最初の勉強会…の昼食の席(@今はなきシェーキーズ高田馬場店)
中村さん(N)は3ヶ月前とは打って変わって力なさげ(目も虚ろ)でした。
私「風邪は大丈夫ですか?」
N「あぁ、風邪はもう治りました。今日は相談があって…」
私「なんですか」
N「えっと、僕、司法試験やめようと思って」
私「・・・(うわー、いきなりぶっこんでくるなぁ)」
●ランチは突如緊迫の場に
私「(こういうときはいきなり結論めいたことは言わないことにして…)」
「やめてどうするんですか?(ここはとりあえず質問が無難だろう)」
N「働きたいです。大学受験の講師とか。ぼく天職だと思うんですよ」
私「そうですよね。でもなんで司法試験の講師じゃダメなんですか?」
N「今すぐに講師やりたいんですよ」
私「(それ、理由になってるか?)」
「でも、せっかくこんなに勉強してきて、今やめたらもったいなくないですか?」
N「正直、いま法律を見るのも、考えることさえ嫌なんです」(辛そうな顔)
私「勉強なんかしなくていいじゃないですか(←よし、ここは私の得意分野)」
N「・・・・・」
私「いったん勉強から離れて、もし続けたいと思ったら戻ってくればいいし、戻りたくなければそのときは駿台でも河合でも行けばいいじゃないですか」
●…という感じで「今日この場では結論は出さないでいったん保留する」という自殺志願者への対応マニュアルみたいな返しを知らぬうちにしていました。
●結局、ほどなくして中村さんは受験勉強に復帰し、とりあえず事態は落ち着きました。
その後は、20時間とかそんな破滅的な勉強はしなくなったようです。
自由意志か決定論か
●このブログには、
①人間の自由意志を尊重し、人は方法と努力によって目的を達することができるとする面と
②決定論的人間観を強調し、人はなるようにしかならないと主張する2つの面がありました。
最近の流行は圧倒的に②なのですが、私がどちらかといえば①のほうを多く語ってきたのは、「②でファイナルアンサー」と簡単に言い切れてしまう人に対して、どうしても言っておきたいことがあったからです。
●それは、「中村さんの思い出~その二~」の続きで言うなら、こんな言い方になります。
「自分を根底から否定するほど勉強方法を見直して、1日20時間努力して、それでも受からないっていうなら、そのときは、人はなるようにしかならない(②)って認めてやるよ」
●逆にいうと、「あなたがそこまでやっていないのであれば、あなたがこの勝負を降りる際に、私には最初から受かる能力がなかった(②)なんて口が裂けても言ってほしくない」
ということです。
●やめてもいいんですよ。嫌になったらいつでもやめればいい。私はそう思っています。
でも、それは単にあなたが司法試験に愛想を尽かしたから(あるいは結局のところ本気で受かる気がなかったから)なのであって、あなたに「能力」がなかったからではない。
このことだけはきちんと確認しておきたいです。
●私なんか、自分がローで1日5~6時間、2~3年も勉強すれば絶対受かってたよな…と今でも(揺るぎなく)思ってますからね(思うのはどこまでも自由![]() )。
)。
●…私のことはいいんでした。
要は、今回の思い出話を読んで、優秀とされる人がなぜ優秀であるのかを、最後にもう一度だけ真剣に考えていただきたかったわけです。
そのことを少しでもお伝えることができたなら、これほど嬉しいことはありません。
中村さんの思い出 ~その三~
●中村さんが修習生のときの話
修習生になっても、中村さんは時間をみつけては勉強会に顔を出していました。
ある日、私は伊藤塾の論文マスターの解答例をレジュメ化するという「勉強」をしていました。
具体的にいうと、解答例を(もっとシンプルに&解答例の構造・流れがよく分かる形で)自分の言葉に置き換えながらルーズリーフ1枚にまとめ直していたのです。
●ようするに、
・問題を読んで→答案構成をして→答案を書く、という通常の作業ではなく、
・解答例を→答案構成のような形に書き直していた、のです。
つまりは、解答例(の主要部分・枠組み)を理解・記憶するような勉強法です。
●このやり方で1科目あたり数十問を理解&記憶して、自力で答案を書く足掛かりにしよう。
私はそう考えていました(ロー入試ならこれで十分いけると思いますが)。
私は知識がないことが不安(コンプレックス)だったので、このやり方で手っ取り早く全科目の論文知識を覚えてしまおうと考えていたのです。
●横にいた中村さん(N)が突然怒り始めました。
N「何をやってるんですか!」
私「あ、いや、答案が書けるようになるには最低限知識が必要だと思って」
「それに、知識を仕入れるのも答案それ自体を使ったほうがいいでしょ(過去問主義!?)」
N「NOAさん…何もかも間違ってます。根本から間違ってます」(頭を抱えている)
「解答例は、答案(構成)を書いた後に読むんですよ。先に読んでどうすんですかっ」
私「でも、私には答案なんて書けないですよ」
N「ほんとですか?」
私「ほんとですよ」
●中村さんは「ふぅ~」とため息をついた後、カバンの中から過去問を取り出しました。
N「じゃあ、この問題を読んで、解いてください」
私「(解けない…っつてんだろ)」「あーいやー」
N「思考過程を口で言っていってもらえばいいですから」
私「え~と。まず、この問題の論点は・・・○○って論点なかったでしたっけ?」
N「そうじゃないんですよ!論点なんてどうでもいいんですよ!」(このとき怒りMAX)
私「でも、論点知らなかったら、合格答案は書けないじゃないですか」
N「へぇ~そうですかねー」(今度は笑っている)
●私が「解かされていた」のは刑法の過去問でした。
N「NOAさんが検察官なら、甲をどうしたいですか?」
私「そうですね。死刑…じゃなくて殺人罪(199)にしたいかな」
N「じゃ199条が成立するか検討していきましょう。刑法の解き方の手順は知ってますよね」
私「論点は知らないけどそれなら分かります。実行行為、結果、因果関係…とかですよね」
N「それでは、その手順で事案を検討していってください」
●数分後、処理手順に従って一つ一つ事案を検討していくが、最後につまづく。
私「いろいろ考えましたが、やっぱりこのケース、因果関係認めるの難しくないですか?」
N「あぁ、いいですね。その場合どうなります?」
●本当はもうちょっと詳細なプロセスを説明したいところですが、(路線変更して)今度は殺人未遂罪に繋がるルートを(答案表現っぽく)中村さんに口頭で伝える。
N「はい。合格です」
私「は?」(なに言ってんだ?)
N「本試験でも未遂ルートの合格答案はいっぱいありましたから、これで合格答案です」
私「いやいやいやいや。これで合格なんだったら、知識ゼロで受かっちゃうじゃないですか」
N「そうですよ?(得意げな顔)。特に論文は、知識ゼロでも合格答案書ける人はいますよ」
私「いやいやいやいや。それじゃ何のためにみんな論証集とか…」
N「だからそういうことじゃないんですよ。既遂とか未遂とか、規範とか論証とか、そういうのは派生的なことに過ぎないんです。今回やったように処理手順を1コも飛ばさずに丁寧に事案と突き合わせて検討していって、その過程を結論まできちんと一本の筋として表現できれば、それで合格なんです。そこが難しいだけなんで、逆に簡単な人には簡単なはずなんですよ」
●このとき検討した問題が、司法試験の論文試験の中でも最も知識を必要としない(と今や私も思っている)刑法の問題であったという点を割り引いても、↑このエピソードはどうしても皆さんにお伝えしておきたかったです。
できれば、実際の講義やガイダンスなどで、皆さんご自身で実感していただきたいです。
●このとき私が受けた衝撃は、この短い回想ではなかなか伝わらないかもしれません。
しかし、この日を境に、私も(中村さんと同様に)司法試験の本質が知識ではないことを完全に理解するに至りました。
●同時に、過去問の真の重要性(過去問という教材の本質)を完全に理解したのも、間違いなくこの日だったと思います。
(雑感② おわり)