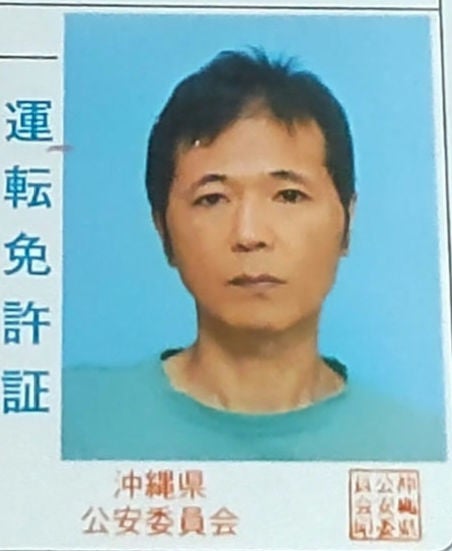お試しブログ
ブログの説明を入力します。 反物製作にお繋ぎお忍びお試し
プロフィール
テーマ
カレンダー
ブログ内検索
2016年02月19日(金)
もう1つの 明治維新 その4
テーマ:古代 (こだい / 誇大) もうそう宗教は世界の人々を大きく動かし、それに付随する文明は生活習慣や経済活動にも通じ、国境をもまたぎました。
日本人は 「わたし無神論です」 と人が多いというが、かなり古くから日本人の心を動かす 「魔法 (まほう) 」 のようなものが存在している事を イエズス会 は察知していた。
イエズス会が持ち込んだ 「宗教」 にも『経済と政治』が付随し、彼らは諜報活動も行っており、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康が登場する不安定な戦国時代まっただ中に来日していました。
*イエズス会 ≒ CIA / 諜報機関
戦国大名・織田信長、豊臣秀吉、徳川家康は、イエズス会の背後にある 「政治」 を警戒しつつも『経済』を利用していた。3者とも、前半は開封 ⇔ 後半は封印しているように思われます。
ー・ー
「応仁の乱」 以前の守護大名と以後に登場する戦国大名は大きく異なり、

http://s.ameblo.jp/yuukata/entry-12129262367.html 戦国大名・織田信長、豊臣秀吉、徳川家康などは、実力で権力を得たけど、実力 / 武力のみでは得られない何かが存在していました。
日本人の心を動かし、日本人を長期間に渡ってコントロールする。そうした何か 「魔法 (まほう) 」 のようなものを CIA (イエズス会) も気にかけていました。
ー・→
戦国大名の中、徳川家康が最終的に 「天下取り」 を成し 長期政権 を築きましたが、徳川家康が 「天下取り」 以上に苦労したのは『征夷大将軍』という称号で、織田信長も豊臣秀吉もその称号は得ていません。*征夷大将軍とは、夷 (おに / 鬼) を征す 「鬼退治の将軍」 を意味し、日本を統一する際に朝廷 (中央) から得られる称号で、天皇の 「血筋 / 家柄」 のようなものでした。
戦国大名・織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の3者は、どちらかというと 「夷 (おに / 鬼) 」 の血筋に近いが、3者とも『征夷大将軍』という称号を得ようとしていた。中でも徳川家康はかなり気にし、実際にその称号を得て 長期政権 を築く事ができたと云われています。
ー・→
徳川家康が『征夷大将軍』という称号 ← いわば、天皇の 「血筋 / 家柄」 にこだわるようになったのは、幼少期に人質として駿河国の今川家で生活した思い出からきているようです。*今川家は足利家の分家で源氏 (天皇の血筋) でした。
桓武天皇の子孫は桓武平氏、桓武天皇の子孫・清和天皇の子孫は清和源氏、天皇の摂関家・藤原氏、橘氏など‥ あり、武士は平氏や源氏といった氏名 (血筋 / 家柄) を欲していました。
ー(・・? ー・ー
どうして?‥
足利家が 「源氏」 なのか? というと、
平安時代の後期、桓武天皇の子孫 → 源義国 (源氏) まで さかのぼる といいます。https://ja.m.wikipedia.org/wiki/源義国
もとは、河内源氏の棟梁・源義家 (八幡太郎義家) の三男・源義国が下野国足利荘 (今の栃木県足利市) に住んだ。

引き続き、源義国の次男・源義康も下野国足利荘 に住み、その地名から足利義康と名乗り、源義国の長男・源義重はとなりの上野国新田荘 に住み、その地名から新田義重と名乗るようになったといいます。
*足利家も新田家も 「源氏」 → 足利家の分家・今川家も吉良家も 「源氏」
鎌倉時代 → 南北朝時代に、
下野国の足利尊氏は京都の室町幕府 (北朝) ⇔ 上野国の新田義貞は奈良の吉野朝 (南朝) *源氏は2つ朝廷に分別した。
ー・→
徳川家康の幼名は竹千代で、今川家 (北朝方 / 足利方) の人質になっていましたが、戦国時代の桶狭間で今川家と織田信長が衝突し、織田信長が勝利しました。https://ja.m.wikipedia.org/wiki/桶狭間の戦い
そして12歳の竹千代は、織田信長の子分になった。
大きくなった竹千代 → 徳川家康は、摂津国豊島郡の南朝勢力の手を借りていました。http://s.ameblo.jp/yuukata/entry-12128343194.html そのとき、同じく織田信長の子分・明智光秀は丹波国を拠点にしていた。
丹波国といえば?‥
http://s.ameblo.jp/yuukata/entry-12107818346.html 江戸城を築いた太田道灌の縁 (ゆかり) ある地で、太田道灌が江戸城を築く際、豊島一族と衝突していました。*太田家は室町時代に足利尊氏の母方・上杉氏とともに関東に来ている。http://s.ameblo.jp/yuukata/entry-12106272836.html
太田道灌は伊勢原市で亡くなっており、明智光秀と太田道灌も源氏で、明智家と太田家は 「桔梗の家紋」 を使用していました。
ー(・・? ー・ー
なぜか?‥

上野国新田荘はいま 「群馬県太田市」 という住所になっており、

太田市の近くに 「伊勢崎市」 という住所がありました。
伊勢原は伊勢のはら 凹 ⇔ 伊勢崎は伊勢のさき 凸 を意味しているようです。
ー・ー
主に 武蔵国の豊島一族は、南北朝時代には 「南朝方 / 新田方」 についており、武蔵国の豊島郡も摂津国の豊島郡も 「南朝方」 の拠点であったのか?‥ 思えて来ました。
そうすると?
竹千代は人質生活に不満があったのか?
戦国時代にも 「南北朝の動乱」 が続いていたのか?‥ とも思えて来ます。
ついでに、
太田道灌が亡くなった後 → 北条早雲が関東地方にやって来ました。http://s.ameblo.jp/yuukata/entry-12110336940.html 北条早雲は、もとは 「伊勢氏」 で 「伊勢氏」 は『平氏』の 「血筋 / 家柄」 でした。
そのほか、豊島一族、北条氏も『平氏』
ひそかに、「源氏と源氏」 が亡ぼしあう間に『平氏』も来ている。
ー(・・? ー・ー
内容は違う方向に行っていますが、
戦国大名・織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の3者は 「源氏」 でも 「平氏」 でもなく、どちらかというと 「夷 (おに / 鬼) 」 の血筋に近いが、3者とも『征夷大将軍』という称号を得ようとしていた。
源氏 → 「南北朝の動乱」
源氏と平氏 → 「源平の争乱」
見えない →『伊勢神と出雲神』
神と鬼と →
かなり古くから日本人の心を動かす 「魔法 (まほう) 」 のようなものが存在している事を イエズス会 は察知していた。
日本人は 「わたし無神論です」 と人が多いというが、かなり古くから日本人の心を動かす 「魔法 (まほう) 」 のようなものが存在している事を イエズス会 は察知していた。
イエズス会が持ち込んだ 「宗教」 にも『経済と政治』が付随し、彼らは諜報活動も行っており、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康が登場する不安定な戦国時代まっただ中に来日していました。
*イエズス会 ≒ CIA / 諜報機関
戦国大名・織田信長、豊臣秀吉、徳川家康は、イエズス会の背後にある 「政治」 を警戒しつつも『経済』を利用していた。3者とも、前半は開封 ⇔ 後半は封印しているように思われます。
ー・ー
「応仁の乱」 以前の守護大名と以後に登場する戦国大名は大きく異なり、

http://s.ameblo.jp/yuukata/entry-12129262367.html 戦国大名・織田信長、豊臣秀吉、徳川家康などは、実力で権力を得たけど、実力 / 武力のみでは得られない何かが存在していました。
日本人の心を動かし、日本人を長期間に渡ってコントロールする。そうした何か 「魔法 (まほう) 」 のようなものを CIA (イエズス会) も気にかけていました。
ー・→
戦国大名の中、徳川家康が最終的に 「天下取り」 を成し 長期政権 を築きましたが、徳川家康が 「天下取り」 以上に苦労したのは『征夷大将軍』という称号で、織田信長も豊臣秀吉もその称号は得ていません。*征夷大将軍とは、夷 (おに / 鬼) を征す 「鬼退治の将軍」 を意味し、日本を統一する際に朝廷 (中央) から得られる称号で、天皇の 「血筋 / 家柄」 のようなものでした。
戦国大名・織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の3者は、どちらかというと 「夷 (おに / 鬼) 」 の血筋に近いが、3者とも『征夷大将軍』という称号を得ようとしていた。中でも徳川家康はかなり気にし、実際にその称号を得て 長期政権 を築く事ができたと云われています。
ー・→
徳川家康が『征夷大将軍』という称号 ← いわば、天皇の 「血筋 / 家柄」 にこだわるようになったのは、幼少期に人質として駿河国の今川家で生活した思い出からきているようです。*今川家は足利家の分家で源氏 (天皇の血筋) でした。
桓武天皇の子孫は桓武平氏、桓武天皇の子孫・清和天皇の子孫は清和源氏、天皇の摂関家・藤原氏、橘氏など‥ あり、武士は平氏や源氏といった氏名 (血筋 / 家柄) を欲していました。
ー(・・? ー・ー
どうして?‥
足利家が 「源氏」 なのか? というと、
平安時代の後期、桓武天皇の子孫 → 源義国 (源氏) まで さかのぼる といいます。https://ja.m.wikipedia.org/wiki/源義国
もとは、河内源氏の棟梁・源義家 (八幡太郎義家) の三男・源義国が下野国足利荘 (今の栃木県足利市) に住んだ。

引き続き、源義国の次男・源義康も下野国足利荘 に住み、その地名から足利義康と名乗り、源義国の長男・源義重はとなりの上野国新田荘 に住み、その地名から新田義重と名乗るようになったといいます。
*足利家も新田家も 「源氏」 → 足利家の分家・今川家も吉良家も 「源氏」
鎌倉時代 → 南北朝時代に、
下野国の足利尊氏は京都の室町幕府 (北朝) ⇔ 上野国の新田義貞は奈良の吉野朝 (南朝) *源氏は2つ朝廷に分別した。
ー・→
徳川家康の幼名は竹千代で、今川家 (北朝方 / 足利方) の人質になっていましたが、戦国時代の桶狭間で今川家と織田信長が衝突し、織田信長が勝利しました。https://ja.m.wikipedia.org/wiki/桶狭間の戦い
そして12歳の竹千代は、織田信長の子分になった。
大きくなった竹千代 → 徳川家康は、摂津国豊島郡の南朝勢力の手を借りていました。http://s.ameblo.jp/yuukata/entry-12128343194.html そのとき、同じく織田信長の子分・明智光秀は丹波国を拠点にしていた。
丹波国といえば?‥
http://s.ameblo.jp/yuukata/entry-12107818346.html 江戸城を築いた太田道灌の縁 (ゆかり) ある地で、太田道灌が江戸城を築く際、豊島一族と衝突していました。*太田家は室町時代に足利尊氏の母方・上杉氏とともに関東に来ている。http://s.ameblo.jp/yuukata/entry-12106272836.html
太田道灌は伊勢原市で亡くなっており、明智光秀と太田道灌も源氏で、明智家と太田家は 「桔梗の家紋」 を使用していました。
ー(・・? ー・ー
なぜか?‥

上野国新田荘はいま 「群馬県太田市」 という住所になっており、

太田市の近くに 「伊勢崎市」 という住所がありました。
伊勢原は伊勢のはら 凹 ⇔ 伊勢崎は伊勢のさき 凸 を意味しているようです。
ー・ー
主に 武蔵国の豊島一族は、南北朝時代には 「南朝方 / 新田方」 についており、武蔵国の豊島郡も摂津国の豊島郡も 「南朝方」 の拠点であったのか?‥ 思えて来ました。
そうすると?
竹千代は人質生活に不満があったのか?
戦国時代にも 「南北朝の動乱」 が続いていたのか?‥ とも思えて来ます。
ついでに、
太田道灌が亡くなった後 → 北条早雲が関東地方にやって来ました。http://s.ameblo.jp/yuukata/entry-12110336940.html 北条早雲は、もとは 「伊勢氏」 で 「伊勢氏」 は『平氏』の 「血筋 / 家柄」 でした。
そのほか、豊島一族、北条氏も『平氏』
ひそかに、「源氏と源氏」 が亡ぼしあう間に『平氏』も来ている。
ー(・・? ー・ー
内容は違う方向に行っていますが、
戦国大名・織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の3者は 「源氏」 でも 「平氏」 でもなく、どちらかというと 「夷 (おに / 鬼) 」 の血筋に近いが、3者とも『征夷大将軍』という称号を得ようとしていた。
源氏 → 「南北朝の動乱」
源氏と平氏 → 「源平の争乱」
見えない →『伊勢神と出雲神』
神と鬼と →
かなり古くから日本人の心を動かす 「魔法 (まほう) 」 のようなものが存在している事を イエズス会 は察知していた。