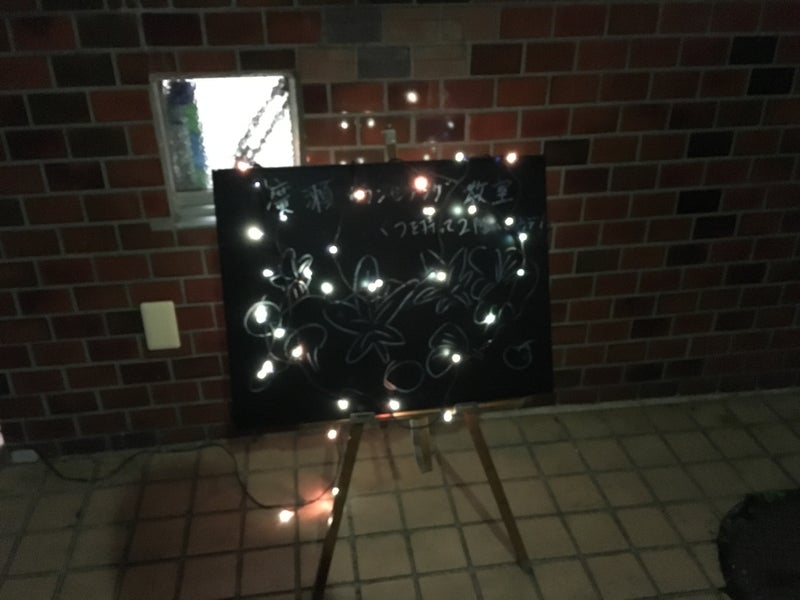こんばんは。しばらくブログを書いてなかったので久方ぶりの投稿です。
今月の教室の後の飲み会で、「小成は大成を妨げる」という言葉を紹介しました。
せっかくなので、これについて少し書いてみたいと思います。
この言葉の意味は、読んで字のごとく小さな成功は大きな成功を妨げるというものです。
吃音にあてはめると、随伴運動とか言い換えを使ったりすることで中途半端に適応できてしまうと、それでなんとか間に合ってしまう(小成する)ので、吃音と根本的なところから向き合ったり克服したりするまでに至らない(大成しない)というのが、一例として挙げられます。
かつての私は吃音の症状がそれなりに重く、随伴運動や言い換えでなんとかなるレベルではありませんでした。
特に難発が酷くて、どうやってもいつまでも言葉が出てこず、大学院のゼミでの発表が途中で中止になったこともあります。
それで、社会に出たり生活するためには直すしか選択肢がないというところまで追い込まれた結果として、この教室に来ました。
そして、現在では心理的にも症状的にもほぼ問題にならなくなっています。
私がもし随伴運動や言い換えでごまかせるレベルの吃音だったら、それで就活や仕事の場を乗り切ってしまい、今でも吃音のままでいたでしょうし、もっと年をとっても吃音のままでいたかもしれません。
そして吃音の悩みもそのままであったでしょう。
こういうふうに見ていくと、私は小成が得られなかったことによって大成を得ることができた、ともいえます。
吃音の症状が重い、というのは不幸なことですが、それによって小成を回避することができ大成に至ることができた、と考えるとむしろ幸運であったといえるかもしれません。
こうなると、吃音の症状が軽い方が「まし」であるという普通の見方が崩れてきます。
こんなふうに、ものごとを小成と大成とに分けて考えると、いろいろなことが見えてきます。
小成に安住しないためには、自分がいま小成と大成のどちらにいるか省みてみることが大事かもしれませんね。
ところで心理学でもこれと同じような概念があって、それは「補償」といいます。
よく例に挙げられるのは、サーカスの曲芸士には幼少期に運動神経が悪かった人が多いというもので、彼らは自らの劣等感コンプレックスを克服するために努力して、人並み以上の運動能力を得るに至ったというのです。
幼少期に人並みに運動ができるという小成を得ていたら、サーカスの曲芸士として脚光を浴びるという大成は得られなかったという訳ですね。
こんなふうにマイナスに見える要素も使い方によってはプラスに転じるための「てこ」になり得ます。
あらゆるものに対する見方を決めつけてしまわないで、常に柔軟でいることが大事です。