福岡市の博多あたりは古代、那津と呼ばれていたのが博多と呼ばれるようになったが、名称変更の時期がはっきりしない。7世紀後半から759年の間に変更されている。
多分、山口県か穴門国から長門国に名称変更された時期と一緒であろう。そうすると665年あたりとなり、白村江の戦いの敗戦直後と言うことになる。
博多湾の古図に草香江、冷泉津と言う入江が見える。草香と言う名は、現在の大阪の旧河内湖の東岸に日下(くさか、草香)があり、神武東征神話を思い出す。それでは、冷泉(れいせん、れいぜい、いずみ)はどうであろうか?大阪府和泉市(いずみ)に伯太(はかた)町があり、ここの地に伯太(はかた、博多)神社が鎮座している。この神社の創建が673年とあり、益々、辻褄があう。
博多の名前は、博多湾と大阪湾の湾岸の地名を一致させたものであった。すなわち、大阪湾から大和地域を博多湾から太宰府、甘木・朝倉あたりに対応させたことが理解できる。
665年に唐の朝散大夫沂州司馬上柱国の劉徳高が戦後処理の使節として来日し、3ヶ月後に劉徳高は帰国した。この唐使を送るため、倭国側は守大石らの送唐客使(実質遣唐使)を派遣した(参考)とあり、太宰府を畿内の都と思わせて、外交交渉したのであろうか!

参考
② 博多の名称の由来(参考)
博多の名称は「続日本記」(759年)の中に博多大津という名称があります。その名称の由来については、次のような説があります。
1.鳥が羽を伸ばしたような地形から「羽形」から「博多」となった。
2.泊潟からきた。
3.人や物が多く集まり、土地が広博であることからきた。
4.船の泊まる潟がなまった
③ 博多の名称の発生時期(参考)
中国の史書に家台・花旭塔・八角島などとも表記される。古代では那津と呼ばれていましたから、それ以降の名前ということになる。辞書にも、「奈良期から見える地名」とあります。「続日本紀」天平宝字3年(759年)3月24日条によれば、大宰府が博多大津・壱岐(いき)・対馬等の要害に船100艘以上を設置することを述べたことが見える。博多津は7世紀後半まで所見がある那津(那大津)の機能を継承したものであり、大宰府が警固すべき要害となっていた。
古く「那津(なのつ)」「荒津(あらつ)」「灘津(なだつ)」「冷泉津」「筑紫大津」と呼ばれていた博多湾は、797年(延暦16年)の『続日本紀』において「博多大津(博多津)」と記されているのが見出される(wikiより)。
④ 冷泉津、草香江

中世の博多津は、平安時代の1161年に平清盛により日本初の人工港「袖の湊」が建設されたことにより始まる。住吉神社蔵「博多古図」によると、当時の博多津は大きく「草香江」、「冷泉津」、聖福寺や櫛田神社などがある博多中心部とそこから橋で繋がれた「沖の浜」と言う出島により分けられていた(wikiより)。地名としての草香江、冷泉津、博多はこれより古いことが分かる。


室町期から見える地名筑前国那珂郡のうち中世博多津の異称「世宗実録」世宗5年(応永30年)7月己丑条に「博城冷泉津」と見える(李朝実録之部1/日本史料集成)のをはじめ,同年9月丙申条には「石城冷泉津」が見え,室町以降,朝鮮通交に従事する博多商人が頻繁に用いた呼称であった文明3年に朝鮮政府の申叔舟が編んだ「海東諸国紀」にも博多は冷泉津とも称されることが見える一方,「冷泉津」が日本側の史料に見えるのは戦国期であり,天文7年6月24日の大宰府宣に「冷泉津善導寺」が見える(善導寺文書/博多史料4)また,同11年11月6日の大友義鑑書状にも「冷泉津興浜」が見える(大友家文書録/同前)なお,近世に成立した「博多古図」では,博多の西方,那珂川の河口付近の湾入を冷泉津としているが,文献史料から見る限り,冷泉津は博多津の異称として使われており,この河口部を冷泉津と称したかどうか確認できない(jLogosより)。
国際的な名称として冷泉津を使用しており、大阪の泉大津との混同を意識している。現在の泉大津市(いずみおおつし)は大阪府泉北地域に位置する市で、和泉国の国府の外港(国津)であったことに由来する(wikiより)。
⑤ 伯太(はかた)神社、大阪府和泉市伯太町
祭神:
応神天皇 比売神 伯太比古命 伯太比売命 天照皇大神、小竹祝丸 天野祝丸 熊野大神 菅原道真 天児屋根命
式内社で、祭神は上記のように10柱もの神である。この事から総社的な神社だったのではないかと推測する向きもある。伯太比古・伯太比売の命は、伯太族の祖神であり、伯太族は、藤原不比等を養子として育てたと言われる氏族らしい。かっては博多神社、丸笠神社とも言われ、鎮座している山を丸笠山と呼んでいたそうだ。延喜式神名帳に、『和泉国和泉郡 博多神社』とある式内社。地名などで博多を通音の伯太(いずれもハカタ)とする事例は多く、当社も、今は“伯太神社”と称している。JR阪和線・信太山駅の南東約500mほどの住宅地の中に鎮座する。北側の道路沿いに鳥居が、境内正面に拝殿(入母屋造・瓦葺)、その奥、白壁に囲まれた中に本殿(千鳥破風付き流造・銅板葺)が建つ。末社等は無い。
当社境内に由緒を記した案内は不明だが、資料によれば「白鳳2年創建」と伝える(大阪府全志-1922・他)。年号の“白鳳”とは私年号であって公的な年号ではない。白鳳に対応する実年代については諸説があるが、そのひとつに天武朝(673-686)とする説(672-685・麗気記私抄)があり、それによれば、白鳳2年とは天武元年( 673)に相当する。書紀には、天武朝初期に神祀りに関する記述は見えないが、天武朝から持統朝にかけて、天照大神を頂点とする神祇体制が整備されたというからこれに付会した伝承かと思われる。当社に対する神階授与などの資料がみえず、創建後の経緯は不明。式内社調査報告(1986)によれば、明治5年(1872)に村社となり、大正5年(1916)、字下出の村社・管原神社を合祀し、字丸笠の村社・丸笠神社を飛地境内末社としたという
(⑧ 大阪湾岸に住吉大社、博多湾岸に住吉神社を置いた
10 旧三輪町の大己貴神社は奈良県桜井市三輪町の大神神社から来た(参考)
11 伯太彦神社、大阪府柏原市玉手町707

柏原市の式内社: 伯太彦神社(はかたひこじんじゃ)
所在地: 柏原市玉手町: 河内国安宿郡(あすかべぐん)
祭神: 伯太彦命
由緒: 伯太姫命と夫婦神で、この地域一体を支配していた田辺氏の氏神であろうと言われている。
この神社の祭神「伯太彦命」というのは珍しい。この神様を祀っている神社はそうそう無い。式内社としては近畿圏ではここだけであるし、そのほかにもおそらく近畿には存在しないのではなかろうか。この地は田辺郷で、田辺史氏の本拠地祭神は田辺史伯孫といわれている。田辺史氏は百済系渡来氏族で西文(かわちのあや)氏の管理下に文筆記録に携わった。この地を流れる石川は元は博多川または伯太川と称し流域は田辺史氏が開発した。仁徳朝渡来の百済人思須美と和徳を祖とするが、8世紀に冒姓上毛野君に改氏姓し、出自を神別とした。それにしても伯太(博多)というのは気になる。渡来氏族も北九州経由で近畿へ来たとすれば、田辺史氏も博多に住んで、それからここへ来たのかもしれない(参考、注: 報告者は和泉市伯太町の伯太神社を知らないらしい。また、この辺りから北九州に移動したことも知らないようだ!)。
上毛野君について、7世紀には、白村江の戦いにおいて、倭国主力軍の将軍として上毛野君稚子が朝鮮半島に派遣され一定の戦果を収めたたほか、三千は『帝紀』と上古諸事の記定に携わり、いずれも中央貴族として活躍した。天武天皇13年(683年)には上毛野朝臣、下毛野朝臣、佐味朝臣、池田朝臣、車持朝臣、大野朝臣のいわゆる「東国六腹朝臣」が「朝臣」姓を賜り、中央の中級貴族として活躍したwikiより)。
日本書紀には雄略九年七月条に「田辺史伯孫」が出てくる。注には、「田辺史は帰化系の氏。上毛野公と同祖。外交・軍事に活躍し朝廷貴族化した。弘仁私記序に『大鷦鷯天皇御宇之時、自百済国化来。』とある。」田辺史小隅は壬申の乱で近江側の将軍として戦ったが、大海人皇子側の多臣品治の率いる軍に敗れて逃走している(参考)。この為に北九州に左遷されたか!壬申の乱の時期672年と和泉市伯太町の伯太神社の創建時期673年が近い。
日本書紀は田辺史氏ら百済系官僚が書いた(参考)。
12 伯太氏と田辺氏と百済系渡来人の関係

大阪難読地名の本より
13 白村江の戦いの敗戦(663年)以降の渡来人の扱い
666年 百済人2000人を東国に移す
684年 百済人23人を武蔵に移す
687年 高句麗人56人を常陸に移す
687年 新羅人を下野・武蔵に数十人の単位で随時移す
716年 甲斐・駿河・相模・上総・下総・常陸・下野など7国の高麗人1799人を武蔵国に移し高麗郡を置く
<続日本紀より>
684年 百済人23人を武蔵に移す
687年 高句麗人56人を常陸に移す
687年 新羅人を下野・武蔵に数十人の単位で随時移す
716年 甲斐・駿河・相模・上総・下総・常陸・下野など7国の高麗人1799人を武蔵国に移し高麗郡を置く
<続日本紀より>
14 大宰府と田辺史氏の関わりが書かれている。
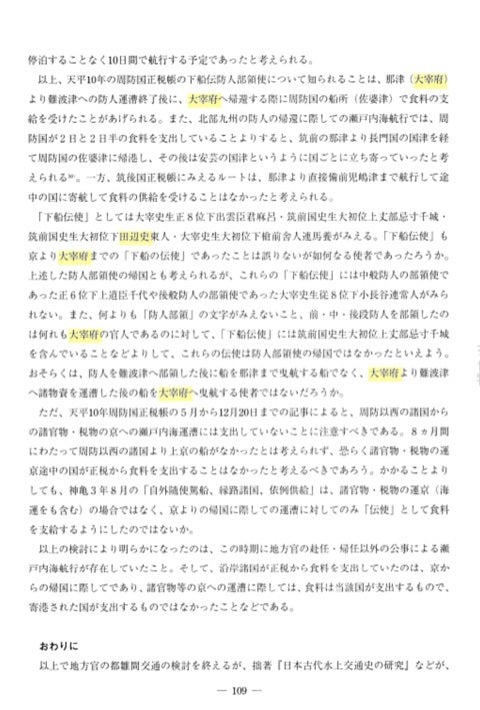
古代交通研究第11号(古代交通研究会 編集)
16 博多湾の一部が冷泉津と呼ばれた理由に、1222年に博多湾で人魚が捕獲され、勅使、冷泉中納言が検分に来たとの説明がある。しかし、公家の冷泉家の祖の冷泉為相は1263年生まれ、ちなみに藤原定家の孫、ほかに藤原朝隆って人が冷泉中納言って呼ばれてたようでだが、こちらは生没年は(1097~1159)で、ともに外れている。ちなみに、この人魚が竜宮から来たものとして、冷泉山竜宮寺に葬られ、竜宮寺に人魚塚ってのがあるそうです(ヤフー知恵袋より)。
やはり、この地の冷泉の読みは本来はレイゼイでは無く、ましてはレイセンでは無かろうから、(ヒヤイ)イズミと訓じたのが正しい。すなわち、大阪の和泉が(ヤマト)イズミの漢字表記であるから、ヤマト言葉としては同一地名である。
17 志賀島は「漢委奴國王」の銘がある金印の出土で著名だが、古代では「鹿の島」と呼ばれていた。この島は古代の豪族(海人族)阿曇氏(あずみ)の本拠地があった場所である。阿曇氏の祖神、「安曇礒良(アズミのイソラ)」が祀られる「志賀海神社」にはご神宝として鹿の角が数千本収められている。船のこぎ手を「鹿児」(かこ)というが、鹿は古代の海人族のトーテムであった。鹿児島は文字通り鹿児の島であって、海人族と関連のある地名には鹿の文字が多い。また全国に残る地名で、阿曇・安曇・厚見、渥見、熱海、泉などは阿曇氏が移り住んだ地であると推察されている(参考)。
19 この時期、東国との人々の入れ替えがあった
20 このころ高良大社と高樹神社の社殿ができた(参考)